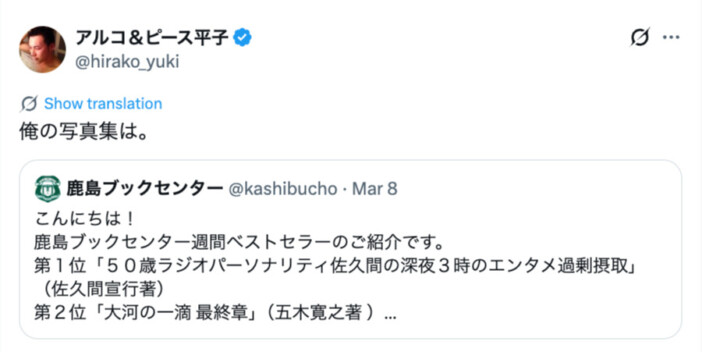【今月の一冊】直木賞受賞作からノンフィクション超大作まで、各出版社の「年間ベスト作品」を紹介

『オーバーヒート』千葉雅也(新潮社)

「小説の新潮」からは、2021年も時代を映し出す優れた作品が数多く刊行された。「多様性を尊重しよう」と謳われる昨今の風潮に一石を投じた朝井リョウの『正欲』、とある島に生きた一族の150年史を描ききった貫井徳郎の大河小説『邯鄲の島遙かなり』、西加奈子がロスジェネ世代の人生の闇に深く潜り込んだ『夜が明ける』など、読み手の認識や価値観を揺さぶるような小説が次々と発表され、混迷した時代における「文学の力」を改めて感じた一年だった。
ジル・ドゥルーズの哲学を主なテーマとしている哲学者・千葉雅也の小説第二弾『オーバーヒート』は、第165回芥川賞候補となった作品で、本書もまた次の時代を照射する一冊である。東京から大阪に移り住み、京都で教鞭を執る哲学者の「僕」は、リベラルな社会の欺瞞に毒づきながら、男たちとの肉体関係に耽溺し、年下の恋人の態度に一喜一憂する。言葉の世界と肉体の世界を対比的に描く中に、「僕」を取り巻く人々との関係性を星座のように描き出した小説だ。
本作を文芸誌『新潮 2021年 06 月号』に発表した直後に、千葉はリアルサウンドに社会学者・宮台真司の書籍についての選評「強く生きる弱者ーー宮台社会学について」を寄稿。「弱者の側には、特有の自治の空間がある。そこには特有の喜怒哀楽があり、ドラマがあり、生きがいがあり、そこにはやむをえずの面もあるが、やむをえずだけではない自律性があるのだ」と、弱者が持つ強さについて言及していた。混迷のあまり、善悪を単純に分割してしまいがちな今こそ、千葉の言う「弱者の強者性」に目を向けることが必要なのではないか。(松田広宣)