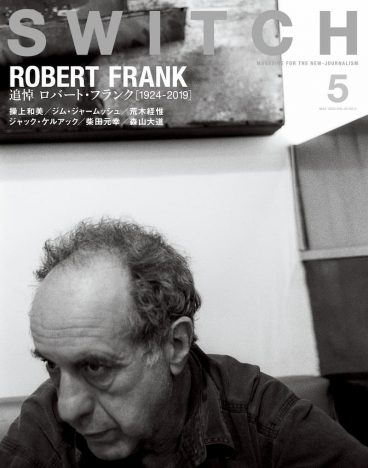不運の大型犬は、いかにして橇犬チームをまとめた? 名著『野性の呼び声』から見えてくる理想のリーダー像

「叩き上げの苦労人」。このフレーズを聞いて今真っ先に思い浮かぶのはそう、自伝的小説『マーティン・イーデン』が昨年ヨーロッパで映画化(映画でのタイトルは『マーティン・エデン』)され、今年日本でも公開となり話題を集めたアメリカの文豪ジャック・ロンドンだ。

舞台は19世期末のアメリカ。4歳の大型犬バックはカリフォルニアにある判事の屋敷で大切に飼われ、何不自由なく暮らしていた。ところが、幸せだった人生は突如暗転する。
バックはある日、博奕の借金苦にあえぐ屋敷の使用人に誘拐され、犬の販売業者に売り飛ばされてしまう。連れていかれた先は、ゴールドラッシュに沸くカナダとアラスカの国境地帯。ここでバックは、郵便輸送隊の橇を引く橇犬(そりいぬ)チームの一員として生きることになる。
温暖な気候のアメリカ南部で暮らしてきたバックにとって、大雪原での暮らしは未知のことばかり。テントなど用意されておらず、どこで寝ればいいのかわからない。少しでも気を抜くと、血に飢えた現地のエスキモー犬が襲いかかってくる。橇の引き方が下手だと先輩犬に噛み付かれ、御者から鞭を振るわれる。暴力がはびこる過酷な環境でバックは自力で仕事を覚え、苦痛に耐えられるだけの筋肉をまとい、仲間の食料を気づかれずに盗むような抜け目のなさを身につける。
彼は適応した。それだけのことだ。意識せずして自分を新たな生活様式に適合させていっただけだ
輸送隊の人間はバックのことを〈悪魔が二匹ついてらァ〉と評する。評の根拠は、彼が持つ強烈なエゴと闘争本能である。自分がリーダーでなければ気の済まないバックは、チームのリーダーであるスピッツを血で血を洗う抗争の末に倒し、その座を奪い取る。
新リーダーのバックがまず取り組んだのは、チームの綱紀粛正だ。怠け癖のある犬、気分屋の犬に制裁を加え、集団に規律が生まれる。そして自ら先導役となり谷を越え氷河を渡り、驚異的なスピードで輸送隊を目的地へ導いていく。
物語の主人公としてのバックは逆境に力強く立ち向かう、読者が応援したくなる主人公である。だがこんな専制君主型のリーダーが今の時代にいてほしいかというと、微妙な気もする。上昇志向と押しの強さに、こちらが付いていけず疲れてしまいそう。なにより修羅場に血の騒ぐタイプは、平時になると……。
その後も橇犬として活躍したバック。彼の主人は巡り巡って、北方地域での旅に憧れる南部人3人組に代わる。彼らの体現するリーダー像はダメな方の見本、計画性のない責任転嫁型のリーダーである。このタイプは、まず見積もりが甘い。暖かい季節には不要なテントにガラクタなど大量の荷物を詰め込み、案の定橇は動かない。荷物を減らして出発したはいいが、用意した橇犬が多すぎて途中でエサが足りなくなってしまう。
経験から学ぼうとしないのも、リーダーとして減点要素だ。毎回テントを張るのも片付けるのも上達せずに時間がかかり、スケジュールはどんどん遅れていく。なのに、自分たちのことは棚に上げて犬にはもっと働けと鞭や棍棒を振るうのだから、チームの士気は当然上がらない。飢えと疲れでヘトヘトとなるバック。キャンプ地で瀕死の状態の彼を見るに見兼ねて、3人組から強引に引き取ったのが、探鉱家のジョン・ソーントンだった。