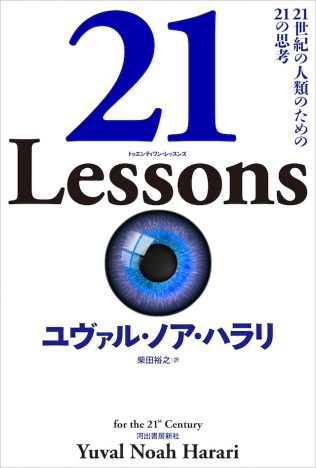中森明夫が語る、80年代精神と“青い秋”の生き方 「本当のお祭りはついぞ訪れなかった」

アイドル評論家の中森明夫による『青い秋』は、“新人類”と呼ばれた80年代のカルチャーを振り返りながら、今なお成熟せず“青い秋”の最中にいる自身の生き方を、ほろ苦い筆致で綴った自伝的青春小説だ。アイドルから思想家まで、実在の著名人をモデルとした登場人物たちの生々しい息遣いとともに、当時の狂騒を感じさせるエピソードの数々は、令和を迎えた今、改めて振り返るに値するものだろう。当時から現在まで、カルチャーの変遷を一線で見つめ続けてきた中森明夫に、その時代精神を訊いた。(編集部)
80年代は、お祭りの前夜祭がずっと続いているような感じ

ーー『青い秋』はアイドル文化や出版文化を軸に、中森さんの少年時代である70年代から現在までの体験をベースに描かれた自伝的小説で、特に80年代の空気感が濃密に感じられたのが興味深かったです。本書を著したきっかけを教えてください。
中森:第1章の「文芸編集者」に出てくる編集者のモデルは高橋秀明くんという『小説すばる』の元編集長で、僕は彼が『週刊プレイボーイ』の編集をやっていた頃から20年来の友人だったんです。その高橋くんが6年前に突然亡くなってしまって、後任の編集長から彼についての短編を書いてほしいと依頼を受けたのが、この小説を書くことになったきっかけです。単発で高橋くんの短編を書いた後、それに連なる作品を書かないかという話になって、僕も良い歳だし、この機会に自分の人生を振り返ってみようと書き始めました。
ーー時系列に沿うのではなく、過去と現在の描写を交錯させながら物語を進めているのが印象的でした。こうした手法を採ったのはなぜでしょうか。
中森:『青い秋』というタイトルとも関わるんですけれど、“青春”はもともと中国の言葉で、青い春のあとには赤い夏の“朱夏”、白い秋の“白秋”、黒い冬の“玄冬”と続くんです。僕はもう60歳だから、白い秋から黒い冬に差し掛かっているわけだけど、この時期に青春をただ回想するだけの物語はありがちだし、それで終わりにはしたくありませんでした。というのも、僕は結婚もしていなければ持ち家もないから、昔の人みたいに“白秋”とはいえない感じで、まったく成長もしていないし、今でも過去のことを引きずっている。そういう風に歳を重ねながらも成熟できなかった現在を“青い秋”と呼んで、小説全体のテーマにしようと考えました。現在と過去を照らし合わせながら話を進めたのは、“青い秋”を際立たせるためです。
ーー主人公の中野がパーティーで酔いつぶれて、現代の“新人類”である富市くん(社会学者の古市憲寿がモデル)に「大人になってくださいよ」とたしなめられるシーンなどは、その手法がすごく活きていたと思います。
中森:あのシーンは誇張された創作です。しかし過去と現在をつなぐ象徴的なシーンになったと思います。僕らが新人類と呼ばれてマスコミで担ぎ上げられたのが1985年で、古市くんが生まれたのも1985年。もちろん彼は、僕たちなんかよりずっと賢いし、メディアとの付き合い方も達者なんだけれど、話をしていると本当の意味で新人類だと思わされます。僕らの時代のエピソードと彼のエピソードを往復したことで、ただの個人の懐かし話にならずに済みました。35年前に新人類と呼ばれて、オタクの名付け親ともいわれる僕は、ちょうど新天皇陛下と同い年でもあります。そういう時代の流れも感じてもらえると、面白いのかなと。
ーー80年代の雑誌文化の裏側を垣間見ることができるのも、興味深いポイントでした。実名では書かれていないものの、『朝日ジャーナル』の編集長だった頃の筑紫哲也さんの話など、貴重なエピソードが満載です。
中森:自分が直接見て体験してきたことも、小説なら表現できるかなと思って、いろいろなエピソードを盛り込みました。僕の勘違いとか、細かな間違いとか、誇張している部分もあるけれど、それよりも当時の雰囲気を大事にしています。あの頃の出版社は今のリアルサウンドの編集部みたいにお洒落じゃなくて、大学の部室みたいな雰囲気で、床に寝泊まりするような汚い奴もいっぱいいた。今考えると「よくやっていたな」と思うんだけれど、それが楽しくもあったんです。僕は方向音痴だけれど記憶力が良くて、その時に誰が何を言ったかとか、すごくよく覚えている。それがこの小説を書く上では随分と役に立ちました。もし筑紫さんがご在命だったら、「いや、俺こんなスーツは着てないよ」とか言いそうですけれど(笑)。秋元康も本当にこの小説に書いている通りの青年で、喫茶店でウォークマンを聴きながらノートに歌詞を書いていた姿を今も覚えています。
ーー本書では、80年代精神を“終わらない夢”と表現しています。その感覚を改めて教えてください。
中森:1984年に公開された押井守の『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』っていうすごく良い映画があってね、ちょうど僕が新人類と呼ばれた頃の作品なんです。文化祭の前夜を描いているんだけれど、時間がループしてしまって、文化祭当日を迎えられないという話で、まさに80年代の時代精神を表現していた。80年代は、お祭りの前夜祭がずっと続いているような感じで、新しくワクワクするような何かが起こりそうだという感覚はあるものの、本当のお祭りはついぞ訪れないまま、平成を迎えてしまったように思います。宮崎勤が1988年から1989年にかけて東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件を起こして、公判で「犯行は覚めない夢の中でやった」と言っていたけれど、あれには80年代に若者たちが遊んでいた“夢”のネガティブでグロテスクな部分を突きつけられた感じで、ショウが終わったという感覚がありました。
ーー1990年代はお祭りにはならなかったわけですね。
中森:その後に後夜祭だけがあったという感覚です。2005年頃に宮台真司さんの結婚式の時に、東浩紀さんと一緒に新宿のバーに飲みに行って、「とうとう宮台真司も結婚か」なんて話していたんですけれど、それがすごく後夜祭みたいな雰囲気だったんですね。結局、文化祭はやってこなかったということを、宮台真司さんの『制服少女たちの選択』(2006年)という文庫の解説にも書きました。1980年代にはバブル景気があったけれど、だからといって実際のお祭りになっていたわけではなかったんです。