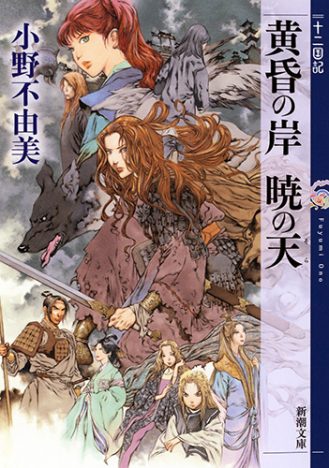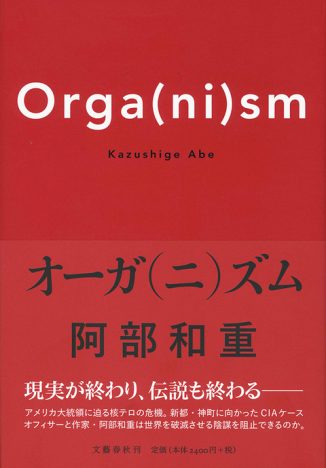村上龍文学の金字塔『コインロッカー・ベイビーズ』から40年……カルチャーに与えた影響を再考察

1980年に『コインロッカー・ベイビーズ』が刊行されてから約40年が経った。村上龍の三作目の長編にして代表作であり、日本の文学のみならず、80年代以降の文化全体に凄まじい影響を与えたこの傑作、そして、80年代の村上龍作品をここで改めて紹介したい。

村上龍は1976年、『限りなく透明に近いブルー』で群像新人賞を受賞。同年上半期の芥川賞を受賞し、小説家としてのデビューを飾った。東京・福生の在日米軍基地周辺で、ドラッグ、乱交、暴力に塗れながら日々を無為に過ごす若者たちを、冷徹にして客観的な筆致で描いた本作は、100万部以上の売り上げを記録。文壇を超え、社会的にも大きな話題となった。
翌1977年、詩的な表現で戦争を待ち望む人々の姿を綴った『海の向こうで戦争が始まる』を発表。そして1980年に上梓された初の長編小説『コインロッカー・ベイビーズ』で小説家としての評価を絶対的なものにした。
主人公はコインロッカーに遺棄され、生き延びた二人の少年“キク”と“ハシ”。横浜の孤児院で育てられた後、九州の離島に住む夫婦に引き取られるが、繊細な感受性を持ったハシは母親を探すために家出。棒高跳びの選手として活躍していたキクは、里親とともにハシを探しにいくーーというのが冒頭のストーリーだ。
九州の廃坑、東京の薬島(薬物汚染のため隔離され、売春やドラッグ売買の温床となっている)などを舞台に、歌手として成功するハシと世界を破壊したいと願うキク、東京でキクと出会う、鰐を飼っている美少女アネモネの運命が絡み合う本作は、村上龍の圧倒的な想像力が爆発した最初の傑作と言えるだろう。

この小説の大きなテーマになっているのが、システムに抗い、破壊しようとする意志。それを象徴するのが、「壊せ、殺せ、全てを破壊せよ、赤い汁を吐く硬い人形になるつもりか、破壊を続けろ、街を廃墟に戻せ。」というキクの独白、そして、小笠原の沖に存在する毒物“ダチュラ”だ。この破壊衝動は、『コインロッカー・ベイビーズ』のみならず、『愛と幻想のファシズム』(1987年)、『昭和歌謡大全集』(1994年)、『半島を出よ』(2005年)、『オールド・テロリスト』(2011年)などにも共通する、村上の一貫したテーマでもある。
描写と台詞と独白が一体となり、詩的にして過激な表現が連なる文章はきわめて濃密で、決して読みやすくはない。それにも関わらず『コインロッカー・ベイビーズ』は、80年代の若者に大きな刺激を与え、数多くの読者を獲得した。筆者が初めてこの小説を読んだのは1984年だが、音楽やカルチャーに興味を持っている人間にとっては、“絶対に読むべき作品”として認知されていたと思う。“小説を読む=教養を身につける”という図式ではなく、社会の在り方や常識を根本から問い直し、読者一人一人の意識や行動に直接的な影響を与えた本作を読むことは、先鋭的なロック・ミュージックを聴くことと似た行為だったと言っていい。簡単にいうと、『コインロッカー・ベイビーズ』を読むことは、きわめて“カッコいい”ことだったのだ。廃坑、薬島の描写、ハシのコンサートのシーン、キクが棒高跳びで有刺鉄線を超える場面などは、いま読み直しても驚くほど刺激的。読者の脳内で映像が喚起され、膨大な情報が一気に流れ込んでくるような感覚は、この小説でしか味わえない。
この小説のインパクトは広範囲に及び、数多くのクリエイターに影響を与えている。作家でいえば、金原ひとみ、又吉直樹などが、『コインロッカー・ベイビーズ』に影響を受けたことを公言。マンガ、映画、ロックバンドなどの分野にも、この小説にインスパイアされだと思われる作品が数多く存在する(たとえば岡崎京子の『pink』の主人公の造形には、明らかに“アネモネ”の影響が見て取れる)。また2016年、2018年には、A.B.C-Zの橋本良亮と河合郁人が主演の音楽劇『コインロッカー・ベイビーズ』が上演され、話題を集めた。
発表から40年経った現在も、そのインパクトはまったく変わっていない。むしろ、政治、経済、文化、環境などあらゆるところで既存のシステムが立ち行かなくなっている今、この小説の意義は見直されるべきだろう。