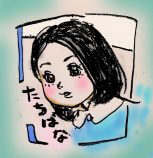『この本を盗む者は』に込められた、本好きの悔しさと怒り 前日譚で描かれた、たまきの想いとは?

本を貸したら、変な折り目をつけられたり、帯が破れたりして、腹を立てた経験は、本好きならば一度は経験しているんじゃないだろうか。知らないうちに又貸しされて、大事にしていた小説が行方知れずになり、買いなおす羽目になって「こんな思いをするくらいなら、二度と誰にも本は貸さない!」と心に決めた人も少なくないだろう。劇場版アニメーションが絶賛公開中の小説『この本を盗む者は』(深緑野分/角川文庫)の根っこにあるのは、そんな本好きの悔しさと怒りである。
本好きが集う読長町いちばんの有名人、御倉嘉市は全国に名を知られた本の蒐集家。地下二階から地上二階までの巨大な書庫「御倉館」は、本好きならば誰もが一度は足を踏み入れたいと願う夢の場所。だが、あるとき一度に二百冊もの本を盗まれたのをきっかけに、嘉市の娘・たまきは御倉館の開放を禁じてしまい、さらに、所蔵するほんのすべてに呪いをかけた。そして、たまき亡きあとに発動したその呪い――ブック・カースに、孫の深冬が立ち向かうことになるのが『この本を盗む者は』という物語なのだが、ここではその前日譚となる短編「本泥棒を呪う者は」(『空想の海』所収)をご紹介したい。

主人公は、たまきである。幼いころから本を愛するというより信仰していた彼女は、なぜ読書を中断してまで食事を摂り、眠り、便所へ行き、学校へ行かねばならないのかわからなかった。母親が泣きながらたまきの口をむりやこじあけごはんを流し込んだ、という描写を読んだとき、まっさきに浮かんだのは「わかる」だった。御倉の血筋を(御倉館の書物を)守るためだけに結婚して子どもをもうけた、その執念はさすがに「わかる」とは言いがたいけれど、「なぜ本よりも人を愛さねばならないのか理解できなかった」という彼女には、やっぱりちょっと、わかると思ってしまう。
本を読むのが、好きだった。物語の世界に没頭しているだけで、満たされた。本のなかには果てしない世界が広がっていたし、友達だって現実よりもたくさんつくれた。学ぶことだって山のようにある。決して、現実逃避なんかじゃない。ただ本を読むだけで幸せで、ほかになにもいらないと思っていた感覚を、記憶の底から一気に引っ張り出された気がした。
思えば本編でも、たまきに同調しそうになる瞬間はあった。たとえば〈物語を読み味わった体験は、個人の心の中だけに存在すればよく、意見の交換は愚にもつかぬ行為〉だとたまきは考えていた、とか。……いや、本の感想を語り合うのは好きだし、読書会などを通じて新たな読み方の発見できると、とても楽しい。それでも、自分にとって好きを超えて大事だと思える作品について、誰とも語り合いたいとは思えないことは、ある。不可侵の聖域として、誰にも穢されず、美しく胸に抱き続けていたいと。
おそらく、たまきにとっては、すべての本が、物語が、その対象だった。つまり彼女は、過激派同担拒否だったのだろう、と思うと急に親近感がわいた。自分が完璧だと思う存在を守るために、ほんのわずかでも欠けが生まれることを許さず、苛烈に妄執をふくらませていった彼女の想いそのものが間違っているわけではない。ただ、やり方を間違えた。本以外と心を通わせることを求めなかった彼女は、現実で他者とともに生きることを放棄してしまっていたのだろうと想像すると、切なくなった。
劇場版で描かれるたまきには「本泥棒を呪う者は」のエッセンスが加わっているのが、とてもよかった。確かに彼女は自分勝手に欲望を暴走させた人ではあるが、それだけではない、ということが伝わってくる演出になっている。
劇中、煉獄で怒りに燃え続けるたまきを見ながらふと思った。果たして本を読むという行為は閉じているのだろうか、開いているのだろうかと。好奇心の扉、という意味では確かに開いている。読長町に大勢の本好きが集まり、交流を重ねているように、思いがけない出会いを得ることもある。それでもやっぱり、読書というのは内向きな行為で、それを「好き」な人としかつながれない、狭いコミュニティであることも確かだ。だから、たまきの孫であり、御倉家の跡継ぎであるのに、本を読むことが大嫌いな深冬は孤独を抱えていた。
深冬はブック・カースが発動して、本の世界にさまがわりしてしまった読長町と、登場人物に変えられてしまった家族をふくむ町の人たちを救うために奮闘する。深冬がまきこまれる物語の世界は、劇場版では視覚的にもとても美しく、想像力ひとつで私たちはどこまでもいけるのだという可能性を示してくれているようにも見える。それでも、そこで感じたことのすべてを、誰かと共有することはできない。自分だけで抱え続けるしかない。
それでも、深冬がたまきのように自分ひとりの世界に閉じこもることがなかったのは、ましろという不思議な相棒とともに、誰かのために頑張りたいと思えたからではないだろうか。本が好きであろうと、嫌いであろうと、同じ町で暮らし、心を通わせる人たちのことを守りたい。彼らの存在する世界で生きていきたいと願うから、彼女は、ブック・カースを打ち破ることができたのではないかと思うのだ。
誰にも明け渡すことのできない孤独な感情。それでも、誰かとつながっていたいという想い。その二つがあって初めて、本は、呪いではなく祝福に変わるのかもしれない。