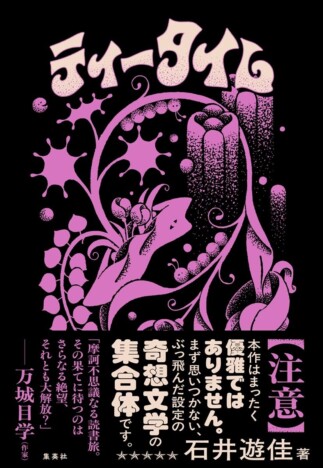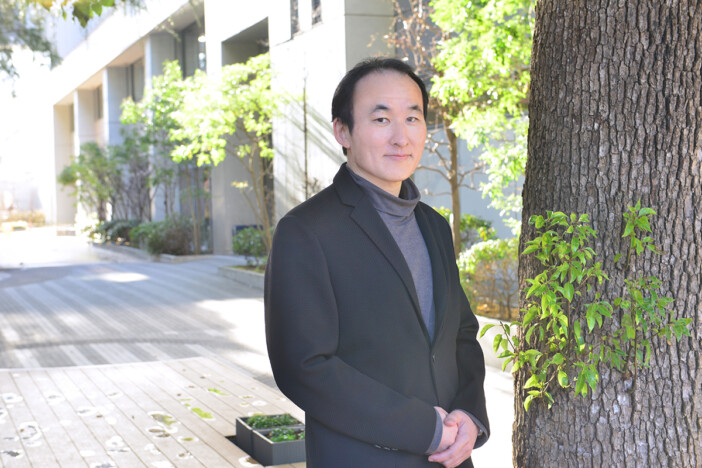杉江松恋の新鋭作家ハンティング ミステリー的な構造で読ませるホラー小説『うたかたの娘』

ホラーだけどミステリーとして読んだ。
横溝正史ミステリ&ホラー大賞は、横溝正史ミステリ大賞と日本ホラー小説大賞が合併してできた長篇新人賞だ。合併してからは七回目となる第四十五回は、綿原芹『うたかたの娘』(KADOKAWA)が受賞した。
この賞の美点は、ミステリーとホラーを単にくっつけただけではないところにある。ジャンルとして見た場合、二つは別物である。ミステリーは合理的精神に基づいて謎を解明し、ホラーは人間の手が及ぶところにはないものを描いて恐怖を招き寄せる。では二つの間に接点はないのか、と言えばそんなことはなく、もちろんミステリーであると同時にホラーでもある小説はいくらも存在する。ジャンルの交点はあるのだ。しかし横溝正史ミステリ&ホラー大賞においては、もう少し小説の本質に踏み込んだ選考が行われている気がする。作品をミステリーとして成立させている要の部品、同じく恐怖を生み出すホラーならではの要素、そうしたものが一作の中でどのような使われ方をしているか、ということが毎回の選考では問われているように思うのだ。作者が用いる技巧を選考委員は評価している。ジャンルよりも作品の中身を優先しているわけで、理想的な形だと思う。
『うたかたの娘』は四話から成る連作形式の物語だ。四話すべての共通項として、ある伝説が出てくる。第一話「あぶくの娘」は、福井県のある小さな港町が舞台で、高校生の男女を主人公とする青春小説の体裁をとっている。語り手の〈僕〉は高校入学直後にある揉め事を起こして停学処分を受けたことが尾を引き、学級では浮いた存在になっている。そんな彼に珍しく声をかけてくれるようになったのが水嶋藍子である。水嶋もまた、学校では浮いた存在だ。特に女子の間では人望がなく、のけ者にされているらしい。水嶋は地方の高校にいるのが信じられないほどの美貌の持ち主だが、そのことが人間関係にどう影響しているかは〈僕〉にはわからない。
高校二年次の十一月に、二人がゆっくり話をする機会が訪れた。そこで語られるのがくだんの伝説、薄紅の昔話である。
海辺の村に薄紅という女がいた。絶世の美女であり、男で恋に落ちない者はいなかった。それがために嫉妬を買い、村でいちばん醜い容貌の女が薄紅を殺し、死体を鍋にして食ってしまった。すると、女の顔が別人のように美しくなっていったのである。しかし、それも束の間、今度は体中が鱗で覆われていき、ついに下半身が鱗になってしまった。女は捕らわれ、不老不死の薬として時の権力者に献上されてしまったという。
この昔話の土台には八百比丘尼伝説が眠っている。人魚の肉を食べると不老不死になるというものだ。美しい娘は人魚なのであり、それを殺して食べると同じ美しい顔になる、という部分が本作の独自性である。
水嶋愛子が信じられないほど美しい娘である、という点が薄紅の伝説とつながっていることは容易に想像がつくはずだ。実際物語は、その点を軸に進んでいく。水嶋は幼少期に奇妙な体験をしていた。薄紅をめぐる人々のその後はどうなったのだろうか、という興味が読者にページをめくらせる。
現在の福井県である若狭国は八百比丘尼伝説の残る地であり、そうした意味では古来の伝承を現代に接続した怪異の小説として読むこともできる。作者はそうした古い要素を、最新の関心に接続する。第二話「にんぎょにんぎょう」は、職場でハラスメントを受けている〈わたし〉こと藤野が語り手だ。彼女はもともと経理部門にいたのだが、営業に異動になった。課長の飯田は藤野が人事面接で異動希望を申し出たのが気に入らなかったのか、事あるごとに辛く当たるようになってきた。その都度揶揄するのが彼女の容姿と、内向的で明朗さのない性格だ。藤野は生命の危機を感じるほどのストレスを覚え、飯田に対して殺意に似た思いを抱くようになる。その前に一人の女性が現われる、ということから物語は動いていく。
美醜があたかも人間の勝ちそのものであるかのように語られる、いわゆるルッキズムの物語だ。藤野が絡めとられている網の一つにルッキズムがあり、彼女はそれを憎む。しかし美醜で人を判断することが諸悪の根源である、というような単純な書き方をこの作者はしないのである。人物配置が冴えていて、単純な二項対立に陥ることから「にんぎょにんぎょう」は免れている。
「にんぎょにんぎょう」は小説全体では起承転結の承に当たる展開部で、後半の二話で使われる要素がここで初めて示される。たとえば〈わたし〉が謎の老婆から貰った奇妙な人形、たとえば彼女の職場に新しくやってきた、完璧に均整のとれた目鼻立ちを持つ派遣社員の女性、そういうものである。最初の「あぶくの娘」は人魚伝説の物語だったが、「にんぎょにんぎょう」は題名が暗示するように呪いの人形の話である。四話でそれぞれ用いられる物語類型が異なる。この賑やかさが『うたかたの娘』の第一の美点だ。
選考を読むと、委員の評価は第三話の「へしむれる」がもっとも高かったようである。ある水族館が舞台で、確かにあまり類例のない、気持ちの悪い出来事が描かれる。予備知識なく読んだほうが新鮮な驚きを味わえると思うので詳しくは書かない。第一話で示された薄紅伝説は変身譚に属するものだったが、これも同じ類型と言える話である。ただし描かれ方はまったく異なる。とにかく、見たことがないような変な話なのだ。
薄紅伝説の上に各話は組み立てられている。この構造は可視化されているのですべての読者が気づくことだが、実は共通項はそれだけではない。物語は複数の階層の上に立っている。その階層を支える重要な部品がいくつかあるのだが、それらが実は各話の中にも忍ばされているのだ。入ってはいるのだが、別の姿に見せかけられたり、細分化されて部品を組み合わせないと元の形に見えなかったりするので、各話を最後まで読まないと気づかないようになっている。たとえば「へしむれる」には「あぶくの娘」の登場人物が再び顔を出している。なぜその人物が再起用されたのかといえば、階層を支える部品の一つだからなのである。物語が大詰めに近づき、「へしむれる」という話の全容が明らかになる直前まで来ないと、その人物が担っているものは見えないように偽装されている。
とにかく構造のおもしろい小説だ。砕片化された要素を拾い集め、全体像はこうであろうか、と考えながら読んでいくことが求められる。これはミステリーにおける手がかりの収集と、それを元にした推理ではないか。小説をミステリーとして楽しむすべを知っている人ならば、『うたかたの娘』もまたそれとして読むことができるはずである。
作者の綿原はこれがデビュー作だが、本作応募の前年度に、別の作品で小説野性時代新人賞の最終候補にも残っている。両賞で選考委員を務めた辻村深月によれば、これはホラーなどの要素がまったくない青春小説だったそうだ。種類の違う物語の着想をいくつも持っている人なのだろう。どのような作品をこれから書いていくのか、まったく想像ができない。無限の可能性を持つ新人が現れた、と称賛したい。