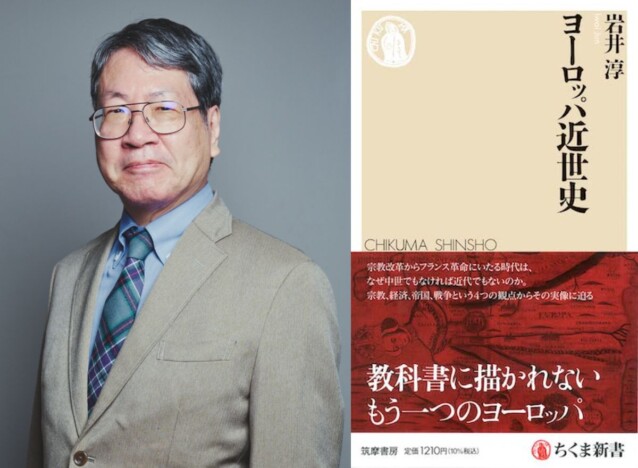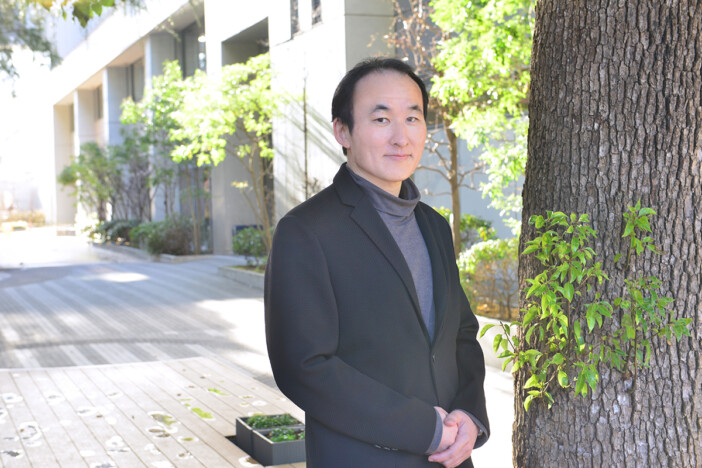トランプ大統領の支持基盤「福音派」は、なぜアメリカ国民に必要とされるのか? 話題の新書『福音派』を読む

ドナルド・トランプの重要な支持基盤とされる「福音派」。9月19日に刊行された加藤喜之『福音派―終末論に引き裂かれるアメリカ社会』(中公新書)はこの福音派の成り立ちと歴史を解説した入門書であり、そこから第二次トランプ政権下で混迷するアメリカ社会の実態も見えてくる。
そもそも福音派とは、どのような集団なのか? 本書では〈米国の福音派は、神の言葉としての聖書、個人的な回心体験、救いの条件としてのキリストへの信仰、そして布教を重視する、複数の教団、教会、個人からなる宗派の壁を超えた宗教集団であり、運動である〉と定義されている。彼らの特殊さを示す要素として分かりやすいのが、「ディスペンセーション主義」と呼ばれる終末論の信仰だ。
終わりの時代が始まると、キリスト教徒は天に引き上げられ、残された未信者は戦争や飢饉により苦しみの時を過ごす。そこにキリストが再臨し、「反キリスト」という悪魔的な支配者とのハルマゲドンが起こる。勝利したイエスは千年王国を築き、エルサレムに王座を据えることになる。ディスペンセーション主義では、このように聖書に記された予言を何かの比喩と捉えず、文字通りのことが現実に起きるものと受け取る。
その思想が広まった1920年代当時、イエスの再臨を信じるキリスト教原理主義者たちは、アメリカのエリート層に時代錯誤の存在と見なされて、教団や神学校の隅へと追いやられていた。そこで彼らは、新しいメディアで規制も少なかったラジオを通じて終末論を発信するなど独自の道を歩み始め、1942年に「全国福音派協会」を設立する。
その歴史を追っていく中で分かるのは、福音派は突然台頭してきた訳ではなく、長きに渡る積み重ねによって影響力を持つようになったということだ。1950年代の共産主義に対する恐れ、1960年代以降の人種統合や性的規範の変容、ドラッグ文化の拡大などにより社会は大きく変化していく。その頃から福音派では「古き良き伝統」(資本家贔屓や人種差別・家父長制を含む)が破壊されるという危機感のもと、さまざまな運動を展開していた。
優しい南部訛りと良く響くバリトンボイスで、反共産主義と終末論を結びつけて語る巧みな説教から、ソ連や中国に脅威を感じる人々をキリスト教に迎え入れた「アメリカの牧師」ことビリー・グラハム。1970年代に自ら出演したドキュメンタリー映画(監督は息子が担当)の上映を通じて、中絶容認の反対を訴えた宣教師フランシス・シェーファー。1979年にロビー団体「モラル・マジョリティ」を発足させて共和党と蜜月関係を築き、福音派を政治集団化させた伝道師ジェリー・ファルウェル。本書で紹介される福音派を表舞台へ押し上げた人々の半生は、思想家・活動家列伝としての読み応えもある。
当時の社会の空気を知る材料として、本書では日本でも知られているようなアメリカの文学作品や映画にも多く触れている。たとえば、福音派が政治の世界に進出してきた時の多くの米国民の戸惑いと恐怖を表現したといえる、マーガレット・アトウッドの小説『侍女の物語』(1985年)。福音派の聖職者たちがマネージメント理論を駆使する時代に教会の「顧客」となった、人とのつながりを求める郊外住民たちの悩みや失望に着目するサム・メンデス監督の『アメリカン・ビューティー』(1999年)など、宗教・政治以外の分野も横断する視野の広さは、専門外の読者にとっての取っ付き易さにも繋がっている。
近年の福音派は、人種差別問題の矮小化やイスラエル寄りの政策の支持など、利害関係にない存在への冷たさ・無関心さが目立つ。そこに批判的な目を向けつつ、内部で反発する人々の存在についても言及する本書の公平さは、福音派の意外な多様性を浮かび上がらせる。たとえば福音派は白人の保守層で構成された集団かというと、そうとは言い切れない。少数派ではあるが、社会政策において進歩的な考えを持つ左派も存在している。また現在、3人に1人は有色人種である。福音派全体を見るとトランプ支持は6割弱と、そこまで高くはない。全国福音派教会に入れず、1963年に「全国黒人福音派教会」を独自に組織した歴史を持つ黒人に至っては、支持率が9%に過ぎないという。
とはいえ福音派の白人の圧倒的多数がトランプを支持する状況は変わらず、リベラル派・非宗教者との分断は進んでいる。あくまでそこに至る過程を描くことを目的とした本書で、解決策が提示されるわけではない。だが、〈福音派の立場を戯画化するだけでは、現代社会が向き合うべき問題を覆い隠してしまう恐れもある〉と、福音派の存在する意義を検証する著者の偏見を排した姿勢は、アメリカはもちろん日本でも社会を変えていく上で必要なものとなるはずだ。