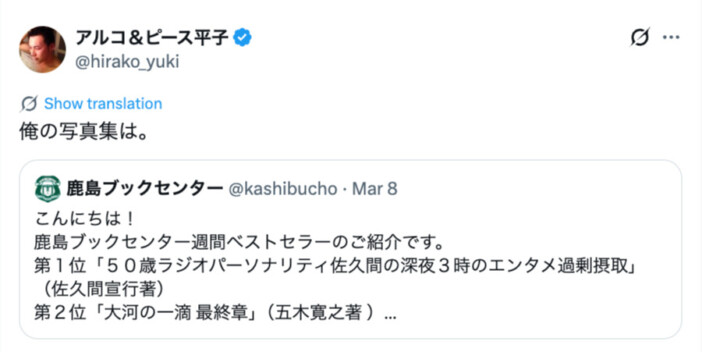第173回芥川賞候補4作品を徹底解説 例年に比べて1作少ないノミネート作、注目タイトルは?

2025年7月16日(水)に第173回芥川賞が発表される。今回候補作に選ばれているのは、以下の4作品(著者50音順)。
・グレゴリー・ケズナジャット「トラジェクトリー」(『文學界』6月号)
・駒田隼也「鳥の夢の場合」(『群像』6月号)
・向坂くじら「踊れ、愛より痛いほうへ」(『文藝』春季号)
・日比野コレコ「たえまない光の足し算」(『文學界』6月号)
駒田氏・日比野氏は初ノミネート、ケズナジャット氏・向坂氏は2度目のノミネートである。そして今回のノミネート作は例年に比べて、1作少ない4作となった。候補作が4作品というのは、戦前の芥川賞黎明期をのぞけば最少で、2017年以来2度目の事態となる。ちなみにその際は、1作(沼田真佑「影裏」)の単独受賞だったので、今回もその先例を踏まえ、受賞作は1作のみとなるのだろうか(通常なら2作受賞も珍しくないのだが、候補作が4作しかないとなると、その半数におよぶ2作が受賞作に選ばれるというのは、やはり少々バランスが悪いような気がしてしまう)。
以下、候補作を順番に紹介していく(受賞作予想もいちばん最後にする)。
グレゴリー・ケズナジャット「トラジェクトリー」(『文學界』6月号)
〈このようなところに住むことに彼は抵抗がなかった。だがここがいつまでも居場所であるとも思わない。間ということはつまり移動中である。どこかへと進む途中のところだ。方向が分からない。方向を示すものが見当たらない。〉
2007年に来日し、谷崎潤一郎の研究などをしていたというアメリカ出身の著者であるが、2021年に『鴨川ランナー』で第二回京都文学賞の最優秀賞となり、作家デビュー。第168回芥川賞にノミネートされた「開墾地」に続く、2度目の候補作入りである。
本作の主人公であるブランドンもまたアメリカからはるばる日本へと移り住み、しかし日々に倦みつつ英会話教師をしているらしい。そんなブランドンが勤めるブリッジ英会話学校名古屋東校には、授業への不満や嫌味が多く周囲から煙たがられている「カワムラさん」という常連客がいた。毎日、朝起きた際に15分、アポロ十一号の宇宙飛行士たちが残した記録をお経のように読み上げているのだという彼とともに、ブランドンはその記録を翻訳しつつ、読み進める授業を行なっている。
小説の舞台となる英会話教室は、まちがいなく「グローバル」な学びの場ではあるだろうが、どういうわけか、みなあまり楽しそうには見えない。なるほど、ある時代には「宇宙船」が、ある時代には「英語」が、「ここではないどこか」へと自らを連れ出してくれる希望のようなものであったのだろう。が、グローバリズムは行き詰まり、時代は変わった(端的に言えば、アメリカも日本も凋落した)。そんな現実の影は、本書のところどころに付箋のようにして貼り付いている。そこで主人公は、ふたたび英語の世界へと参入していくのではなく、「はざま」での「とりあえず」の暮らしを守る、という存在様式を選ぶ人間である。
タイトルの「トラジェクトリー」(trajectory)とは、ロケットなどの弾道や軌道、あるいは人の軌跡や歴程を表す英単語だという。生まれた時間も場所も、ゆえに価値観も異なる人々がそれぞれ描く軌跡の、奇跡的な交点が具現化されたような小説である(本当はどんな小説だって、そしてこの現実だってそうなのかもしれないけれど)。
駒田隼也「鳥の夢の場合」(『群像』6月号)
〈それから蓮見は、やはり自分は死んだのだと思った。蓮見は死んだ。/彼は次の日の朝、初瀬にそのことを話した。/「初瀬さん」彼女はそのとき目玉焼きをつくっていた。/「おれ、死んでもうた。やから殺してくれへん?」〉
第68回群像新人文学賞の当選作、つまりはデビュー作でいきなり芥川賞候補入り。
4人組のルームシェアで、ほかのルームメイト同士が結婚することになったため、シェアハウスに取り残されることになった男女・蓮見/初瀬。これからルームシェア解消まで、二人の新たな共同生活が始まる、かと思いきや、一転、蓮見はとつぜん死ぬ。が、それすら本作においては問題ではなく、彼らを悩ませるのはむしろ、死んだ、にもかかわらず、蓮見が幽霊としてこの世に残り続けていること、だった。ということで蓮見は、初瀬に自分を殺すように頼むのだが、初瀬からすれば、本当に蓮見が死んでいることを確信できないまま殺すのはどうにも躊躇われる。そこで初瀬が設定した決断までの猶予は、海外から帰国した友人からちょうどもらった50本の葉巻を蓮見が吸い切るまで、ということになった。
冒頭の「両方ある」というあからさまな宣言どおり、現実/非現実を確定させない語り口とそれに由来する独特な時間感覚がまず目にとまる。くわえてストーリーテリングも独特で、普通ならクライマックスに持っていきたくなるのかもしれない、さきの「殺すor殺さない」的な問題が、想像よりもざっと2段階ほど手前で一定の解決を迎えてしまう、という点に意表を突かれる。
幽霊となった知人との共同生活的な主題は、単純に私が芥川賞関連記事を書き始めて(=2020年度上半期)以降だけを考えても、石沢麻依『貝に続く場所にて』(2021年度上半期・受賞作)、向坂くじら『いなくなくならなくならないで』(2024年度上半期・候補作)と印象的な作品が続いており、それが現代的なテーマだといえばそうなのかもしれない(少なくとも『貝に続く場所にて』には、明確な必然があった)が、それでもやはりこうも続くといささか食傷気味ではある。先の時間感覚的な実験性についても、いわば保坂和志以降、あるいは、はっきりと柴崎友香以降的な雰囲気もあり、現代文学の申し子であるのは間違いないが、著者独自のシグニチャーがどのような点に認められるのか、次作以降の作品についてもぜひとも読みたいと思った。
向坂くじら「踊れ、愛より痛いほうへ」(『文藝』春季号)
〈「なんだと思ってますか。わたしを!」/「どういうこと? なんで……なんで怒ってるんですか?」/「わたしをなんだと思ってますか、わたしと、わたし以外の、わたしをふくめた、人たちを、なんだと思ってるんですか」〉
文筆活動を始め、さまざまな領域横断的な活躍で知られる著者が、昨年、第171回芥川賞候補に選ばれた『いなくなくならなくならないで』以来、1年ぶりの候補作入り。
バレエスクールに通う少女・アンノは、ある事件をきっかけにバレエを辞めた。時が経って数年後、アンノは高校時代の半ばから自宅の庭にテントを張り、そこで一人生活するようになっていた。それに相前後するようにして交際を始めた大学生・昭宏の祖母「あーちゃん」と知り合う。「あーちゃん」もまた、昭宏の両親と絶縁状態にあって一人で暮らしているという。ほどなくして昭宏とは別れることになったが、しかし、アンノはその後も「あーちゃん」のもとに通い続けていて……。
〈anno〉と書いて左から読めば「アンノ」だし、右から読めば「女」である。母親や「アケミ先生」、「モリちゃん」、心理士の女、そして「あーちゃん」。あるいは、生まれてこなかったアンノの妹。アンノは本作に登場するそれら「女」たちのいずれでもあり、かつそのいずれでもない存在である。アンノは「女」の鏡像であるし、ゆえにというべきか「アンノ」は「女」と衝突する。「女」は、アンノが繰り返す「割れる」行為によって生み出された片割れたちなのかもしれないし、いわゆる「女」になり損ねた存在が「アンノ」かもしれない。「女」はアンノの敵であり、味方である。さらにアンノの「アン」は、「un」の「アン」かもしれず……と書いていて混乱してくるが、この「こんがらがり性」こそが前作『いなくなくならなくならないで』から続く著者の魅力であり、本作においても女性同士(とくにアンノと「あーちゃん」)の愛憎入り混じった一筋縄ではいかない関係性というのが、作品の読みどころになっている。
日比野コレコ「たえまない光の足し算」(『文學界』6月号)
〈はじめはひまがあれば髪や爪を食べ、水を飲むように指をしゃぶっていた。髪を根もとから摘みとったとき、そのいっぽんいっぽんが避難者からの通信のように、ぷつっと途切れる音に、心から安心した。爪切りで切られたばかりの爪が喉に引っかかるのを好んだし、飲み込めないほど大きな氷を、食道がふくらみ通そうとするたびにどきどきした。〉
第59回文藝賞受賞作『ビューティフルからビューティフルへ』(2022年)によりデビューした著者が、最新作で芥川賞初ノミネート。
舞台となるのは、「かいぶつ」と呼ばれるギミック満載の不思議な時計台。ぐるぐると螺旋状に層をなして組まれた足場では「とび商」と呼ばれる少年少女たちが自らの能力を生かした個人商売を行なっており、「生活者たち」が物見遊山にやってくる。その横には、この世からの唯一の《痛くない出口》だという黒い池があり、時計台からそれを目掛けて飛び降りる者の姿がたびたび目撃されている。主人公は、拒食症がこじれて食べ物以外のあらゆるものを食べられるようになった「異食の道化師」・薗。拒食症になったきっかけは、美容外科の待合室で見つけた広告ポスターの「痩せたら何もかも変わる!」という広告だった。そこに新規でフリーハグを始めた「抱擁師」・ハグ、同じく今日からプロの「軟派師」となった弘愛(ひろめぐ)が加わり、三人の暗闇のなかでの交流が始まる。
とここまでで十分に理解されるとおり、本作は、ホストや風俗嬢的な存在を含む、いわゆる「トー横」的な現実空間のアレゴリーたろうとしている(「とび商」のなかには「映画(動画)」的メディアのルーツを思い出させる「ゾートロープ師」なる商売人もいるし、「かいぶつ」なる時計台からは、あのゴジラを連想してしまうはずだ)。幻想的な世界観とそれを成立させるディティールはきわめて精緻だが、そうした寓意を取り払ってみるなら、ストーリーとしてはかなりベタで、通俗的な話になりかねない、という点にやや疑問が残った。
*
ひとまず「受賞作なし」がないとするなら、わたしの受賞予想は、向坂くじらが本命です。