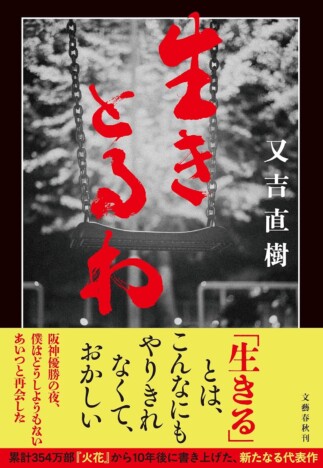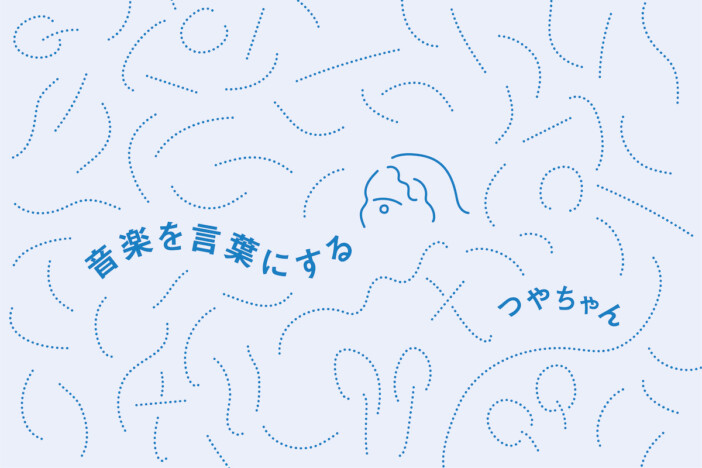【連載】嵯峨景子のライト文芸新刊レビュー
『ある魔女が死ぬまで』『ふつつかな悪女』などアニメ化作品も 見逃せないライト文芸の新刊タイトル

『少女小説を知るための100冊』や『少女小説とSF』などの著作で知られる書評家の嵯峨景子が、近作の中から今読むべき注目のライト文芸をピックアップしてご紹介する連載企画。今月はTVアニメも話題の魔女ものから豪華作家が集結したアンソロジーなど、5タイトルをセレクト。
坂『ある魔女が死ぬまで3 -はてしない物語の幕が上がる-』(電撃の新文芸)

コミカライズが好評連載中で、この春からTVアニメの放映も始まった人気シリーズの最新刊。
幼い頃に両親を失ったメグは、「永年の魔女」ファウストに拾われ、彼女のもとで魔女修業に励んでいた。ところが17歳の誕生日、メグは自分が「死の宣告」の呪いにかかっており余命が残り一年しかないことを告げられる。呪いへの唯一の対処方法は、誰かが流した嬉し涙を一年間で千粒集めること。不可能に近い難題に挑むメグは、さまざまな人たちを助ける中で嬉し涙を集め、魔女としての生き方や自分にしかできない役割について考えていくのだった。
第3巻スタートの時点でのメグの余命は残り半年、集めなければいけない涙は残り五百粒。焦るメグの前に姉弟子の「災厄の魔女」エルドラが現れ、これまでファウストが隠し続けてきたメグの故郷の滅亡と、エルドラとの因縁が明かされた。己のルーツを知る決意を固めたメグは、魔法協会のプロジェクトに参加し、魔法災害の被災国への支援と滅んだ故郷の調査に携わることに。本作の大きな魅力である師弟愛はこの巻でも健在で、広い世界に旅立つメグと、彼女を送り出すファウストとのやり取りはひときわ胸を打つ。優秀だが曲者揃いの新キャラたちと共に、危険なミッションの数々に立ち向かうメグの活躍と成長、そして絶望する人々に希望を与える姿は私たちの心にも勇気の明かりを灯すだろう。
中村颯希『ふつつかな悪女ではございますが10 ~雛宮蝶鼠とりかえ伝~』(一迅社)

シリーズ累計300万部を突破し、TVアニメ化決定も発表されるなど、ノリに乗っているシリーズの第10弾。
詠国の後宮内にある雛宮(すうぐう)には五つの名家から雛女(ひめ)たちが集められ、次期の妃を育成する教育が行われている。美しくて慈悲深いと評判の黄家の玲琳は「殿下の胡蝶」と称され、多くの人に慕われていた。一方、「雛宮のどぶネズミ」と呼ばれる朱家の慧月は、嫌われ者で周囲から疎まれている。玲琳を妬んだ慧月は道術を使い、二人の精神と身体を入れ替えた。このとりかえ劇をきっかけに、玲琳と慧月は思いがけないかたちで関わりはじめ、後宮で起こるさまざまな事件を通じて、やがては「分かり合える友」として深い友情を築いていくのである。
雛女たちの絆が魅力の後宮シスターフッド小説の最新作では、金家の雛女・清佳にスポットライトが当たる。西の隣国・シェルバ王国の第一王子ナディールが視察で金家領に立ち寄り、彼をもてなす宴に玲琳と慧月も協力することに。派手好きですべてに難癖をつける王子に手を焼く三人は、清佳を疎ましく思う叔父の思惑にも巻き込まれ……。当初の清佳は玲琳の本性を知らず一方的に崇拝しているが、ナディール王子への対応を通じてこれまで知らなかった彼女の一面にふれていく。三人が力を合わせてナディールに立ち向かう痛快な前半パートと、病弱な玲琳の切ない願いと慧月への思いが涙を誘う後半パートと盛りだくさんな一冊だ。
和泉あや『色を忘れた世界で、君と明日を描いて』(双葉文庫パステルNOVEL)

10代向けのライト文芸レーベルとして2025年3月に新創刊された「双葉文庫パステルNOVEL」第二弾の一冊。
高校2年生の森沢和奏は自分の意見を人に言うことができず、いつも周囲に合わせて過ごしている。3年前、和奏はよかれと思って友人にかけた言葉が原因で彼女と決裂し、学校での居場所を失った。この失敗で人を傷つけるのが怖くなり、自分の本音を他人にぶつけることができなくなってしまったのである。
同じマンションに住む幼馴染の佐野翔梧とは、かつては仲が良かったものの、物怖じせずに自分の思ったこと口にする佐野を苦手に感じるようになり、避けて過ごしてきた。だが佐野と隣の席になってしまい、気まずい雰囲気のまま過ごしているうちに、和奏は異変に気付く。5月31日の夕方になると前日の昼間に戻るループが起きていて、自分の他には佐野だけがこのリセットに気づいていた。一日をやり直すたびに世界から色が欠けていく中で、二人はループを抜け出すために自身の心と向き合うことになるが……。
ひとりぼっちになる恐怖や、自分らしさを失って生きるもどかしさなど、等身大のキャラクターたちが抱える迷いや後悔は誰もが共感できる普遍的な感情だ。傷ついた少年少女に寄り添いながら、それでも前向きに生きていこうと背中をそっと押してくれる優しさと、終盤のグルーヴ感が大きなカタルシスを残す、感動の青春小説である。