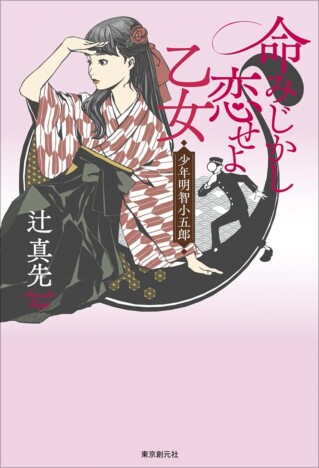『コミケへの聖歌』本や雑誌がない時代を描くポストアポカリプスSF 文明が滅びた後〈コミケ〉はどう象徴化されたのか

タイトルは大切。本当に大切。なぜならタイトルこそ本の第一印象であり、興味を惹かれて手に取るということがよくあるからだ。最近の本を例に挙げるなら、第十二回ハヤカワSFコンテスト大賞を受賞した、カスガの『コミケへの聖歌』である。同時受賞した、犬怪寅日子の『羊式型人間模擬機』も惹かれるタイトル(そして面白い作品である)だが、どうしてもタイトルに、毎回、喜んで行っている〈コミケ〉が入っている本書の方が、気になってならない。ということでさっそく読んでみたのだが、こちらの勝手な予想とまったく違った、ハードなポストアポカリプスSFだった。
あらためて書くが〈コミケ〉の正式名称は、コミックマーケットである。今や世界的に有名になった同人誌即売会のことだ。ただし本書の主人公たちがいう〈コミケ〉が、どれだけ実際の〈コミケ〉を意味しているか疑問が残る。なぜなら二十一世紀半ばに文明が滅び、文化が根絶されようとした三十年の暗黒期を経て、〈コミケ〉も断片的な情報しかないからだ。また、かつての東京は、赤い瘴気の立ち込める《廃京》と呼ばれ、どうなっているのか誰にも分からない。
主人公の〝ゆーにゃ〟こと悠凪は、その《廃京》から離れた、山奥の僻村·イリス沢集落地で暮らしている。父親は農夫で、母親は村で唯一の医者である。弟がいるが、ゆーにゃが母の跡を継いで医者になる予定だ。しかし一方で彼女は、《イリス漫画同好会》の〈部活〉にのめり込んでいた。村を指導するナグモ屋敷の娘の比那子。父親と一緒に村に居ついた、元ナガレ者のスズ。バラック長屋で家族と貧しい生活をしている茅。四人の少女は廃屋を改造した〈部室〉に集まり、見つかった旧文明時代の漫画を読んだり、ノートに漫画を描いたりと、部活を楽しんでいる。だが、比那子が旧文明時代の地図を発見し、〈コミケ〉に行こうと言い出した。とても現実的ではないと反対するゆーにゃだが、これを切っかけに、村の現実や自分の心を見つめ直すことになるのだった。
《イリス漫画同好会》の四人の少女が、ポストアポカリブス世界で〈部活〉をする。これだけ聞くと楽しそうな話だが、先にも触れたように内容はハードだ。イリス沢集落地は百人以上の住人がいる大きな村で、それなりに安定している。しかし生活水準は、現代と比べ物にならないほど衰退した。機械の部品などは旧文明時代の発掘品頼りで、先細りになることは分かっているが、有効な改善策はない。村を維持するための制約も多い。医者の家であるために村では比較的優遇されているゆーにゃも、さまざまな抑圧を感じていた。それはスズや茅も同様だ。また、ナグモ屋敷の次期当主であり、勝手気ままに生きているように見える比那子も、別の形で抑圧されている。
このような少女たちの生きる世界の息苦しさを、徐々に露わにしていく作者の手腕が優れている。本や雑誌も旧文明時代の発掘品しかなく、しかも読むために必要とされているわけではない。どこかに貼ったりなど、別の用途で使われている。おそらく村で小説を読んでいるのはゆーにゃだけ。《イリス漫画同好会》の他の三人も、小説には興味を示さない。三十年の暗黒時代で焚書などにより文化が弾圧され、厳しい日々の暮らしの中で漫画も小説も失われようとしているのだ。
だからこそ、四人の〈部活〉に、ほっとさせられる。発掘された漫画を読み、それについての話で盛り上がる。同人誌(肉筆回覧誌というべきか)を作る。物語の力、創作の力を随所で示し、世界の厳しさの中にある、小さな文化の聖域を表現しているのである。
しかし現実は非情だ。ゆーにゃは〈部活〉のことで、母親と揉める。比那子たち三人に対する、感情も複雑だ。特に、貧しい茅を下に見ていたことに気付く場面は痛々しい。そういえば本書の最初の方でゆーにゃは、〈部活〉のことを〝ごっこ遊び〟という。そして終盤で別の人が、よりやるせない意味で〝ごっこ遊び〟という言葉を使う。ここは感心し、悲しくなった。だが、こんな世界だからこそ〈コミケ〉が象徴となり、少女たちの希望へと繋がっていくのだろう。だからこの物語は、タイトルに偽りなしの、コミケへの聖歌なのである。