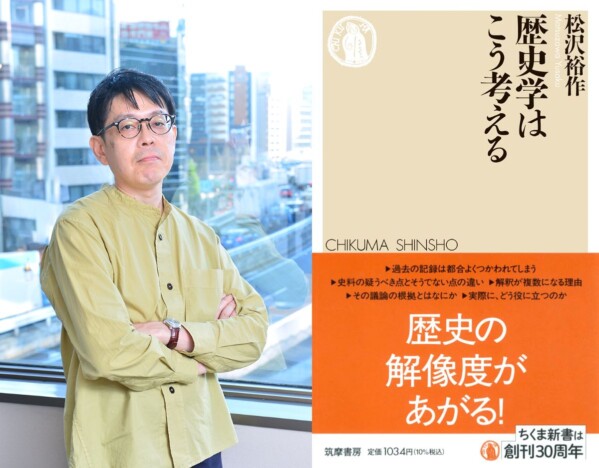桜庭一樹が考える、作者とファンと批評の理想的な関係性 「論理的な批判と感情的な悪口は異なるもの」


小説家・桜庭一樹が、小説を発表する上での心構えを綴った新書『読まれる覚悟』(ちくまプリマー新書)を刊行した。
小説は、人に読まれてはじめて完成する表現であるため、多くの人に読んでもらいたいと願うのは小説家の性だろう。一方で、小説が多くの人に読まれれば読まれるほど、誤読や批判が起こるのも避けられない。本書は、そんなときに書き手の心を守り、読む/読まれるという営みをいっそう豊かにしていくための「読まれ方入門」だ。
SNSの登場以降、多くの人々の意見が可視化される中、創作物をめぐる言説もまた目立つ状況となり、作家と批評家の間で論争が起こることもあれば、熱心なファンたちによって筋の通った批評までもが炎上することもある。桜庭自身も発表してきた作品を巡って、さまざまな問題と向き合ってきたという。その経験を踏まえて執筆された本書で、桜庭はどのような考えに達したのか。
結論ありきで組み立てられたものは、論とは呼べない

桜庭一樹(以下、桜庭):本当にそうですね。そして対話の中でも、小説ははっきりとは言い切らず、多様な解釈に開かれた状態で書かれることが多いですが、たとえばSNSだと、一つの意味で書いたのに、抽象的な表現だったために多様に誤解されて炎上してしまうケースもあると感じます。今回、新書というかたちで本を出すことになったとき、強く意識したのは「誤解されない文章にするにはどうしたらいいか」ということです。つまり、小説のような多様な解釈ができる文章ではなく、誰が読んでもなるべく一通りの解釈しかできないような、そして一部分を切り取られても誤解されづらい文章を書くことでした。
――それは、意識してできることなんですか。
桜庭:じつは最近、SNSに投稿するときは、書いた文章を、一度、英語か中国語にAI翻訳しているんです。で、それをもう一度、日本語に翻訳しなおす。そのとき、意味が通らない文章になっていたら、そこには多様な解釈をする余地があるということです。でも、どれだけ重訳しても意味が変わらない文章なら、誤解される危険性はほとんどないでしょう。そういう練習をSNSでしていたことが、新書の執筆にも生かされたかもしれません。
――なるほど!
桜庭:私自身、人と話したり、SNSを読んだりして、誤読した経験が何度もあるから、誤解してしまった側の悲しい気持ちもわかります。できるだけ読者のみなさんに安心して読んでいただきたかった、というのも、気をつけて書いた理由です。それに、そういう意識が芽生えたことで、小説を書くときも、以前より校正者の方から指摘されるより前に「この表現は差別につながるかもしれない」などと気づくことが増えました。多様な解釈に開かれているからといって、意図せず誰かを傷つけてしまうのも怖いですよね。
――誤解されて攻撃されるのもつらいですが、そのつもりがないのに誰かを傷つけてしまうのも怖いですよね。
桜庭:そうなんですよね。この本を書くときに、編集者さんが「暴力が生じることは避けられない」というお話をされたんです。どんな表現も、誰かを傷つける可能性がある。その覚悟をもつことは正しい責任なのだけど、でもやっぱり、できるだけそんな事態は避けたい。事故はどうしたって起きてしまうものだとしても、事後にどう対処するかも含めて、ある程度は暴力は避けることができるはずです。かつて文学の世界には、それよりむきだしの自分を投げ出そうとする姿勢が必要だと思われていたかもしれませんし、わたしもかつてはそうしようとしていました。でも書くというのはそもそも一方的な行為なのだから、最大限配慮する義務があったのだと思います。もちろんこの本にも、努力したつもりでも、批判されるべきところは残ってしまっているだろうと思いますが。
――最大限、配慮したうえで、書いたものの解釈を受け入れる。それこそが桜庭さんの「読まれる覚悟」なのだと、本書を通じて感じました。だからこそ読み手も、安易に解釈するのではなく、作品の奥にあるものをきちんと探らなければいけないな、と。
桜庭:ただ、一般の読者の方には「こう読むべき」とあまり言いすぎないほうがよいという気持ちもありました。私自身、仕事と関係なく本を読むときは、ゆるい気持ちでいることも多いし、気軽に楽しんでいただきたいから、「べき論」を押しつけすぎてしまうのはよくないなと。それとは別に、批評する立場の方には、書いている側が命を懸けているのと同じくらいの真摯さで向き合ってほしい、という気持ちがありました。
――傷つくのは、批判されることそれ自体ではなく、冷笑まじりのいじりや、論のない否定をされることだと、本書にありました。
桜庭:ある書評家さんが、批評する本にものすごくたくさんの付箋を貼っているのを見たことがあります。私の作品も、もしかしたら私がゲラを読む回数よりも多く、読み込んでくださっていたかもしれない。たとえ批判されたとしても、これほど読み込んだうえで論理的であれば、書き手も嬉しいと思いました。でも、本書にも書いたように、たとえばなんらかのテーマを掲げて書く文芸時評で、著者が言いたいことを補強するために作品の一部が切り貼りされて、異なる内容として紹介されてしまうこともあります。
――〈誰かの都合で一部分だけ切り取られ、異なる意味を付与され、グロテスクな一部になった自分の腕とか足とかを、無力感とともに眺めるしかない。わたしはこんなことをされるために書いたんじゃありません。〉という文章が、心に残っています。
桜庭:結論ありきで組み立てられたものは、論とは呼べないと私は思います。これまでも我慢して沈黙してきた作家さんがたくさんいたかもしれません。また、これも本書に書きましたが、新人作家さんや何らかのマイノリティ性を抱えた作家さんに対しては、批評家のほうが立場が強くなってしまうこともあります。