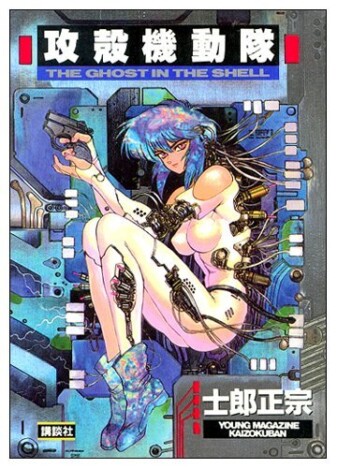人間はなぜ太るのか? 肥満当事者が『肥満の科学』で知ってしまった不都合な真実

ちょっとびっくりしたのは、糖尿病や内臓脂肪のような、現代では完全に病気として扱われている症状も、厳しい環境を耐えるための仕組みだったという点だ。本書によれば、エネルギー源が限られている中で脳に糖を優先して回し、鋭敏な状態を保って餌を得るために必要なメカニズムが糖尿病の原因だったのだ。また内臓に脂肪をつけるのも、リソースが限られた中でできるだけエネルギー源を体に溜め込むための工夫である。糖尿病も内臓脂肪の蓄積も、食料が限られている環境下では一時的な緊急措置でしかなく、すぐに解消されてしまうものだった。
脂肪や生活習慣病にはそういった意義があったことを説明しつつ、本書は「ではなぜ我々はエネルギー源を野放図に溜め込んでしまうのか」という疑問に切り込んでいく。実は野生動物には、食料を食べる量を調整して、常に適正な体重を保つ本能がある。しかし、冬眠をする動物や渡り鳥などは、長時間栄養補給ができない場合に備えて、大量に脂肪を溜め込むことがある。著者はこの行動の変化に、「大量に食料を摂取するモード」に体を切り替える"スイッチ"の存在を推測する。そして、常時その"スイッチ"が入りっぱなしになっているのが、現在痩せることができないでいる人間だというのである。
著者は、食料の大量摂取モードに動物の体を切り替える要因を、さまざまな研究結果をもとに「果糖」であると結論づけ、果糖の摂取によって引き起こされる生物学的プロセスを「サバイバル・スイッチ」と名付ける。サバイバル・スイッチはオンになると、ありとあらゆる方法を使って摂取した食物を脂肪に変換、体の中に溜め込み続けるのである。そして、現代の食糧事情は糖分の摂取を極端に簡単にしており、結果として現在肥満の人は「常にサバイバル・スイッチがオンになった状態」に置かれていると説く。
このサバイバル・スイッチの仕組みについての詳細は本書を読んでいただきたいのだが、これがまあ本当に、うんざりするほどよくできている。とにかく代謝のありよう自体を「エネルギー消費を少なくし、脂肪を溜め込む」という方向にシフトする仕組みなので、果糖によってスイッチが入っちゃったら何をやっても最終的に脂肪になるのである。恐ろしいことに人間の体は体内で果糖を作り出すことができるので、「じゃあ果糖を食べなければいいじゃん」という手すら通用しない。さらに塩分も体内での果糖生成を助けるので、「甘くなければいいのでは」というルートも塞がれているし、うまみの元となるグルタミン酸も肥満を引き起こす力があるという。どうしろっつ〜のよ……。
要するに、我々がおいしいと感じるものは、脂肪を溜め込んで自然界を生き延びるために必要なものばかりであり、そもそも「おいしい」と感じさせることでそれらを意識的に探すようプログラムされている、ということなのだ。う〜ん、やっぱりそうですか。そうなんじゃないかと思ってたんだよな……。終始こんな感じで、本書に書かれていることは概ね我々の想像の範囲を出ない。我々がおいしいと思うようなものはほぼ全部体に悪く、やっかいな病気を引き起こす原因になるという、あ〜やっぱりそうですか……という話が、これでもかとエビデンスを示しながら書かれている。
本書の後半は、「では、いかにしてサバイバル・スイッチをオンにせず、体重を増やさないか」という具体的な方法にページが割かれている。本書を手に取る人の大半が知りたいのはこの部分だと思うので、この原稿ではあえてそこについては具体的に触れないことにする。なんせ書いてあることが科学的に真っ当なので、提示されるダイエット方法もしごく真っ当、「それができないから困ってるんでしょうが!」と言いたくなるような方法ばっかりなのだが、現在のテクノロジーでは減量に近道が存在しないことがよくわかる内容となっている。
という、肥満で困っている人間としてはゲンナリするような内容の本なのだが、しかし「なぜ人間は太るのか」という点に関して生物学的・歴史的側面から非常に高い解像度で説明をしている本なのは間違いなし。不都合な真実を知り、おのれの体に向き合うきっかけとして、肥満の人にもそうでない人にもおすすめしたい一冊だ。