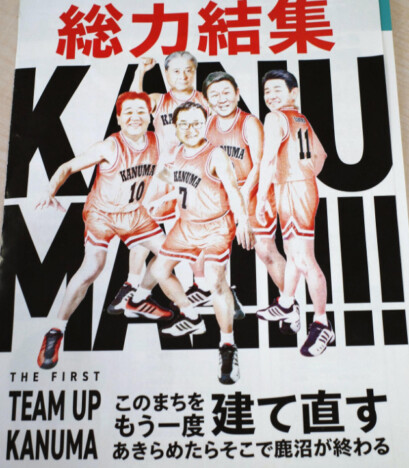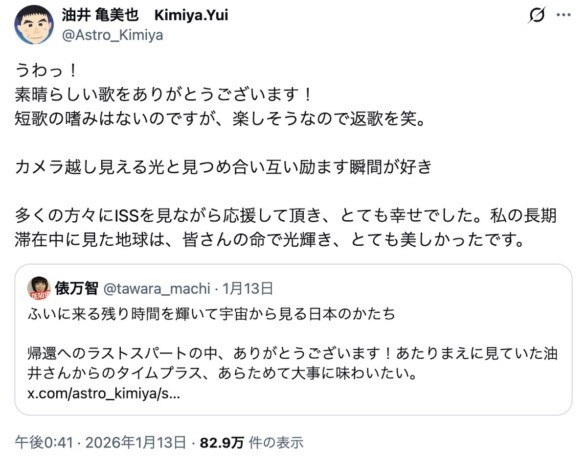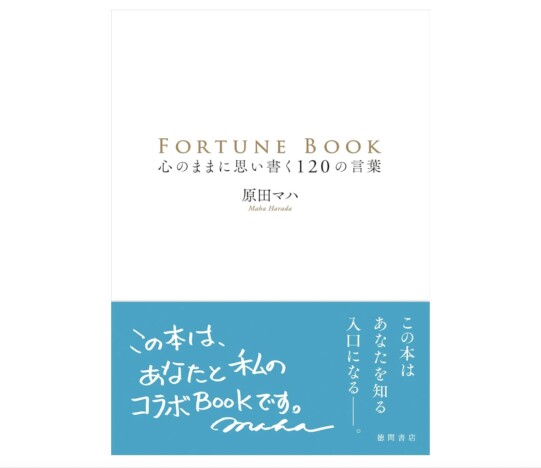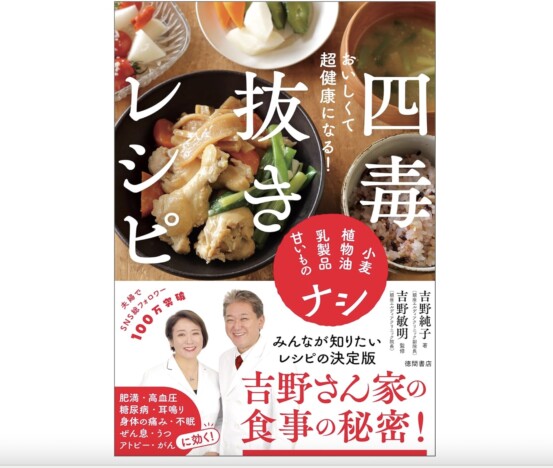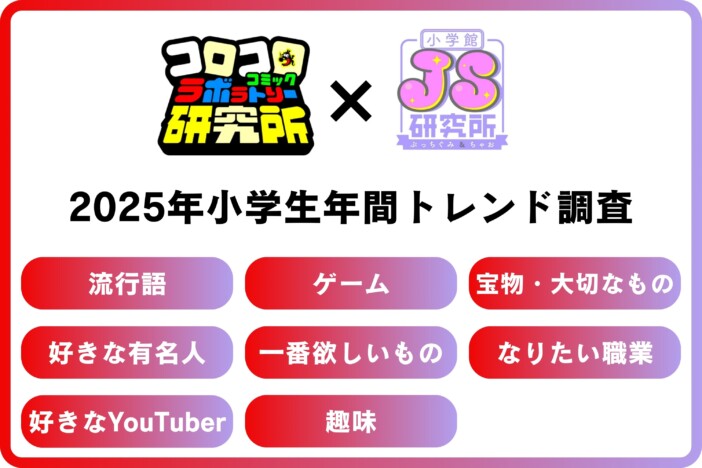東京都知事選挙ポスター、なぜ騒動に発展した? 弁護士に聞く、公職選挙法のシステム

6月20日に告示された東京都知事選挙。過去最多となる56人の立候補者が出たことも話題になっているこの選挙だが、もうひとつ話題になっているのが選挙ポスターをめぐる騒動だ。「NHKから国民を守る党」が大量に同一のポスターを貼ったり、ほぼ裸の女性を大写しにした河合悠祐候補のポスターが撤去されるなど、選挙ポスターをめぐってさまざまな問題が噴出している。
特に河合候補のポスターに関しては警視庁が介入。東京都迷惑防止条例違反にあたるとして口頭で警告が行われ、最終的に掲示板から剥がされるなど、異例の事態を招くことになったのである。
しかし、なぜこのような事態が発生しているのだろうか。小杉・吉田法律事務所の小杉俊介弁護士に、一連の事件に関するポイントを伺った。
──そもそも、ほとんど裸の女性の写真を印刷した選挙ポスターを貼るのは、なんらかの法律に抵触しているんでしょうか?
選挙に関する法律として公職選挙法というものがありまして、選挙に関する諸々の規制を実行する選挙管理委員会はこの法律に基づいて動きます。で、公職選挙法においてはそもそも選挙ポスターの内容に対してなんらかの規制を加えるという仕組みになっていません。
──それくらい、選挙ポスターでの表現の自由は手厚く守られているわけですね。
選挙管理委員会は公権力であり、ポスターの内容を規制することは検閲に該当しかねません。公職選挙法を理由にして選挙ポスターを剥がさせることはできないので、今回の警察による注意は東京都の迷惑防止条例を根拠としたものになっています。ただ、「迷惑防止条例を根拠にすればポスターの内容を規制することができる」というのは疑問が残ります。
問題のポスターは「猥褻で卑猥な掲示物である」ということで、警察も動かざるを得ない状況なのでしょうが、「表現の自由か、猥褻か」という問題は大変古典的なものです。たとえば、猥褻物頒布罪を規定しているのは刑法175条ですが、この法律は表現の自由を保障している憲法21条に反して違憲ではないのかという論点は昭和の昔からずっと存在しています。
現在の選挙は公職選挙法で厳しい規制をかけた上で、その範囲内で自由を認めるというシステムになっていますが、条例を根拠にして選挙運動に規制をかけるのは、いきなり踏み込みすぎかもしれません。
──しかし、なぜこのような状況になってしまったのでしょうか?
理由は1つではありませんが、あまり指摘されていないのは公職選挙法自体の問題です。「選挙運動というのは、こういうことをやってはいけませんよ」ということを色々と決めている法律なんですが、その規制が厳しすぎるという点は前々から広く指摘されていました。1925年に普通選挙が始まって以降ずっとこの状態が続いていて、あまりにも規制が多いことを揶揄する「べからず選挙」という言い回しもあります。
選挙活動を厳しく規制し、その例外として選挙ポスターの掲示や政見放送などを認めるというシステムとなっているため、それを逆手にとって利用されたという面はありそうです。例えば、自由な表現の許される選挙ポスターの掲示の規制がもっと緩やかで、常に目に入るような日常に溶け込んだものだったら、わざわざ馬鹿騒ぎをする人は減る可能性はあります。今回もN国党がポスターを掲示する枠を販売していましたが、高い値段をつけて売ることができるような、特殊なものになっている現状があります。非常に厳しい規制こそがプレミアを生み出してしまっているのかもしれません。