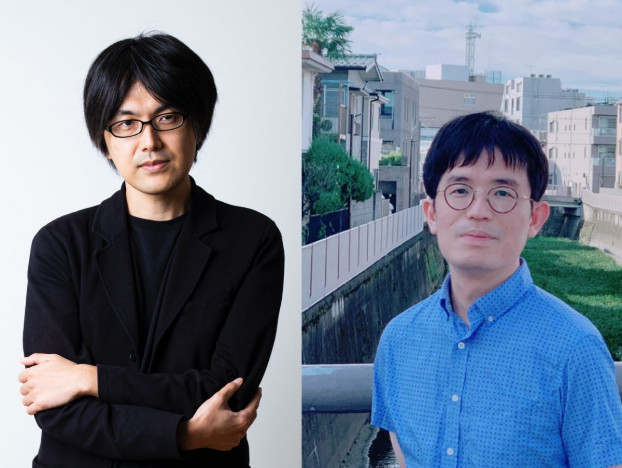福嶋亮大の大江健三郎 評:《弟》の複眼――大江健三郎の戦後性
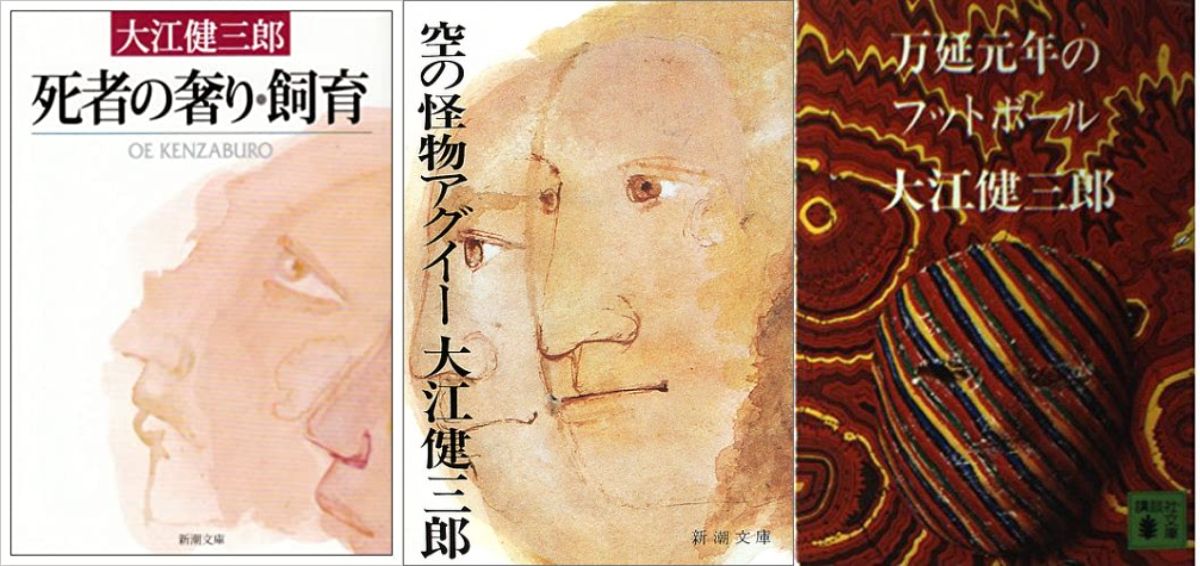
大江健三郎の小説を特徴づけるのは、何よりもその異様な文体である。ときに暗く低いうめき声をあげながら、うごめき、とぐろをまき、立ち止まり、また動き始めるミステリアスな生き物のような文体は、こちらを当惑させるほどに粘っこい。大江の小説は、ある事柄を高所から鮮明にするというよりは、その粘っこい運動のなかで、過去の記憶や未来のサインを手探りするようにして進む。それでいて、彼の文体はぼやけた不正確なものではなく、暗い欲動をしぶとく引っ張り続けるような独特の力をもつ。分析することではなく持続させること――それが大江の文体が志向するものである。
この異様なスタイルはどこから生まれたのだろうか。大江は《戦後》の時空間から出てきた作家であり、本人も戦後文学の系譜を強く意識していた。大江の小説は戦後日本のコンテクストに根ざすことによって、かえってその特殊なコンテクストを突き抜けた普遍性を得たと言えるだろう。一般には、大江に先行する文学者たち――大岡昇平、埴谷雄高、野間宏、椎名麟三、梅崎春生、武田泰淳、三島由紀夫ら――が「戦後文学者」の名称でくくられるけれども、彼らの知的活動はおおむねすでに戦前・戦中に始まっていた。それに対して、一九五七年にデビューした大江は石原慎太郎とともに、戦後を知的な出発点とする最初の作家である。その意味では、大江にこそ《戦後性》が濃縮されていると言ってよい。
では、大江はどういう態度で戦後に取り組んだのか。それを考えるには、今挙げた先行する戦後文学者たちと比較するのがよい。彼らの特徴は〈1〉国家と戦争というきわめてハードな問題に直面し〈2〉その強いショックへの反応として、死者の声をも包含するような形而上学的なヴィジョンを象りながら〈3〉その固有の体験をしばしば戦後の空虚さとのギャップにおいて位置づけたところにあった。個々の意志を吹き飛ばすような強烈な力にさらされた彼らは、そこに神に似た何ものかを重ねる。しかし、そのような「神的なもの」への感染者は、戦後日本においてはもはや居場所がない。ある強制力のもとで何かを見てしまった人間は、まさにそのことによって世界に所属できなくなるのだ。
戦争文学の金字塔である大岡昇平の『野火』(一九五二年)は、これらのテーマを巧みに織り込んでいる。フィリピンの戦場で六本の芋を渡されて、部隊から追放された田村を語り手としながら、大岡はその極限状態から厳密さへの志向を引き出している。「この六という数字には、恐るべき数学的な正確さがあった」。人間の世界から切り離された田村は、人肉を食べるか食べないかというボーダーをさまよい、やがて神的なヴィジョンに感染するが、死の一歩手前のところで奇蹟的に生還する。にもかかわらず、田村にとって、戦後社会はもはや帰還できる場所ではあり得なかった。彼は精神病院に収容されて「狂人」として生きるが、それは非存在(non-existence)の幽霊になることと同じである。
大岡は自らの戦争体験を精錬して、それまでの日本文学にはなかったような硬質の「思想」を作り出した。大岡を筆頭に、戦争によって日本の「外」に接触し、それを思想として伝達しようとした作家たちが、戦後文学のパイオニアになったのである。ただし、その思想は戦後を本質的に受け入れないし、戦後もまたその思想を受け入れない。つまり、戦後文学の根底には、戦後との深刻なギャップがある。
彼らがいわば兄だとしたら、大江は《弟》のポジションにあったと言えるだろう。『野火』の田村は戦後を拒んで狂人となったが、《弟》はそうではない。しかし、《弟》のポジションにも兄とは別種の困難がある。『野火』の五年後に出た大江の短編小説『他人の足』(一九五七年)の冒頭に、鍵となる文章がある。
僕らは、粘液質の厚い壁の中に、おとなしく暮らしていた。僕らの生活は、外部から完全に遮断されており、不思議な監禁状態にいたのに、決して僕らは、脱走を企てたり、外部の情報を聞きこむことに熱中したりしなかった。僕らには外部がなかったのだといっていい。壁の中で、充実して、陽気に暮らしていた。(以下、大江の小説の引用はすべて岩波文庫の『大江健三郎自選短篇』に拠る)
兄たちが強制的に「外部」に連行されたとすれば、弟である「僕ら」にはむしろ外部がない。しかも、それは自ら選択したものではない。それは大江が、この「粘液質の厚い壁の中」を「強制収容所」のメタファーで呼んでいることからもわかる。戦争は強制力だが、戦後にもまた別種の強制が働く――しかも、それは戦争と違ってマイルドな力であるだけに、より「あいまい」で捉えがたいものなのだ。大江の「あいまいな日本の私」というノーベル賞講演はよく知られるが「あいまいな日本」とは「戦後日本」のアレゴリー(寓意)にほかならない。
大岡にとっては、強烈な「外」の体験を明晰かつ厳密に捉えることが「思想」であった。逆に、大江にとっては、そのような明晰さや厳密さをむしばむ「不思議な監禁状態」こそが、戦後性の核にある。しかも、このような外部性を欠いた監禁というテーマは、その後村上春樹の小説、さらには押井守や庵野秀明のアニメでもたびたび反復されてきた。子どもっぽい陽気さにあふれた強制収容所――それは戦後日本の一つの肖像であり、大江はそれを最も早い段階で捉えた作家なのである。