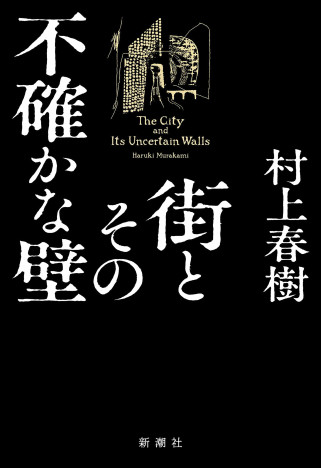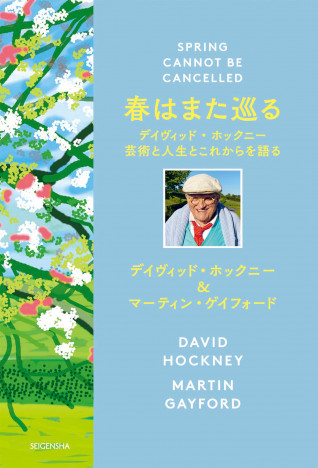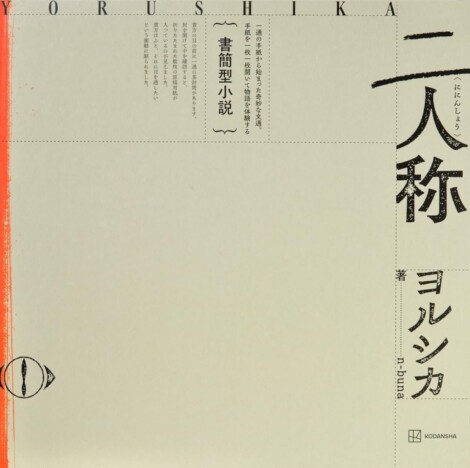【新連載】福嶋亮大「メディアが人間である」 第1回:21世紀の美学に向けて

3、「人間の拡張」の終局?
では、21世紀のメディア、特にインターネット上の動画の特性は何だろうか。それを考えるには、先ほどの濱口竜介の問いを裏返してみるのがよい――現代の動画の特性は、ひとを眠くしないことにあるのではないか、と。
現に、InstagramやTikTok、YouTubeなどに時々刻々とアップロードされる無数のショート動画は、人間の知覚や生理に過度な負荷をかけない。それらは知覚を脅かす機械的なショックよりも、むしろ人間的な関心や注意力を短時間集中させる仕掛けによって成り立っている。21世紀のメディアにアクセスする人間(ユーザー)は、眠気や退屈を強要されない。TikTokを見て寝てしまう人間は、ほぼいないだろう。そこに「映画の世紀」との根本的な差異がある。
映画が「持続する時間」のなかで、ときに自らのアブノーマルなエイリアン性を露呈させてきたのとは逆に、インターネット上のショート動画は一分ほどで次々と切り替わってゆく。21世紀の動画は映画的な持続性を排除しながら、自らの本体がinstantなtelegram(電報)であると自称する。巨大なスクリーンへの「投影」という大がかりな手順は省かれて、映像は電報的(即時的)な発信と共有のための素材に変えられる。同じくTikTokも「持続する時間」をこまぎれに分解し、チックタックという秒針のリズムのなかで共有と消費を促す。これらのアプリにおいては、視聴者の関心が途切れるまで、短い動画がループし続けるだろう。
この点で、Instagramのショート動画が「リール」と呼ばれるのは面白い。草創期の映画にはリールの制約があった。「シネマトグラフ」を発明したリュミエール兄弟の映画はだいたいどれも一分間ほどの長さであったが、それはフィルムのリールの大きさで決まっていた(※6)。その後の技術的な発展によって、映画の長さには事実上制約がなくなり、持続する時間が生じる。しかし、21世紀になると、このような映像の進化の方向はくるりと反転し、むしろ「リール」の有限性が復活したのである。
加えて、興味深いことに、リュミエール兄弟のシネマトグラフは現代のスマートフォンのようにモバイルであり、しかも記録・再生・編集の機能を兼ね備えていた。シネマトグラフという「魔法の旅行鞄」は、撮影、映写、ポジ焼き付けという三つの用途で使用可能であり、軽くて頑丈で持ち運びも自由であった(※7)。蓮實重彦は以前、映画がやすやすと国境を超えて複製・翻案されることを指して「映画には足が生えている」と巧みに評したが(※8)、軽くて機動性に富んだモバイルなシネマトグラフには、もともと足が生えていたのだ。
要するに、スマートフォンおよびそれに依存するInstagram等のアプリには、初期映画への先祖返りのような一面がある。このいささか奇妙な現象を目の当たりにするとき、私にはメディアによる「人間の拡張」というマクルーハン的なプログラムが、一つの長いサイクルを終えたように感じられる。そのことは実は、すでにマクルーハン自身が『メディアの理解』で予告していた。
機械の時代に、われわれはその身体を空間に拡張していた。現在、一世紀以上にわたる電気技術を経たあと、われわれはその中枢神経組織自体を地球規模で拡張してしまっていて、わが地球にかんする限り、空間も時間もなくなってしまった。急速に、われわれは人間拡張の最終相に近づく。それは人間意識の技術的シミュレーションであって、そうなると、認識という創造的なプロセスも集合的、集団的に人間社会全体に拡張される。(※9)
「機械の時代」から「電気の時代」への移行を経て、身体の拡張という仕事が飽和した後は、ただ「人間意識の技術的シミュレーション」だけが課題となる――これは現代のAI研究の登場を正確に言い当てている。そして、マクルーハンにとって、それは人間の拡張というメディアのプログラムそのものが終局を迎えたことを示唆していた。私はこの指摘を、今こそ真剣に受け取るべきだと思う。
※6 ロイ・アーメス『映画と現実』(瓜生忠夫他訳、法政大学出版局、1985年)15頁。
※7 ジョルジュ・サドゥール『世界映画全史1』(村山匡一郎他訳、国書刊行会、1992年)289頁。
※8 蓮實重彦『映画への不実なる誘い』(青土社、2020年)。
※9 マクルーハン前掲書、3頁。
4、メディアが人間である
繰り返せば、あらゆる映像はヒトもモノも等価に扱う「機械的な無関心」を潜ませている。しかし、現代のインターネットのアプリはそれをすばやく人間的関心によって補正する。20世紀の映画が非人間的な機械性をもつとしたら、21世紀のInstagramはそれを再人間化したと言えるだろう。映画の「持続する時間」は、(いわばリドリー・スコット監督の『エイリアン』の宇宙船のように)「他なるもの」の母胎になり得る。逆に、映画のエイリアンを孵化させないようにするには、持続を瞬間に置き換えればよい。
ただ、そのとき映像は他者というよりは人間の鏡に近づく。そして、人間が人間を拡張することはできない。マクルーハンは『メディアの理解』において≪メディアがメッセージである≫と記した。それはメディアが「人間の拡張」の舞台になった20世紀にふさわしい、すばらしい標語である。では、人間の拡張のサイクルが閉じたかに思える21世紀にふさわしい標語は何か? 私はこう答えよう――≪メディアが人間である≫と。
今や人間は形式となった。メディアが人間を拡張するのではなく、人間がメディアの拡張を制限する。メディアの法則はマクルーハン的な「人間の拡張」ではなく、その逆の「人間への転回」に置き換えられたように思える。もとより、それは人間がメディアの支配者になったことを意味しない。むしろ人間はより強くメディアに管理されコントロールされているのだが、その様式が「映画の世紀」からは大きく変わったのである。20世紀の人間がスクリーンと椅子に拘束されているとしたら、21世紀の人間はスマホとベッドに拘束されている。強制力がなくなったわけではない。ただ、強制力の場所が変わったのである。
このような状況をどう考えればよいだろうか。私はマクルーハンの思想を足がかりとしつつ、さらにその先に、つまりポスト・マクルーハンのメディア論に向けて一歩を踏み出したい。それは、21世紀のメディア環境を外部から一方的に裁断するのではなく、むしろ内部から観察し再考するためのルートを整備することと等しい。本連載はその企図に差し向けられた小さな試論である。