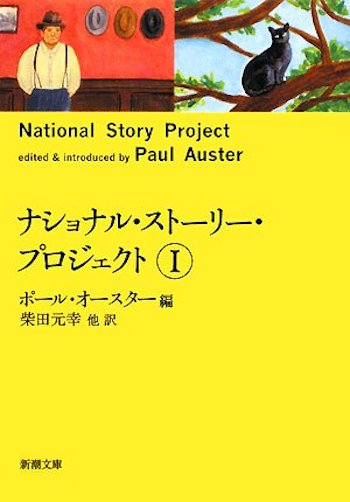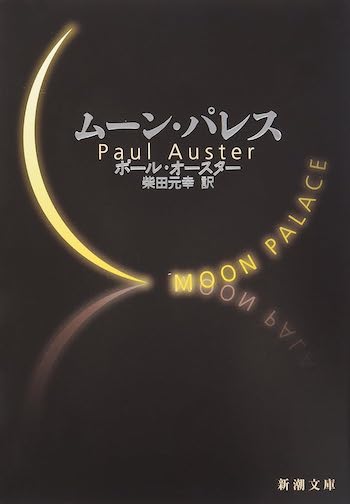去る4月30日、アメリカの人気作家ポール・オースターが77歳で亡くなった。アメリカだけではなく、世界中の言語に訳され広く愛される小説家であり、訃報には多くのファンが驚きを隠せなかった。日本でもたいへんな人気で、翻訳小説に親しむきっかけとなる作家として大きな役割を果たしたのではないだろうか。ニューヨークを舞台にした作品がよく知られ、日本人にとってもなじみやすいモチーフが多い。また文庫化されていて入手しやすく、翻訳を手がけた柴田元幸氏の現代的な訳文が読みやすいなど、読者がアクセスしやすい作家だった。海外文学という、やや敷居の高いカルチャーへの入り口として、人びとに支持される条件も揃っていたように思う。長年に渡って精力的に作品を発表し続け、多くの読者を獲得したオースターを追悼しつつ、彼の魅力についてあらためて考えてみたいと思う。
ポール・オースターの魅力は、「物語の力を信じる」という点にあるのではないか。彼の著作を読んできて、そのように感じている。私は、彼が『トゥルー・ストーリーズ』(新潮文庫)で書いているような、過去の貧乏生活にまつわるエッセイが大好きなのだけれど、ほとんど「オースターのすべらない話」とでも呼びたくなるような卓越したユーモアを読んでいると、そこには自分自身の過去を物語として語り直すことの豊かな効能が感じられるのだ。実際のところ、貧乏生活は苦しかったはずである。「明けても暮れても金が欠乏し、そのことが私をぎりぎり締めつけ、ほとんど窒息させ、魂にまで毒を及ぼし、果てることのないパニック状態に私を閉じ込めたのである」と彼は書いている。それでも、彼が貧乏生活を語るとき、苦しい経験はとても笑えるストーリーに変換されるし、なんなら楽しかった記憶のようにすら感じられるのだ。それはまぎれもなく「物語の力」であり「語り直すことの効能」だと私は思う。物語には、過去に起こったできごとの意味を変化させるような力がある。
小説家だけではなく、ごく普通の生活を送る私たちもまた、自分の人生を振り返ってとらえ直すとき、なんらかの物語に変換しているところがある。無意識のうちに、そうしているのだ。たとえば「過去には苦しいできごとがあったが、それは結果的に自分を強くし、人生をプラスに変えたのだ」というように、みずからの人生を物語に変換する作業は確実に存在するし、そうしなければうまく生きていけない。オースターは「人がみずからの人生を、物語として語り直す」過程に注目している。彼が『ナショナル・ストーリー・プロジェクト I・II』(新潮文庫)で試みたのは、市井の人びとから実体験を募集し、物語として語ってもらうことであった。物語にするには、無数の要素からいくつかのモチーフを選択しなければならないし、それをつなぎあわせた上で、なんらかの意味づけや結末を作らなくてはならない。オースターは「物語を語ってください」と人びとに呼びかけたのだ。あらゆる人びとは、なんらかの物語を自分の内側に持たなくてはならない。
生きていくためには、より良質で、生きる力を生み出すような物語が必要である。そして、よい物語を生み出すのは意外に難しい。オースターの小説を読んでいると、自分の人生をこんな風に豊かにとらえることができたら、生きるのがもっと有意義に感じられるだろうとうらやましく思うのである。オースターの作品が、登場人物の人生を語るときの視点が好きだ。たとえば彼は『ムーン・パレス』(新潮文庫)の冒頭で「キティと出会ったのはほんの偶然からだったが、僕はやがてその偶然を一種の中継地点と考えるようになった。それを契機に、他人の心を通して自分を救う道が開けたのだ、と」と書いている。とてもいい視点ではないだろうか。ここで述べている「偶然を一種の中継地点として考える」ことが、自分の人生を物語に変換するオースターの方法で、私はそのようなものの見方にとても惹かれるのだ。そこには「語り直すことの効能」がたしかにある。