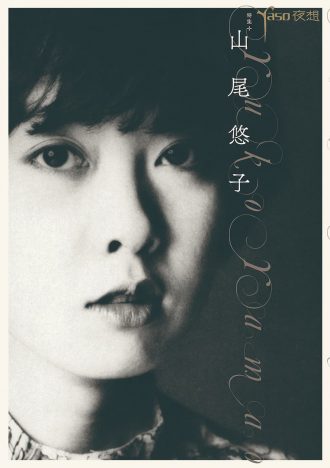【第44回日本SF大賞】人はなぜ人なのかーー長谷敏司『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』が問う人間性の根源

1年(2022年9月1日~2023年8月31日)の間に発表されたSF作品から選ぶ第44回日本SF大賞(日本SF作家クラブ主催)が2月23日に決定。長谷敏司『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』(早川書房)が受賞した。長谷は2015年に作品集『My Humanity』(ハヤカワ文庫JA)で第35回日本SF大賞を受賞しており今回が2度目。『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』は第54回星雲賞の日本長編部門も受賞しており、SF界の2つある大きな賞を制覇した格好だ。
参考:<a href="https://realsound.jp/book/2022/12/post-1195698.html">「2050年に30歳以下で年収200万円以下は普通にありえる」 近未来SF『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』のリアリティライン</a>
人はなぜ人なのか。『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』は、そのような問いかけに対する答えを、ふたつの方向から探ろうとしたSF作品だ。ひとつが身体。ダンサーの護堂恒明は、コンテンポラリーダンスの新星として期待されていたが、バイクの事故で右足の膝から下を失い、ダンスをあきらめかける。
そこに知人から、AIを搭載したロボット義足を着けて踊ってみないかといった誘いが来る。恒明のダンスを記憶して再現することも可能なロボット義足なら、前のように踊れるかもしれない。そんな期待を抱きはじめた恒明に、コンテンポラリーダンスの第一人者として活躍していた父親の護堂森が、強烈にダメ出しをする。
「気持ち悪い動きだな」と、恒明の義足を着けてのダンスを見て森が放った言葉は、ハンディキャップを義手や義足で補いながら生活している人への侮辱に聞こえてしまうかもしれない。もっとも、『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』の中で語られるのは、まったく逆のことだ。
自分の感情を、肉体の隅々にまで伝え表現するのがダンサーだとしたら、義足を着けていたならもその義足を含めた身体全体で表現しなければならない。ロボットの義足がAIによって恒明のダンスを学習し、義足を着けていなかった時と同じようなダンスを再現したところで、筋肉と骨格で出来ていた生身の足と義足とでは、齟齬が生じてしまう。
恒明は義足にもしっかりと踊らせるような新しいダンスの探求を始める。さらに、ロボットといっしょに踊ることを目指す中で、人間のような主体性を持たないロボットとどのようにコミュニケーションをとりながら、コンテンポラリーダンスとして観て美しいものにしていくかといった模索をしていく。
人間と共生するロボットの開発は可能かを思索する展開は、過去に数多くのSF作品でも描かれてきたものだ。長谷自身も、人間以上の存在となった少女型のAIと人間の少年との関係を描く『BEATLESS』(KADOKAWA)で挑戦し、第34回日本SF大賞の候補作に挙げられた。『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』はそうした長谷のライフワーク的探求の延長線上にある作品だ。
ここでは、テクノロジーの可能性に留まらず、ダンスという行為を通して、身体における人間性(ヒューマニティ)とは何かを考えさせようとしている。そしてもうひとつ、『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』は、精神というものが人間性というものに働いている意味についても問いかけてくる。
ダンサーとしての復帰を目指して練習と仕事に励む恒明だったが、そこで父親の森が交通事故を起こし、同乗していた母親を死なせ、森自身にも認知症の症状が出始める。直前までしていたことを覚えていられない症状では、ダンサーとして構成に沿って踊ることは難しい。演出家としての仕事もできない。
年金と介護保険だけしか収入がない老父を、息子が働きながら介護する大変さが描かれたストーリーは、同じような課題に直面している多くの人たちの関心を誘う。加えて森の場合は、ダンサーとして積み重ねてきた経験や得てきた栄誉を、恒明のような肉体の欠損によって失うのではなく、記憶の衰退という義手や義足では補えない状況によって失っていく不安に苛まれることになる。
そんな森と最初は対立していた恒明だったが、瞬間の衝動しかなくなってしまっても踊ろうとする森の中に、残されていた人間性を見る展開が、衰えつつある心身を抱えた人を前向きな気持ちにさせ、介護に悩む家族にも相手を理解する大切さを伝える。
これからますますAIは発展し、膨大な学習データを元にして人間と見間違えるような情報を吐き出すようになっていくだろう。小説では、第170回芥川賞を受賞した九段理江『東京都同情塔』に生成AIが使われていたという話が評判になった。イラストや絵画でも、AIが生成したものを人間の手によるものと見分けることが難しくなってきている。過程がどうであれ、完成したものが良ければそれで良いのではといった意見が説得力を持ち始めている。
恒明がロボット義足を着けて挑み、体験を伝えることで義足を成長させ、その延長でロボットたちとステージで踊る段階までたどり着いたダンスの世界も、いずれロボットだけで観客を魅了するものを作り上げるかもしれない。そうなった時に人間性とはいったいどこに宿るのか。そもそも人間性とは必要なものなのか。浮かぶ疑問に対し、肉体というものの実在であり、思考という機能が答えをくれる展開に触れさせて、自分という存在がどう思い、どう動くかが大切なのだということに改めて気付かせる。そんな作品だ。