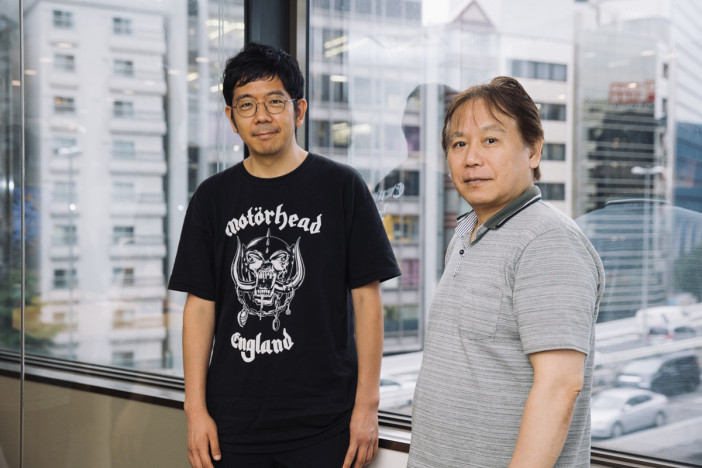新鋭ミステリ作家が仕掛ける究極の知的スリル 結城真一郎『#真相をお話しします』レビュー

ミステリというジャンルにはさまざまな楽しみ方があるけれども、その中でも大きなものと言えるのが「騙すか、騙されるか」のスリルを味わうことではないだろうか。作家側は斬新かつフェアなやり方で読者を騙そうとあの手この手を考え抜き、読者側はそんな作家の目論見を見抜こうと注意深く読み進める。しかし、実生活において騙されることを喜ぶ人間があまりいないのに対し、ミステリの場合、作家側のたくらみが優れていてまんまと騙された時こそ読者が喜ぶというのがこのゲームの特色である。
そんな知的スリルを期待する読者に強くお薦めしたいのが、結城真一郎の新刊『#真相をお話しします』(新潮社)である。
著者は1991年生まれ。2018年に『名もなき星の哀歌』(新潮文庫)で第五回新潮ミステリー大賞を受賞してデビューしている。2021年には、「#拡散希望」で第七十四回日本推理作家協会賞(短編部門)を受賞。平成生まれの作家では(長編および連作短編集部門で同時受賞の坂上泉とともに)初の日本推理作家協会賞受賞者となった。『#真相をお話しします』は、その「#拡散希望」を含む著者初の短篇集である。
ミステリの専門用語に「ホワットダニット」というものがある。これは、犯人当てが主眼の「フーダニット」から派生した言葉で、作中でそもそも何が起こっているのかわからないので、それを推理するのが主眼となっているミステリを指す。本書の五篇の収録作は、ほぼこの「ホワットダニット」をメインとしている。家庭教師の営業のためある家庭を訪れた大学生が、噛み合わない会話に当惑する「惨者面談」。マッチングアプリでナンパした男が思わぬ事態に遭遇する「ヤリモク」。妻と娘とともに暮らす男のもとに、かつて精子提供した女性が産んだ「我が子」からの連絡が来る「パンドラ」。学生時代の腐れ縁たちのリモート飲み会が剣呑な状態へと突入してゆく「三角奸計」——いずれも、読者は何が進行しているかわからない状態で、主人公たちが巻き込まれた事態を固唾をのんで見守るしかないのだ。
「#拡散希望」のように、比較的オーソドックスなフーダニットとアリバイ崩しを扱った作品もある。とはいえ、この作品でも、長崎市から西の沖合八十キロに位置する小さな島で、殺人事件が起きてから何故か住民たちが、島にたった四人しかいない子供によそよそしい態度をとるようになった……というホワットダニットがメインとなっている。こういう辺鄙な孤島は本格ミステリではよく舞台として選ばれるけれども、この作品のような奇天烈な使われ方の例は滅多にないだろう。
他にも五篇の収録作に共通しているのは、読者の予想の裏をかいてやろう、という意欲である。すれっからしのミステリマニアなら、「この展開ならきっとこういうどんでん返しだろう」と先読みをしようとするに違いない。だが、著者のその先読みを更に先回りして、もう一段裏を用意しているのである(特に第三話「パンドラ」以降の三篇にそれが顕著だ)。これはもう、知力の限界に挑んだ著者対読者の究極の頭脳戦と言っていいだろう。そこから醸し出されるブラックな雰囲気にも、病みつきになりそうな独特の味わいがある。
また、「三角奸計」におけるリモート飲み会など、現代ならではの世相と人間模様の絡ませ方も冴えている。本格ミステリ大賞にノミネートされた長篇『救国ゲーム』(新潮社)において、下手に扱えば水と油になりかねない政治的テーマと鮎川哲也ばりの精緻なアリバイ崩しとを巧みに組み合わせた著者だけのことはある。
こう紹介すると、マニア向けの短篇集なのではと誤解されるかも知れない。だが、本書はむしろ、騙しのテクニックの教科書的作品であるという意味で、ミステリをよく知らないという読者にこそ向いている一冊でもあるのだ。
本書を読んでいて私が想起したのは、「どんでん返しの魔術師」の異名を取るアメリカの作家、ジェフリー・ディーヴァーだった。四肢麻痺となった科学捜査の天才リンカーン・ライムが活躍するシリーズなどで人気が高いディーヴァーは、稀代の短篇ミステリの名人でもあり、特に『クリスマス・プレゼント』(文春文庫)は不朽のマスターピースとしての評価を確立しているけれども、本書のどんでん返しの切れ味からは、ディーヴァーの作風に極めて近いものを感じるのである。もし本書を英訳したら、アメリカのミステリファンはどのように受け止めるのだろうか。