武田砂鉄×横田増生が語る、ナンシー関という才能「みんなテレビで同じものを見ているんだけど、誰もこうは書けない」
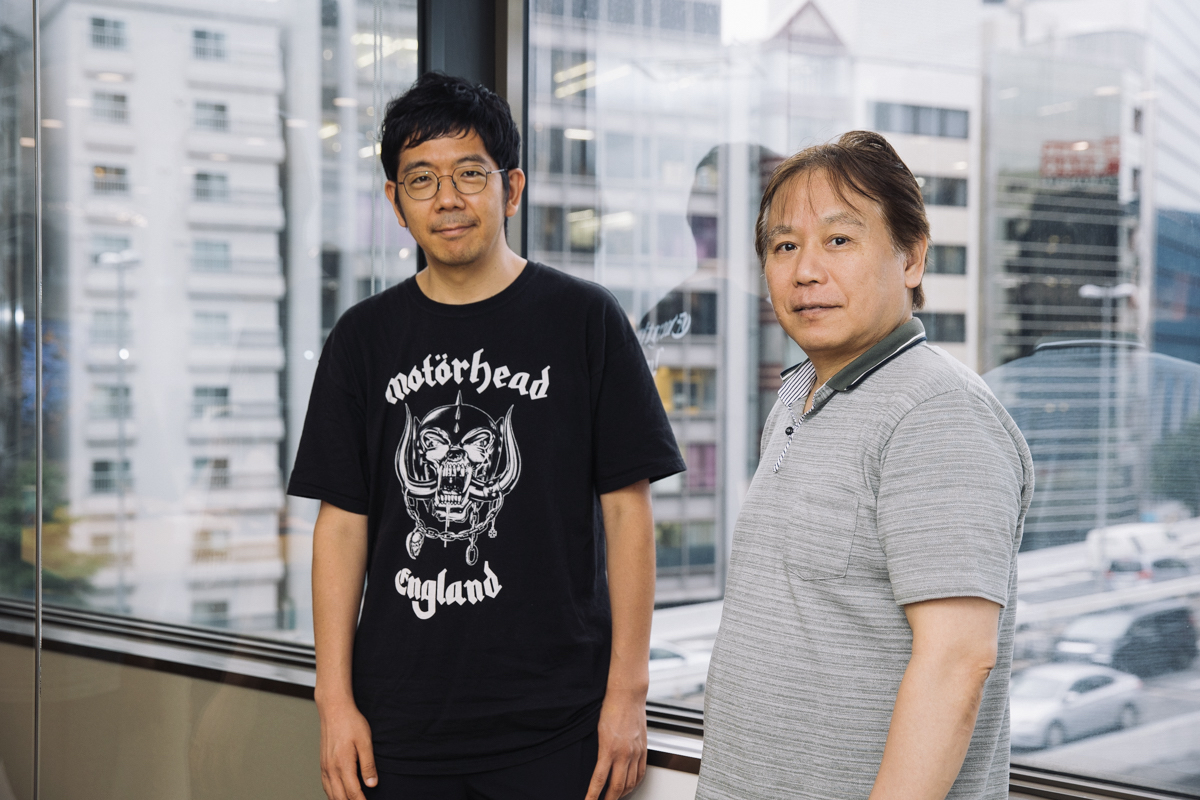
ジャーナリストの横田増生氏が、コラムニストで消しゴム版画家のナンシー関の実像に迫った大作『評伝 ナンシー関 「心に一人のナンシーを」』。2012年に朝日新聞出版から刊行され、14年には朝日文庫となっていたが、今年の5月に新たに中公文庫から復刊された。

そんな横田氏とライターの武田砂鉄氏との対談をお届けする。武田氏はナンシー関のファンであり、18年刊行の『ナンシー関の耳大全77 ザ・ベスト・オブ「小耳にはさもう」1993-2002』(朝日文庫)では編者を担当している。二人にとって、ナンシー関とはどのような存在だったのか? 2022年の現在に見えてくる、ナンシー関のおもしろさ、そして批評性について、じっくり話してもらった。(篠原諄也)
何度も読み返してしまう面白さ

――武田さんにとってナンシー関はどういう存在でしたか?
武田:僕はナンシー関さんと直接的な接点があったわけではなく、ただのファンです。2002年に亡くなられた時は、僕はまだ大学生でした。高校時代から読んでいて、高校まで自転車通学をしていたんですが、途中にコンビニが2軒あって、いつも週刊誌を立ち読みしていました。そこで「ナンシーさんは、今週はどんなこと書いているのかな」って。
同級生の多くは週刊誌を読んでいないので、ミッチー・サッチー騒動についてナンシー関がどう書いているかについて、語り合える人を探したりしていましたね。
当然、文章の面白さ・強度に引き込まれていました。当時から、ライターの仕事をやろうと思っていたわけではないですが、ひとつの対象をいかにつかまえるかという視座は勉強になりました。「信仰の現場」など、取材ものも書いていますが、基本的にはテレビの前で、その対象についてどう感じたかを書き続けました。
39歳、若くして亡くなられたので、「今、もしナンシー関がいたら」とずっと言われてきました。その枕詞が機能しているのはなぜなのか。メディアの形も大きく変わってきました。ただ、『ナンシー関の耳大全77』の解説で書いたように、ナンシーさんからの目がなくなり、放免された芸能人たちがいるのも事実です。だから、そういう人たちにチクっと言いたいなと思ったりはしますよね。
横田:ナンシーさんを好きなのは、武田さんより上の世代が多いですね。だから、すごく早熟な読み手だったわけですよね。
武田さんの解説を読みながら気づいたんですけど、僕はナンシーさんが亡くなった2002年以降、テレビを見なくなったんですよ。偶然なんですけど、うちの息子が生まれた年でした。テレビがあったら喧嘩するじゃないですか(笑)。だから面倒くさいと思って、捨ててしまいました。
武田:なにも、捨てることはないじゃないですか(笑)。
横田:コマーシャルに耐性がないんですよね。アメリカにいた時は仕事で仕方なくテレビを見ていましたが、コマーシャルを見ないでいいように、コマーシャルのたびにチャンネルを変えながら見ていました。でも日本ではコマーシャルが大量に流れるから、我慢ができないんですよね。
武田:横田さんの評伝が出たのは2012年です。ということは、原稿を書く時にはもうテレビがない状況だったわけですね。それでもなお、ナンシー関について書いたのはなぜだったんですか?
横田:やっぱり、面白かったから。今回は2回目の文庫化で、改めてゲラに目を通しましたが、ナンシーさんのコラムを読み返してしまうんですよね。本を取り出してきては、読んで笑ってしまう。「違う、ゲラを読まなきゃいけない!」と思って。その繰り返しでしたね。
ナンシー関が鋭かった理由

武田:ナンシーさんが書いていた頃は週刊誌の影響力が強かった時代ですね。1週間に1回、何をどう書くのか。書く側にも、読む側にも、緊張感があったはずです。同時に、テレビもメディアとしての力が強く、芸能人は今以上にお茶の間で大きな存在でした。だからこそ緊張関係の中にあった。
今ではSNSを中心に、芸能界の内側から情報がいくらでも発信されるようになりました。「テレビ的な演出でやりあっているけど、実はこの二人はよく飲みに行っていて仲が良い」とか、業界内のマッピングまで知っている。視聴者と芸能人側が互いに寄り添うような流れが生まれました。だから今、テレビに出ている人に対する批判って、なかなか出しにくくなっています。
横田:ナンシー関に連なる人が出てこない。テレビ批評を書くコラムニストはいるけれど、やっぱり二段、三段ぐらい格が落ちてしまう。何が一番違うかというと、文章の切れ味はもちろん、テレビを見ている量が圧倒的なんですよね。子どもの頃からテレビを見ている蓄積があって、それを的確に表す言葉の力があった。そのふたつが合わさって、ナンシー関だったと思いますね。
武田:たとえば、神田うのについて、ものすごくしつこく書いていましたね。今だと、神田うのについての情報は検索するだけで膨大に出てきますが、ナンシーさんが書いていた頃は、やっぱりテレビを見続けるしかなかったわけです。
様々なワイドショーをザッピングして、各テレビ局の映像のわずかな差異を見逃さない。そこから「神田うの」性を見出すという作業をやっていた。対象について知るアプローチが全く違うんですね。そういう意味では、非常に期間限定の芸風だったのかもしれません。
「神田うのの仕事は『うのでーす』と叫ぶことだ」と書いていました。この短文が見事な批評になる。その存在を包み込んでいる。普通だったら「神田うのはいつもテレビに出ているけど、一体この人は何をしているのだろう」と書く。それだと説明的だけど、面白くない。
「神田うのの仕事は『うのでーす』と叫ぶことだ」という一文を読み、読者は記憶の中から、これまでに見てきた神田うのの映像をいくつか抽出します。そしてナンシーさんの文章と照らし合わせてみる。そうか、そういうことだったのかとなる。ナンシーさんの文章はこの手の体験をさせてくれます。
横田:見方が唯一無二で、切るところがうまいですよね。キムタクだったら、ハンコに「モテモテ」とあって、「だてにキムタクやってませんから」と書く。いかにもキムタクらしいですもんね。
武田:デヴィ夫人のハンコには「夫人」という2文字が入っていた。神田うのの『うのでーす』と同じで、彼女のアイデンティティのすべてだと思えてくる。この端的な表現が見事なんです。
横田:あの選球眼は確かですよね。みんなテレビで同じものを見ているんだけど、誰もこうは書けない。やっぱりすごいなぁと。
武田:そうですね。これまで漠然と共有されてきたものに対して、その造形というか輪郭を指摘していく。本当に難しいことです。






















