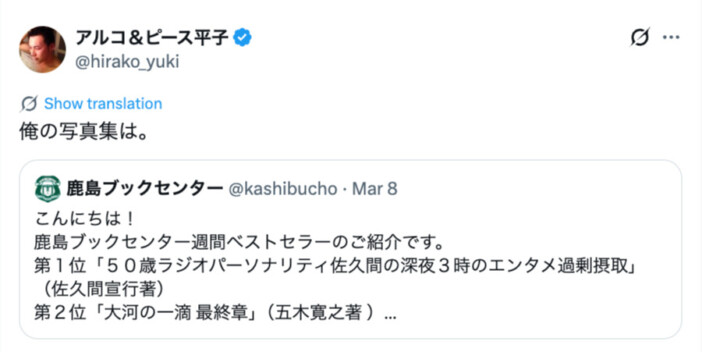今村翔吾『塞王の楯』など、直木賞・芥川賞受賞作がトップ3を独占! 文芸書週間ベストセラー解説

2月期ベストセラー【単行本 文芸書ランキング】(2月8日トーハン調べ)
1位 今村翔吾『塞王の楯』(集英社)
2位 米澤穂信『黒牢城』(KADOKAWA)
3位 砂川文次『ブラックボックス』(講談社)
4位 浅田次郎『母の待つ里』(新潮社)
5位 今野敏『探花―隠蔽捜査9―』(新潮社)
6位 林真理子『李王家の縁談』(文藝春秋)
7位 逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』(早川書房)
8位 浅倉秋成『六人の嘘つきな大学生』(KADOKAWA)
9位 遠藤和『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』(小学館)
10位 朝井リョウ『正欲』(新潮社)
1位は、ノミネート三回目で満を持しての受賞となった今村翔吾の『塞王の楯』。時は1573年、朝倉義景の守る一乗谷城に織田信長が攻め入り、落城させたところから物語は始まる。主人公は“石の声が聞こえる”という少年・匡介。両親と妹を失い、城から逃げる途中、石垣造りを生業とする穴太衆の頭目に拾われ、才能を買われ、後継者としても育てられることに。誰も攻め落とすことのできない石垣を築きあげることができれば、そんな石垣をもった城が世の中に溢れかえれば戦国の世は終わる……と願う匡介は、やがて同じ野望を抱く彦九郎に出会うのだが、鉄砲職人の頭目である彦九郎は、誰も立ち向かうことのできない圧倒的な砲をつくろうとしていた。“最強の盾”と“至高の矛”。生きるため、大事な人を守るために、必要なのはどちらなのか。戦を封じることができるのは、どちらなのか。現代を生きる我々にも他人事ではない問いをも描きだす本作を、選考委員の浅田次郎は「極めて作品の熱量が高く、力強い小説」「石垣職人と鉄砲職人の戦という極めて独創的なテーマで、楽しいエンターテインメント作品」と評価した。
ちなみに今村は、昨年11月に大阪・箕面の書店「きのしたブックセンター」を廃業の危機から救うべく、事業を継承し店長に就任したことでも話題となった。町の本屋さんが次々と姿を消していくなか、書店の未来を守るために立ちあがった今村の今後に、作家としても店長としても注目したい。
2位は2020年のミステリランキングで4冠を達成し、山田風太郎賞をも受賞した米澤穂信の『黒牢城』。デビューから歴史・時代小説を書き続けてきた今村に対し、ミステリ作家としてその評価を確実なものとしてきた米澤が、デビュー20周年の集大成として初めて手掛けた時代小説である本作。くしくも描かれる時代も『塞王の盾』と近く、1578年、本能寺の変が起きる4年前が舞台。織田信長に叛旗を翻して有岡城に立て籠った荒木村重は、城内で起きる事件を、囚人としてとらえていた織田方の軍師・黒田官兵衛に解決を依頼する……という戦国ミステリ。言わずと知れた時代小説の名手である浅田次郎に「私が思い返してもあまり類例がない戦国時代を舞台にしたミステリーで、極めてユニーク」と言わしめた一作だ。
そんな浅田次郎の最新作も堂々4位にランクインし、選考委員の貫禄を見せつけている。『母待つ里』は現代が舞台だが、浅田次郎が〝母〟を描くとなれば、心が揺さぶられる作品であるのは保証されている。だが今作、ちょっとこれまでとは色合いが違う。親も故郷も捨てた大手食品会社の社長・松永徹が40年ぶりに実家に帰るのだけれど、母と再会しても「こんな人だったろうか」と首を傾げ「お名前は」と聞く。母が好物だと言って差し出す料理には、覚えもない。なんだか変だ……と読み進めると、実家は「曲がり家」と呼ばれる伝統建築だと判明し、母は「むかしむかし、あったずもな」と語りはじめる。明記されていないが、あきらかに岩手県の遠野である。つまり、どんな不思議なことが起きてもおかしくないということだ――とがぜん、興味がそそられる。浅田次郎が切り開くふるさと小説の新境地もまた、直木賞受賞作とともに堪能してほしい。