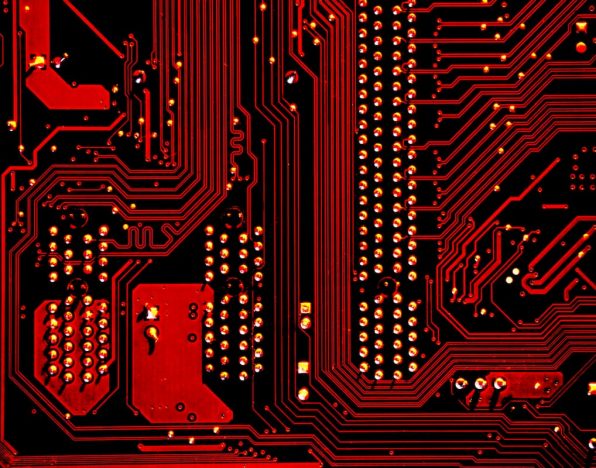100年前に想像された「ロボット」はどんな存在だった? 今なお古びない、テクノロジーへの問い

現実世界では今や様々な分野で、ロボットの導入が進んでいる。だがその働きはまだ、一つの作業に限定されている。人間のように複数の仕事をこなす知性を持ったロボットの開発は、できると言われつつも実現には至っていないわけで、本作で描かれる未来も議論の内容も古びていないことに驚かされる。それだけでなく、作者の〈私は、個々人としてではなく、機械として、人間を考えはじめるようになり、その道中、働く能力はあるが、考える能力はない人間を示す表現にはどういうものがあるだろうかと考えはじめた〉(付録「ロボットは……」)という発想から描かれるロボットは、長時間労働によって物事を落ち着いて考える暇も無い、現代の労働者の似姿にも見えてくる。
議論が一段落した後、実はヘレナに一目惚れしていたドミンは、唐突に愛を告白する。それから10年後、ヘレナは求愛を受け入れて島に残っていた。その間にロボットの一部は、より人間に近づくよう細工が施される。自分の意志を持つようになった彼らは、機械に仕事を任せきりの人間たちに対し、こう思うようになる。
〈あなたたちはロボットではない。あなたたちはロボットのように有能ではない〉。
ここから、ロボットたちの反乱が始まる。
そんな本作ではロボットについては詳細に書いているのに、こと人間の恋愛になると奥ゆかしい書きぶりの印象がある。ヘレナはドミンの強引すぎる求愛を、どのような思いで受け入れたのか? なぜ、島にはヘレナ以外の女性がいないのか? そのことをRUR社で働く男性陣は、どう思っていたのか? 書かれてはいない余白の部分を想像しながら、ロボットに夢中なドミン、夫の関心を独占する機械に複雑な感情を抱くヘレナという図式の恋愛物として読んでみる。そうすると、また新たな作品解釈が生まれてきそうだ。
長きにわたり読み継がれてきた名作だからこそ、あえて本筋から外れた読み方を試してみたり、今の視点から新たな発見はないか考察するのが古典作品を読む醍醐味というもの。機械的に作者の言いたいことだけを読み取る読書なんてしていたら、読者もロボットみたいになってしまう。
■藤井勉
1983年生まれ。「エキサイトレビュー」などで、文芸・ノンフィクション・音楽を中心に新刊書籍の書評を執筆。共著に『村上春樹を音楽で読み解く』(日本文芸社)、『村上春樹の100曲』(立東舎)。Twitter:@kawaibuchou
■書籍情報
『ロボット RUR』(中公文庫)
著者:カレル・チャペック
翻訳:阿部賢一
出版社:中央公論新社
出版社サイト