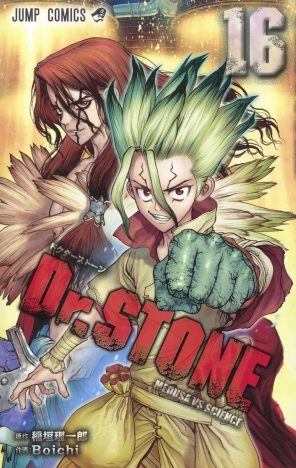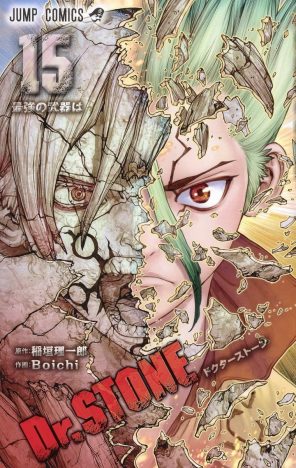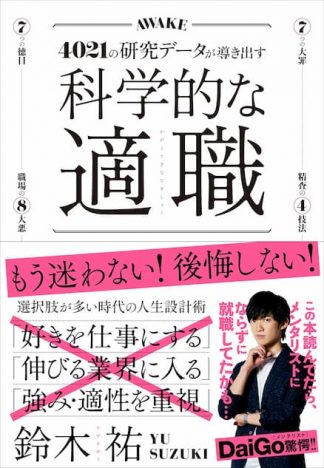茂木健一郎が語る、クオリアと人工意識への見解 「人間の心なんて簡単にロボットに移せると言っている人はまがいもの」

脳科学者・茂木健一郎がその専門分野であるクオリア(意識における主観的な質感)について、人工知能研究の動向を踏まえて書き下ろした『クオリアと人工意識』(講談社現代新書)が話題を呼んでいる。「現在の人工知能をいくら発展させても、人間のように意識を持つことはない」と断言する茂木氏に新刊で扱った「意識」の問題について、そしてコロナ禍で感じた本の価値について訊いた。(飯田一史)
意識の科学にとっての『種の起源』を目指す

茂木:一般の方ですと、マインドフルネスとか、フロー、ゾーンみたいなところを経由して意識の問題に入ってきますね。「マインドフルネスはGAFAも創造性を育むために使っている」とか「アスリートはフローやゾーンに入る方法を研究している」とかいう関心から。でもそれらの問題はいずれも僕のような脳科学者にとっては意識の現象学、意識の科学そのものなんですよ。
それから『クオリアと人工意識』で書いたような「人工知能が発達していけば、人工意識はできるのか?」という疑問から入る人もいます。トランスヒューマニズムやポストヒューマニズム、脳のデータを意識ごとコンピュータに移すマインド・アップローディングは可能だ、といった主張に触れて「意識とは?」と興味を持つケースも当然あります。
――この本で扱われるような人工意識についての議論は世界的に見て盛り上がっているのでしょうか?
茂木:ものすごく盛り上がっています。今回の本は主に英語圏での議論を踏まえて書いたものですから、これを読めば雰囲気がわかってもらえるんじゃないかな。海外では「マインドアップローディングが実現した状態から見れば、人間の脳は素材を提供するための元ネタにすぎない」といった過激な主張もされています。彼らが思い描いている未来の社会像や人間観がぶっ飛んでいるという話です。
まあ、「コンピュータに脳のデータを移し替えれば意識はできる。人間の心なんて簡単にロボットに移せる」と言っている人は基本的にはまがいものです。イーロン・マスクは存在としてはおもしろいし、好きなんだけど、そういう点に関しては微妙なところにいる。「脳とコンピュータをつなげられるインターフェースを作れば勉強なんかしなくてよくなる」なんて平気で言っちゃいますから。
――意識は今のAIに使われているような技術をいくら推し進めていっても作れない、そうではなくて現在の統計的手法を前提としない、まったく別様の研究手法が現れないかぎり意識の謎を解くことは不可能だというのが『クオリアと人工意識』の主張ですよね。茂木さんは意識を扱うことのできるまったく新しい数学などが現れる可能性は実際のところあると思いますか?
茂木:過去にも、たとえば宇宙の理論には同時代の数学者の多くが理解できないものがあったりしたわけです。おそらくクオリアの数学ができるとしたらそういった、今の数学は役に立たない、まったく新しい数学なんじゃないかな。
僕の人生最大の野心はダーウィンのポジションに行くことなんです。『種の起源』は自然選択(自然淘汰)による生物進化を専門家以外にもわかるように説明した画期的な本です。ただ本が出た当初はあくまで仮説にすぎなくて、実際に生物がどう進化していくのかがわかったのはそこから約百年経ってDNAの構造が判明してからなんですね。だけれども『種の起源』ですでに大枠の道筋は示されていた。
それと同じように、今すぐ意識の数学ができるとは思えないけれども、「物質である脳になぜ意識が宿るんだろう?」とか「なぜ自由意志があるんだ?」といった議論に対して腑に落ちる枠組みを示すことはできるかもしれない。僕はそれを目指している。
意識の科学はチェスや将棋に似ているんですね。意識という王様を目指して手を指していく。この本で書いたベルクソンの「純粋記憶」についての議論は、将棋の駒にたとえれば飛車くらいかな。でも飛車だけでは王様を詰められなくて、いろんなタイプの駒を用意して攻めていかないといけない。以前よりは持ち駒が揃ってきたけれども、まだ途上にある、という感じですね。
――茂木さんが意識研究に関して注目している人や組織はありますか?
茂木:Microsoftの共同創業者ポール・アレンが作ったアレン研究所にクリストフ・コッホが移ってきたんですが、コッホとアレン研究所の取り組みは興味深いですね。コッホはもともとDNAが二重螺旋構造であると発表したフランシス・クリックの共同研究者で、意識に関する論文を書いてきました。アレン研究所は脳の遺伝子の発現をビッグデータを駆使して詳細にマッピングしているんですよ。人工知能研究者は脳に興味がないことが多いんだけど、この本でも書いたように、意識は生命現象、生命科学ですから、遺伝子という物の発現から何かわかってくるかもしれない。
――「人工知能研究は身体性の限界を軽んじている」と本の中で批判されています。現在のロボット研究についてはどう考えていますか。
茂木:身体性はAI研究においては意識と並んで重大なチャレンジであり続けていて、僕もロボットやAIの研究者とは過去20年くらい議論してきました。身体性は「いかにロボットやAIに『常識』を持たせるか?」という点から研究者たちが気にしているんですね。たとえば介護をロボットにやらせようというときに、現状のAIではとんでもないことをさせてしまう可能性がある。じゃあどうやって人間が持っているような常識を持たせるのか。複雑な計算をしなくても、身体性があることによって常識が降臨する――みたいなことをロボット研究は追求している、というのが僕の理解です。ボストン・ダイナミクスや自動運転技術がそこをブレイクスルーできるのか、興味深く注視しています。