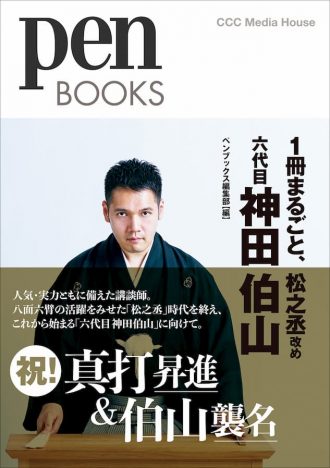映画から戦争を知る『日本の戦争映画』 著者・春日太一が込めた痛切な想いに触れて

徴兵制を設けている国は現在でもあるが、日本でもかつて1945年までその制度が存在していた。満20才(1943年からは満19才)になると身体検査の上、高い確率で戦地へ送られた。
筆者は1977年生まれで、自分が20才だった1997年には、すでに太平洋戦争敗戦当時の記憶がある世代は50才以上、戦争体験者になると祖父母の世代だった。しかしお盆にはTV各局が戦争をテーマにしたドラマ、ドキュメンタリーを放送していた。
それからさらに23年が経った。今20才の人の周囲で戦争体験を語れる人を探すのはますます難しいだろう。空襲の恐れがある都市部から地方へ学童疎開を経験した人でも80才以上、また通常の制度で兵役を経験した人は90才以上になっている。
これから紹介する『日本の戦争映画』の著者・春日太一は筆者と同じく1977年生まれ、体験者の語りや映像などであの戦争を見聞きしていた世代だ。本書は敗戦後から戦後50年(1995年)までに公開された日本の戦争映画を年代順に紹介し、内容や関わった監督、脚本家たちの言動を検証する一冊だ。
冒頭で春日は次のように記している。
ニュートラルな視点から戦争映画と向き合い、戦後五十年の変遷を俯瞰して検証することを目指しています。そして検証しているのはあくまでも「映画」であり「映画の作り手」です。「戦争そのもの」ではありません。(中略)作り手の戦争映画の向き合い方にはそれぞれ違いがあり、そのことが作品ごとに微妙なグラデーションを生んでいます。この本では、そのことを伝えたい。イデオロギーで切っては二色にしかならず、グラデーションが見えてきません。
春日はこの本を書くに当たって、様々な工夫を凝らしている。例えば、文章は「ですます」調になっており、丁寧で優しい印象だが、冷静なナレーションにも思える。戦争の残酷さと映画に投影された作り手の想いがリアルに浮かび上がってくるようだ。
また作品紹介では、それぞれの監督・脚本家たちの「敗戦時」の年齢を必ず記しているのも注目だ。これがあるからこそ、今を生きる若い読者にとっても戦争が地続きに感じられ、よりビビットに見えてくるのではないだろうか。
戦争映画に作り手として携わった人々は様々だ。特攻部隊に所属した人、兵役経験のある人、当時はまだ学生や子どもだった人……。のちの作り手が、戦時中色々な立場にいたことによって、戦争映画と言っても、それと一括りに表現できない広がりがあることに改めて気づかされる。
さらに、年を経て、戦争映画も変化していく。恋愛などの要素(本作では「戦争情話」という言葉を用いている)を入れ、主題歌やテーマ曲を有名歌手が歌うことで、娯楽作品として観客の心を掴んでいたことも指摘している。
戦争をテーマにはしているが、大前提として「映画」なのだ。硬軟はあるが、制作に真摯に向かう者、商売第一に考える者、また両方の折り合いをつける者と、著者はグラデーションをつけて描いていく。中でも、岡本喜八監督に触れた章は必読だ。