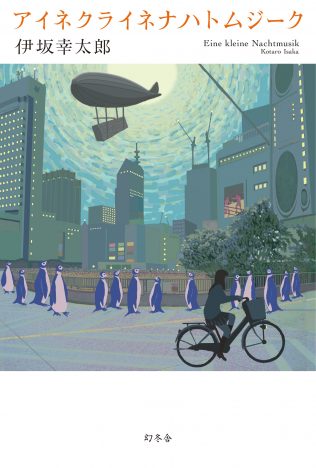限界集落を巡る、悲劇と喜劇のミステリー 米澤穂信『Iの悲劇』が問いかけるもの

Iの悲劇。「I」とは「愛」と思いきや、「Iターン」、つまり都市部から出身地とは別の地方に移り住もうとする人々のことを意味する。そして、話題の映画『ジョーカー』の台詞「My life was tragedy. But now I realize, it’s a comedy.」ではないが、悲劇は裏を返せば喜劇にもなり、本人たちにとって見れば、長年の夢や理想や信念を壊される悲劇であったとしても、傍から見れば喜劇だったりする。それが人生であり、現実だ。つまりこのミステリーは、まるで鳥が空から大地を生きる有象無象どもを眺めるように、一度は滅びた村という箱庭の中を、それぞれの理想と夢を持ち寄って奮闘する人々がひしめき合う様を、徹頭徹尾冷静に描いている。
9月に文藝春秋社で刊行された米澤穂信の新刊『Iの悲劇』は、限界集落を描いた連作短篇集である。米澤穂信は『氷菓』(角川文庫)をはじめ、アニメ化・映画化もされた「古典部」シリーズが有名だが、なんといってもミステリー賞2年連続3冠に輝いた『満願』(新潮文庫)と『王とサーカス』(創元推理文庫)の面白さである。
特に短篇集『満願』は、安田顕や西島秀俊、高良健吾らが演じたNHKドラマ版も素晴らしかったが、どの短編もタイプの違う魅力が凝縮されていて、1つの物語を読み終わらない限り他の事に手がつかないぐらいだった。中でも美しい中学生姉妹の裸身と月夜の物語『柘榴』は、その冷たく研ぎ澄まされ、かつドロリとした官能と狂気に息を呑んだ。
米澤穂信の文章は、常に冷静である。『夜警』や『万灯』、『関守』の仕事熱心な主人公たちがどこかでボタンを掛け違い、破滅へと向かっていくのを著者自身は冷静に見送っている。『Iの悲劇』もまさにそれで、カラリと冷めた筆致が、個性的な登場人物たちの人生の哀愁やおかしみを、万願寺邦和という愛ある傍観者の視線で描くことで、我々が目を背けがちな限界集落と地方自治の現実を突きつける。
舞台は、ある老女の「ありふれた、問題のない死」をきっかけに、自殺し損なった最後の一人が街の養老院に移ってカラオケの人気者になり「そして誰もいなくなった」山あいの小さな集落、蓑石。一度人がいなくなり「死んだ」村に、Iターン志願者を住まわせ、彼らをサポートすることで定住を促し、村を甦らせようという市役所のプロジェクト、人呼んで「甦り課」のメンバー3人が、個性豊かな移住者たちの巻き起こす事件を1章ごとに解決していく「人が死なないミステリー」である。
その3人というのが面白い。まずはこの物語の語り手である、真面目で出世願望が強い公務員・万願寺邦和。考え方もいかにも役人気質、仕事一筋といった感じで、一人称がないせいか、どこか没個性的である。だが、誰よりも住民たちに親身になって仕事をし、彼なりの信念を持っている。
もう1人は、住民たちには好かれているらしい、気さくで自由奔放な、イマドキの新人、観山遊香。
そして何より魅力的なのは、定時退社が何よりの特技、仕事嫌いの課長・西野秀嗣。彼こそがこの物語における「安楽椅子探偵」なのである。万願寺と観山が現場を走り、丁寧に書き上げた報告書から、ふいにやる気を出したかのように、名推理を披露する。
しかし、読者は読み進めていくにつれて、「何かがおかしい」と感じ始めることだろう。彼らは何もできないからだ。土砂が崩れた跡があろうが、雨漏りしていようが、予算がないから問題を解決することができない。悩みを聞きながらも放置されていく問題を不審に思いながら、東京に住む万願寺の弟からは「消耗戦」と言われる止まれない日常を繰り返していく。その違和感が最後の一章で解消されるこの快楽と衝撃は読んでみなければわからない。