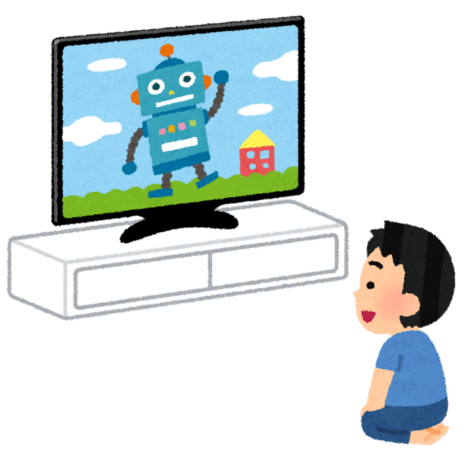2023年を振り返るアニメ評論家座談会【前編】 “宣伝戦略”の重要性にみる時代の変化
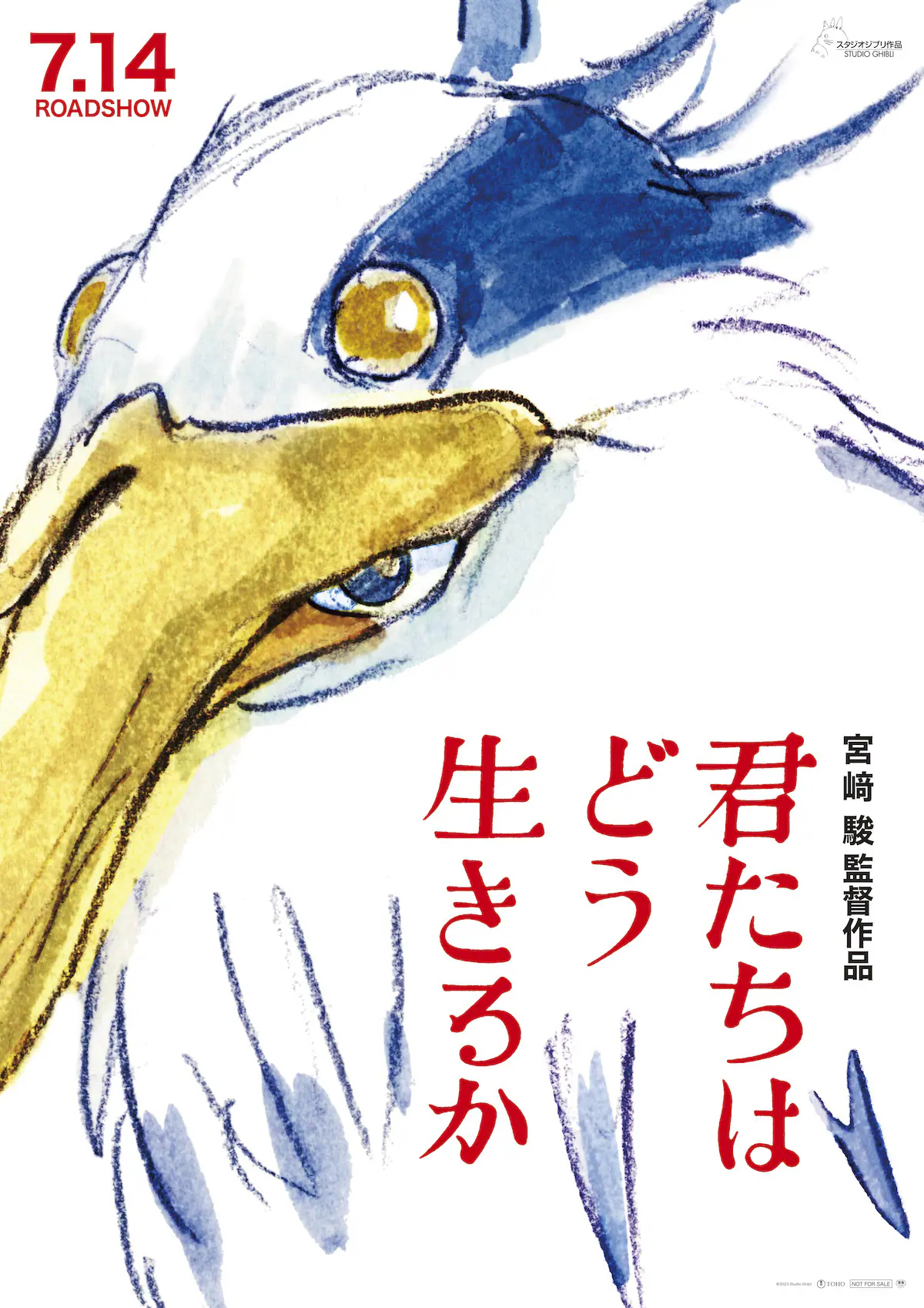
2023年を象徴するアニメとなった『【推しの子】』
ーー『【推しの子】』は「Yahoo!検索大賞2023」アニメ部門1位にもなるなど、とても大きな話題になりました。
杉本:『【推しの子】』が扱う「推し」という概念は、2023年で確実に曲がり角になったはずです。旧ジャニーズ問題、宝塚問題など、推し活は必ずしも良いことばかりなのだろうか、という問いがあります。この作品は、「推し」に対して両義的な部分を持っているので、時代の物語として的確だったと思います。過剰に否定しているわけでもなく、完全に肯定しているわけでもない空気感になっていますし……。
藤津:アクアの斜に構えた感じが、『葬送のフリーレン』が年配向けであるという話に対して、むしろ若い子向けだと感じました。あれくらいわかりやすく斜に構えているのは、痛快だなぁ。そういうキャラクターの魅力は強いと思います。
渡邉:私は、「推し」という文化との関連でいうと、最近流行っている転生ものを使った設定が非常に面白いと思いました。『明るい映画、暗い映画』(blueprint)などでも、ここ数年、私も「推し」について論じてきましたが、多くの論者も共通して指摘しているように、推し活の本質とは、対象=推しとファンとの距離の近さにあります。推し文化の台頭の時期がSNSの普及期と重なっているのも、そこに理由があります。例えば、以前は、ファンと憧れの対象との距離は遠く、関係は一方的でした。それは「スター」という言葉に象徴されています。手に届かない星だったわけです。でも、推しというのは、それがSNSの介在もあって極端に密接になっている。「押し」という響きの近さからも接触性のニュアンスがあります。その点、『【推しの子】』という作品は、まさにファンが推しの「子」に転生してしまう、人間関係の最も親密な「親子」になってしまうという設定で(笑)、まさに推し活(論)に対するある種の自己言及、メタ批評になっているところが興味深い。たまたまかもしれないですが、芸能界のドロドロした話からは、SMILE-UP.の問題などとシンクロしているようにも見える。これらの問題を本質的にラディカルに描いた、今年を象徴するコンテンツだと思います。
『【推しの子】』やブシロード作品も頑張った! アニメ“3話切り”回避の歴史と今後
アニメファンの間で「3話切り」という言葉があります。これは第3話まで観て作品の雰囲気や方向性を掴み、視聴するかどうか判断するとい…
杉本:『【推しの子】』はいわゆるミステリー形式になってますけど、渡邉さんはミステリー評論家としてはいかがですか?
渡邉:昨年11月に刊行した『謎解きはどこにある』(南雲堂)でも問題にしましたが、現代のミステリをめぐる想像力では、一方で陰謀論にも発展するような「考察」への関心と、もう一方でポスト・トゥルース的状況をなぞるような唯一の真相などに関心がなく、個々の主観が信じることが「真相」で、それでいいのだというシニシズムが二極化していると思います。実は私は『【推しの子】』をなぜかあまりミステリとしては観ていなかったのですが(笑)、そういう意味では、確かにこの作品も、昨今人気の考察ドラマとも通じるような視聴者の考察欲を惹起する巧みな展開になっていると同時に、そもそもアイドル文化や恋愛リアリティ番組など、真実と嘘の対立を脱臼するようなリアリティが作中のいたるところにちりばめられている世界観が、ミステリとしても、とても現代的だなとは思います。
藤津:ミステリとしてうまくできているのは、後から証拠が出てきても嘘にならないように最初から設定が組まれていることです。最初はヒントがなく、少しずつ情報が出てくるので、後出しで答えを決められるような作りがうまいと思います。さすがは、連載漫画の作り方ですよね。ミステリーでは、事件の発生時点で手がかりが揃っていることが多いんですけど、そうでなくとも不自然さがない。
杉本:アイドルものとして受容もされているし、プロモーションのされ方も極めてアイドルものなのに、「あれだけ裏側を描いても、ファンがちゃんとついてくるというダブルバインドは一体なんなんだろう?」とは思いますよね。 実際、芸能界の汚いところって、現実世界でも周知の事実だからリアリティがあっていいということでしょうか。今年は、その周知の事実が改めてニュースになった年でもあるという点で、『【推しの子】』は、この2023年の空気にドンピシャだったと思います。
藤津:アイドルアニメはたくさん作られていますが、複雑なんですよね。リアリティラインを上げようとすると芸能ものになりがちで。ゲームベースのアニメが多く、キラキラ感だけを取りたいと思うと、リアリティラインが上がりきらないので、描けるものが限られてくる。その点、今年だと、『アイドルマスター シンデレラガールズ U149』は渋いところにきてましたよね。シンデレラガールズの中から、背の低い子だけ集めたユニットを作る。しかもプロデューサーになったのは、めんどうな企画ということで、押し付けられた若手で(笑)。作画も丁寧で、演出で魅せるところも多く、なかなか完成度が高い作品でした。だからそういう意味では、『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』のヒットは、ザ・芸能界ものの『【推しの子】』と裏表だなと思うんです。これは、ライブなので、キラキラしか存在しない。バーチャルカメラを作って、100個ほどのカメラをセッティングし、スイッチングを行ってるんですよ。CGの精度が高い一方で、コンサート映像なのでカメラの切り返しがほとんどないのが特徴です。だから、コンサート映像としてリアルな仕上がりになっていました。1箇所だけ切り返しがある場所は、因縁のあるキャラ同士の組み合わせで、知っている人には特別な面白さがあったということです……。2016年に『KING OF PRISM by PrettyRhythm』が大ヒットしたことは、アニメ業界においては応援上映の分水嶺だと思っています。その前にも応援上映的なものも行われてはいましたが。
興収17億円突破! 『劇場版アイドリッシュセブン』が3次元アイドルファンに刺さった理由
人気スマートフォン用アプリゲーム『アイドリッシュセブン』(以下、『アイナナ』)は、2022年8月20日に7周年を迎え、その後「7…
渡邉:2016年の『キンプリ』の応援上映は、確かに私も、人生でゴダールの『勝手にしやがれ』を観た時と同じぐらいの衝撃を受けましたからね(笑)。
藤津:真剣に観ないと、って感じですよね(笑)。アニメにおけるライブって、映画館で体感することだから。それで言うとね、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』もすごく体感寄りですよね。

杉本:あれはまさにゲームの映画化ですね。僕らがゲームをプレイしてきた体感をそのまま、ある程度のナラティブに当てはめたらこうなったみたいな。そのバランスが、非常によかったです。僕的には、これが“世界的に大ヒットした”意味はやっぱり大きいです。これを機に、任天堂が本格的に映画産業にも進出しそうになっているので。任天堂の持ってるIPの力の強さを証明できたはずです。 おそらく、キャラクターIPでディズニーに対抗できる、世界で唯一の会社なんですよね。それが突然のように映画産業に出てきた意味は、これからさらに大きくなってくるだろうと思います。
渡邉:没入型VRにも通じる、体感型ムーブに振り切ったっていう感じの、ゲーム的作品でしたね。ディズニーとの比較で言うと、最近ディズニーって、実写も含めて意識しすぎなくらいにマイノリティを出したり、マーベル映画と並んで(今やマーベルもディズニー傘下ですが)、ポリコレの負荷が強くなってると思うんですよ。もちろん、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』のマリオとルイージがイタリア移民の下層労働者だったりとか、アイデンティティポリティクスに関する部分はありますけど。極端な話で言うと、批評的に観てると「最近の“そういうディズニー”にもう辛くなっちゃった」みたいな声も少なからずあって。そういう時に、今回の『マリオ』は「単純にファミリーで冒険物語を楽しみたい」層にヒットしたのかなとも思います。