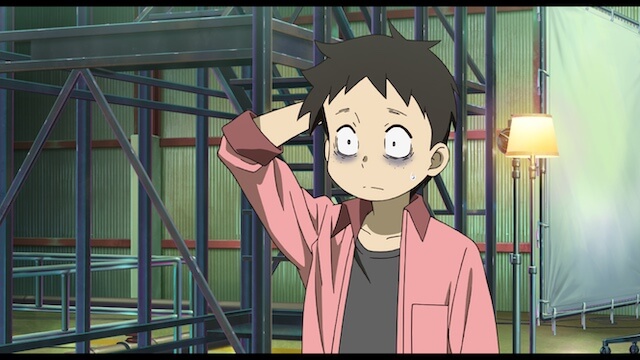『映画大好きポンポさん』には人生の教訓が詰まっている “編集”に着眼した新しさ

平尾隆之監督作品『映画大好きポンポさん』(以下、『ポンポさん』)は、キーボードの「delete」ボタンを繰り返し見せる。
本作は、杉谷庄吾【人間プラモ】氏の同名マンガを原作にした長編アニメーション映画だが、実写映画の製作現場を描いた作品だ。「映画作りを描く映画」は、これまでに数多く作られているが、本作はそれらの作品群の中で特異な位置にある。それは、本作がアニメだからというのもあるが、それ以上に「delete」ボタンが象徴するものによって生じている。
映画制作は大まかに3段階に分けられる。撮影前の準備段階であるプリプロダクション(プリプロ)、撮影、そして編集と音響制作など撮影後に行う作業を指すポストプロダクション(ポスプロ)だ。
映画作りを描く映画は、撮影現場かプリプロでのやり取りを中心に物語が構成されることが多い。DVDなどの映像特典として定着しているメイキング動画でも撮影現場に比重が置かれる。だが、『ポンポさん』の物語は、ポスプロである編集に重心を置いた構成にしている。
これは非常に画期的だ。なぜなら、映画を映画たらしめる作業こそ編集だからだ。そして、映画作りを描く映画において、今まで意外と軽んじられてきた編集という作業を中心に人間ドラマを組み立てることが可能であると証明したからだ。
編集こそ映画の醍醐味
映画制作には多くの人間、多くのお金が必要であり、そこには映画の内容に負けず劣らずの濃密な人間関係が生じる。もの作りへの情熱と商業的事情がぶつかり合い、異なる意見が噴出し、ロケ現場で突発的事態が良く起こる。映画作りの現場は実に物語にしやすいのである。
しかし、それらの映画は主に撮影現場を中心に据えることが多い。
代表的なのは、フランソワ・トリュフォー監督の『映画に愛をこめて アメリカの夜』だ。「パメラを紹介します」という劇中作の撮影現場で起こる悲喜こもごもを描く群像劇である本作は、トリュフォーの映画愛が詰まった名作として名高い。本作はもっぱらフランスの撮影所内で物語が進行し、ハリウッド女優のトラブルや困った新人男優、スタントマンと駆け落ちしてしまうスタッフなど、様々な出来事を通じて映画撮影の苦労を描いている。
日本映画で代表的な作品は、『蒲田行進曲』だろう。つかこうへいの戯曲を深作欣二監督が映画化したこの作品は、時代劇の撮影現場を舞台とした人情劇だ。この2作品は、映画作りの現場には、実に可笑しな人たちが集まってくるのだなと思わされる。
撮影現場を主体にせず、業界の内幕や映画史の変化を背景にした作品も数多く製作されてきた。ミュージカル映画の名作『雨に唄えば』は、セリフのないサイレントから同時録音可能となったトーキーへと映画が変化していた時代を舞台に、サイレント時代の大女優の没落と新人女優がスターになる瞬間を描いている。サイレント時代の役者には滑舌や声の美しさは求められていなかったが、台詞を喋らないといけなくなったトーキー時代に活躍できなくなった役者は数多く存在したのだ。
ビリー・ワイルダー監督の『サンセット大通り』もサイレント時代の大女優がかつての栄光を引きずり悲劇を起こす様を描いている。一方で、デイミアン・チャゼル監督の『ラ・ラ・ランド』のように、夢を追いかける若者を煌びやかに描く作品もある。
自らの体験や苦悩を反映させた作品を作る作家もいる。フェデリコ・フェリーニの『8 1/2』は主人公を自らの分身と言える映画監督に設定し、新作の企画作りに苦悩する映画監督を多様な隠喩表現で表現している。空を自由に飛びたくても足がロープに繋がれている冒頭のイメージは、想像力を自由に羽ばたかせたくても、予算など様々な都合で不自由を強いられる映画作りを暗喩している。
作品名を挙げればきりがないほどたくさん作られているが、ポスプロ作業がフィーチャーされた作品はほとんど見かけない。しかし、映画が先行する諸芸術と異なる独自の表現として確立できたのは編集というプロセスがあればこそだ。その意味では、編集こそが映画の独自性であり、本来の面白さがあると言ってもいいのだ。
編集は役者の芝居すら変えてしまう
『ポンポさん』は、その編集の面白さを存分に描いている。撮影現場のシーンは、物語の前半で終了し、ポンポさんの「役者は今日で打ち上げだけど、ジーンくんはここからが本番」の言葉どおり、本作の本質は後半パートの編集に宿っている。
編集室に籠もった監督のジーンは、名優マーティン・ブラドックともう1人の男優が言い合うシーンを編集している。はじめにつないだバージョンは、説明的な引きの絵と2人の役者を捉えた切り返し替しのショットをつないだオーソドックスなもの。しかし、インパクトが足りないと思ったジーンは、思い切って俯瞰の引きのショットで役者の表情を見えないようにして、決め台詞で初めてクローズアップを用いる。こうすることで、決め台詞の役者の芝居が際立つ。
同じシーンの同じセリフでも、編集によってまるで異なる印象になるのが良くわかる。シーンの雰囲気やリズムのみならず、役者の芝居の印象すら変わっている。編集は、芝居を上手くすることすら可能であると、わかりやすく見せている秀逸なシーンだ。
役者と編集の関係で面白いエピソードがある。2014年のアカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞したルピタ・ニョンゴは、受賞スピーチで監督や共演者に感謝を述べた後、「編集室の見えざるパフォーマー、ジョー・ウォーカー、ありがとう」と編集者を名指して謝礼を言ったそうだ。(『映像編集の技法』スティーブ・ハルフォード著、フィルムアート社、P7)
役者の芝居と生かすも殺すも編集次第。ルピタ・ニョンゴはそのことをよくわかっているのだろう。
それくらい重要なプロセスである編集が、なぜ映画作りを描く映画では描かれにくいのか。それは、編集現場が「地味」だからだろう。
本作でも描かれる通り、編集ルームは暗い部屋にコンピュータがあるだけだ。そこで編集者が1人(時にはアシスタントと2人)モニターをにらみ続けているのが編集だ。撮影現場と比べて華やかでないし、ドラマも起きにくい。
だが、ドラマは起きているのだ、編集者の頭の中で。本作は、そんなカメラでは撮影できない編集中の「頭の中の葛藤」を自由闊達なアニメーションによって描き出すことに成功している。本作は、アニメだからこそ、エンタメとしての強度を保ったまま編集の大切さを描けたと言えるだろう。