異色のアニメーション映画 『映画大好きポンポさん』はなぜ多くの観客の共感を集めるのか

イラスト、漫画投稿サイト「pixiv」で人気を得て出版もされた、映画への愛情をぶつけた同名漫画のアニメーション映画化作品『映画大好きポンポさん』が、一部で話題を呼んでいる。
本作が特徴的なのは、一般に「アニメ絵」と呼ばれる、日本のアニメーション作品特有の絵柄で、実写映画の製作を描いているという点だ。本作はそんな、普段はあまり交わることのないジャンル同士の垣根を越えて、両方に足をかける珍しい存在になっているのだ。
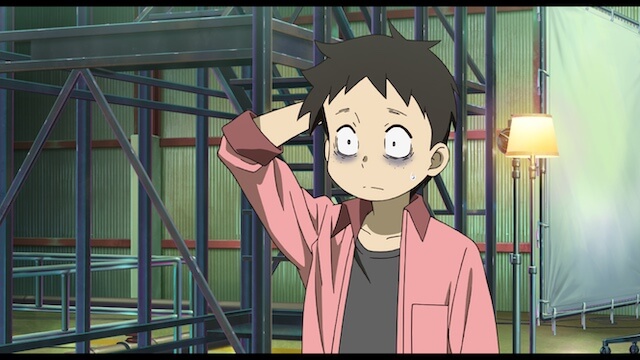
『映画大好きポンポさん』がアニメーション映画として異色作だと感じる理由は明らかだ。漫画作品は作家自身のスキルに大きく左右される。原作者・杉谷庄吾自身の絵柄が、もともと日本のアニメに強く影響された画風であり、同時に実写映画に興味を持ったパーソナリティであるならば、原作漫画のような作品が出来上がることは、何も不思議ではない。しかし、アニメーション映画ともなれば、莫大な製作費と大勢のスタッフを必要とする一大事業となる。その上で、本作のようなバランスの作品が製作されたのは興味深い。
とはいえ、TVアニメ『SHIROBAKO』『映像研には手を出すな!』が一部で話題となり、映画『カメラを止めるな!』(2017年)が予想を超えたヒットを果たしたように、集団的なものづくりの裏側を描く作品に興味が集まっているなかで、同様の題材を扱った企画が実を結んだこと自体は、むしろ時流に乗っている点だともいえるだろう。

本作の舞台は、アメリカの映画産業のメッカ、ハリウッドをモデルにした「ニャリウッド」。主人公ジーン・フィニは、伝説のプロデューサーといわれるJ.D.ペーターゼンの孫でB級作品を得意とする映画プロデューサーの少女J.D.ポンポネット、通称“ポンポさん”のアシスタントを務めている。自分に自信がなく、映画だけを友達としてきたジーンは、ある日、ポンポさん直筆の脚本と、彼女の手引きによって、新人女優ナタリー・ウッドワードや、多くの賞を持つ有名俳優マーティン・ブラドックらが出演する新作の監督を手がけることになる。
実在のハリウッド俳優ナタリー・ウッドをはじめとして、実在の映画人の名前をコラージュしたような登場人物たちは、それぞれに自分の仕事に集中し、優れた映画を完成させるために力を尽くしていく。その物語のなかで、撮影、編集、資金調達など、映画製作の一部分が説明されるのが本作の構造だ。

とはいえ本作で描かれるのは、実際の映画製作事情とは異なる部分が多いのも事実だ。ポンポさんは、いかにB級作品を中心に撮っているとはいえ、少女でありながら「映画は女優を魅力的に撮ればOK」などと、ふた昔前の中年以上の男性プロデューサーのような言動をするし、“老年の指揮者が田舎の自然のなかで若い女性に生きる希望をもらう”という、いかにも日本的で、近年のハリウッドでは受けが悪そうな題材で脚本を書く。現在の多くの女性プロデューサー像からは、かなり乖離している存在である。しかし、本作の舞台はあくまで「ニャリウッド」であり、ハリウッドを原作者や平尾隆之監督らが日本的に解釈した場であると考えられる。
このように、設定を架空のものとすることで、実際の製作現場や技術的な問題、文化などが現実に沿ってなくても成立させさられる手法は、例えば未来の日本を舞台にした『映像研には手を出すな!』でも使われていた。ファンタジー世界であれば、専門家から文句を言われる筋合いはない。ただし、劇中で土下座をする場面は、強烈に違和感を覚える部分であることは間違いないだろう。アメリカを含めて、そのようなかたちでの謝罪や懇願の文化がない多くの国では、意味が通じにくい表現だ。

その他にも、例えば、敏腕製作者による、ボリュームを考え抜かれた脚本を基にしているはずなのに、編集でそのほとんどを削るような、多くのシーンを無駄にする撮影が行われていたり、劇中の山場となっている、監督が追加撮影を要求する場面で、ポンポさんが“同じ撮影スタッフたちを集め直さなければならない”と説明するようなケースも、通常はあり得ないだろう。この場合、すぐ動けるスタッフで撮影し、別ユニットとしてクレジットする方法を迷わず選び、予算を引き上げられるようなリスクを避けるはずだからである。





















