「平和ボケ」は悪いことなのか? 東浩紀著『平和と愚かさ』を梶谷懐が読む
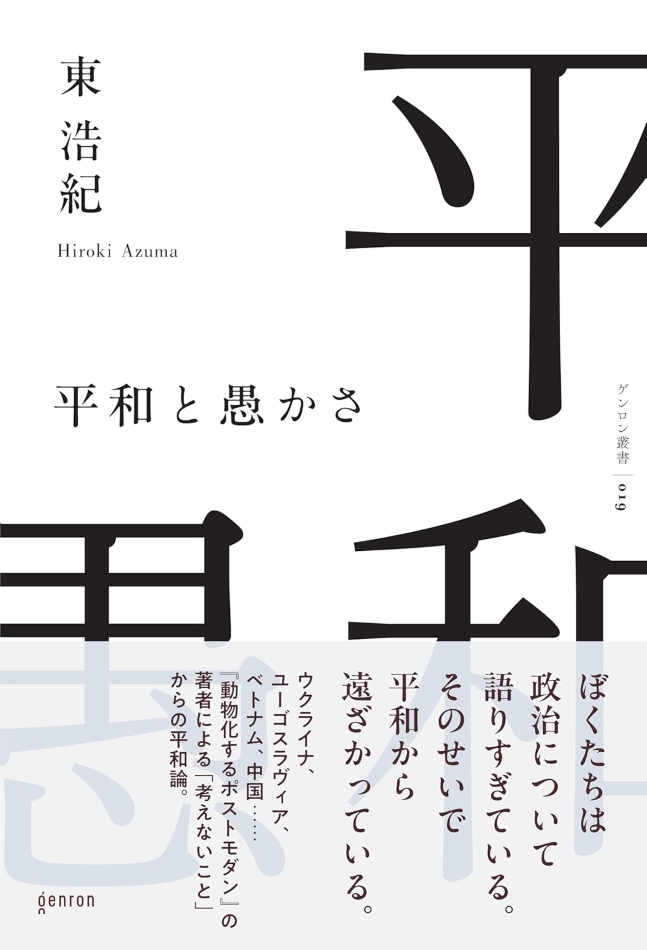
ロシアのウクライナ侵攻やイスラエルのガザ攻撃、そしてトランプ政権によるベネズエラへの武力介入、さらには習政権の台湾への威圧的な姿勢など、国際情勢はかつての大国によるむき出しの「力」が支配する状況に回帰したかのように思える。東浩紀『平和と愚かさ』(ゲンロン)は、そういった状況の中であえて「平和」を語ることの意味とその困難さに向き合った書籍である。本書は3部構成の全8章からなるが、戦争や平和が本書のキーワードである「愚かさ」の問題と直接結びつけて論じられるのは、第1部および第2部の第2・3章に限定される(その他の章では、それとゆるやかに連関させるかたちでウクライナ、ベトナム、アメリカ、東南アジアのリゾートなどの各地を訪れて得られた思索が展開される)。本稿では、この第1部と第2部で論じられた「愚かさ」の性質の違い、そして「考えないことについて考えるという、ほとんど自己矛盾のような作業」という問題に注目しつつ、この書物を読み解いてみたいと思う。
平和と「考えないこと」
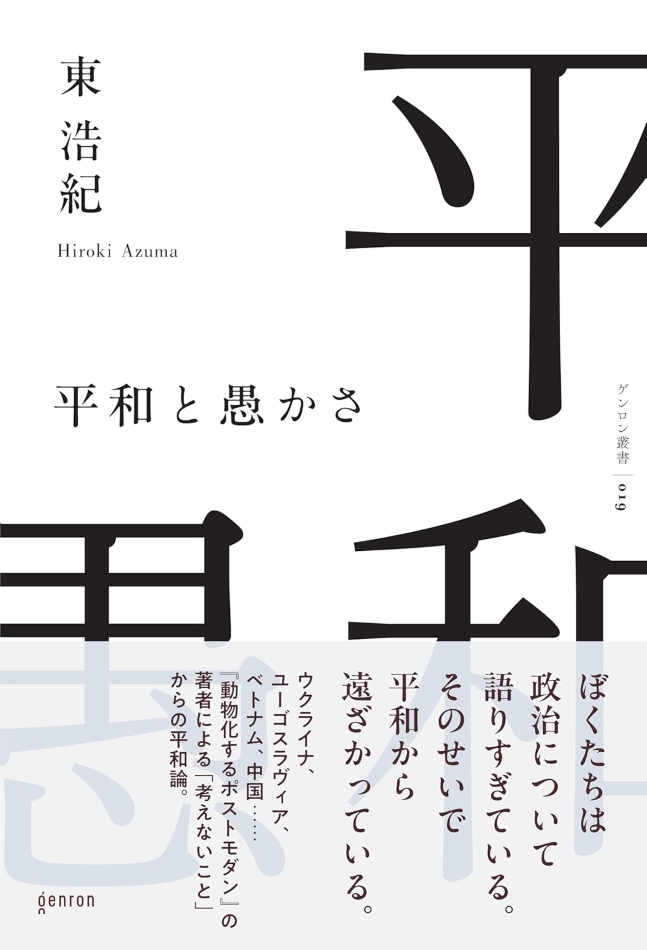
まず第1部(第1章)では、平和について「戦争について『考えないこと』が広く許されている状態」と定義したうえで、そのような「平和」を記憶し、維持することの困難さが、旧ユーゴスラビア圏の諸地域への旅行体験を通じて語られる。旧ユーゴではかつて「多民族の共生」を実現していたと考えられていたにもかかわらず、冷戦終結とともに民族間の紛争が激化し、現在は各民族が混じり合うことなくすみ分ける「隔離の平和」がかろうじて保たれてきた。本書の基調をなす第1部の議論で旧ユーゴが取り上げられるのは、「理念としての平和」を維持することの難しさを体現しているのがこの地域だからにほかならない。
特に強い印象を残すのは、旧ユーゴ圏を代表とする映画監督、エミール・クストリッツァをめぐる議論である。『アンダーグラウンド』をはじめとしたクストリッツァの作品は国際的に高い評価を受ける一方、彼自身は次第に反欧米的な姿勢を強め、近年では、ロシアのプーチン政権へのあからさまなコミットメントにより強い批判を浴びている。
『アンダーグラウンド』に代表される彼の作品は、過去において、多民族が憎みあわず、「何も考えない」で共生できていた時代の記憶を肯定する姿勢に基づいている。しかしその「共生の平和」への郷愁は、「何も考えない」ことが許されてきたマジョリティのものでしかない、という批判が以前よりなされていた。つまり、クストリッツァの作品はもともとこうした「共生の平和の下で抑圧されてきた人びと」の視点を欠く、という問題を抱えており、ついにその弱点を克服することができなかった。著者の言葉を借りるなら「クストリッツァは平和の記憶の訂正可能性そのものを否認して」(133頁)しまったのだ。
いずれにせよ、平和は「(厄介なことを)考えないこと」すなわち「愚かさ」と不可分に結びついている。だからこそ、その平和に対する告発、すなわち、「そんな平和はまやかしだ」という批判に耐える柔軟性を備えること、すなわち「訂正可能性に開かれている」必要がある。それがクストリッツァへの批判に仮託された、第1部の主要なメッセージである。
悪の愚かさ
次に第2部(第2・3章)の内容について簡単に紹介しよう。まず第2章では、旧日本陸軍731部隊の研究所が存在した中国黒竜江省ハルビン市郊外の平房、およびそこに建てられた731部隊罪証陳列館への訪問で感じた違和感がベースとなっている。すなわち、平房の罪障陳列館のように「政治的に正しい記憶」の継承を前面に出した展示ではなく、むしろ場当たり的で主体性のない、愚かさに満ちた加害のあり方を記憶する姿勢こそが必要なのではないか、というのが著者の主張だ。
では、その「愚かさに満ちた加害」とはどういうものか。続く3章では戦時中中国人に対する生体解剖にコミットし、戦後その罪を認め、「語り部」として証言する道を選んだ医師の証言をもとに、旧日本軍による「悪」の本質が考察される。それは実は、主体的に選択された(能動)ものでも、また命令によって強制された(受動)ものでもなく、「なんとなく」「何も考えずに」行われた、いわば「中動態」で記述されるべき行為だったのではないか。このような問題提起が、國分功一郎の著作(『中動態の世界』、医学書院)を援用する形で行われる。
ここでいう「中動態」とは、行為の局面において、意志―行為―責任の連関が成立していない状態を指す。旧日本軍の「悪」の本質がこのような「中動態」として理解できるような「愚かさ」と結びついているのなら、731罪障陳列館の展示がそうだったように、そこに加害者の能動的な意図を見出し、その責任を問い続けることこそが「悪」を防ぐ、という発想には限界がある。これが第2・3章における問題提起である。
二つの「愚かさ」と普遍性
さて、以上の第1部と第2部の議論は、「人間の本質的な愚かさ」への注目、という点において明らかに連続性を持っている。一方で、第1部で提示される「愚かさ」と第2部で論じられる「愚かさ」は決して同じものではない。前者は「愚かではあるが悪から切り離されている」状態であり、後者は「愚かさゆえに悪を成してしまう」状態なのだから、両者の間には大きな隔たりがある。にもかかわらず本書では、この二つの「愚かさ」を統合する十分な考察はなされていない。そこで、以下ではこの二つの「愚かさ」の違いが持つ意味について考えてみたい。
ここで注目したいのは、普遍性に関する二つの「愚かさ」の非対称性である。第1部における、平和の本質を「考えないこと」=愚かさと結びつけて理解する議論は、かなりの普遍性を備えたものだと言っていいだろう。しかし、「悪の愚かさ」の方はそのような普遍性を持っているのだろうか。ここで、丸山眞男が「超国家主義の論理と心理」で展開した議論(『超国家主義の論理と心理 他八篇』、岩波文庫)を想起してもよいかもしれない。丸山は、戦争時における個人の行為の意味づけを、絶対的な権威としての「天皇の意志」に判断をゆだねた戦前における日本人の精神構造を問題とし、戦後の戦犯裁判における強い主体意識を持つナチス幹部の姿勢と対照させた。そうした日本軍の「弱さ」による戦争犯罪の本質は、東が「悪の愚かさ」と呼んだものとそれほど大きな違いはないだろう。
この丸山の議論を敷衍するなら、731部隊に象徴される旧日本軍による「悪」は、当時の日本軍が近代的軍隊として特殊だった、ということに起因するはずだ。言い換えれば、かつての日本がコミットした「悪の愚かさ」は、近代国家の体裁をとりながら、十分近代化されていないという特殊な状況の下で生じたものであり、必ずしも普遍性を備えていない、ということになるだろう。
もちろん、日本の指導者の主体性のなさと、ナチスの幹部の主体性とを安易に対比させる丸山の議論は、その後多くの批判にさらされている。その一方で、そうした日本の特殊性と戦争での「悪」を切り離すべきではない、という議論は現在でも一定の影響力を持つ。例えば大杉重男はその近著『日本人の条件──東アジア専制主義批判』(書肆子午線)の中で、憲法第九条=日本人工学三原則を、特殊な近代国家の下で生きる日本人がふたたび悪に手を染めないように注意を払いつつ、一方で愚かさ=平和ボケを享受できるように国際社会によって設計された拘束具だ、という理解を示している。その背景には、天皇制という東アジア的専制主義体制の残存のゆえに、近代社会に必要な主体性を獲得できなかった「特殊さ」こそが、第二次世界大戦における日本軍の残虐行為を生み出した、という認識がある。
客的-裏方的二重体における愚かさの問題
もっとも、東自身はこのような日本特殊論にはコミットしていない。第2部の議論で、 ナチスの絶滅収容所、アメリカによる原爆投下、チェルノブイリでの原発事故が同じく「悪の愚かさ」の問題として論じられていることからもそれは明らかだ。一方で、大量殺戮のような「悪」は特殊な状況でしか起きえないものである以上、それはそうした状況を生んだ社会の「特殊」さ、すなわち普遍性の欠如と結びつけられて記憶されることは避けられないように思われる。一方の「平和ボケ」が、あまりにありふれた状態であるためにそれを記憶することが困難であるのとは対照的だ。
この二つの「愚かさ」の普遍性をめぐる問題は、平和論を考える上でも重要である。戦場において「悪の愚かさ」、すなわち主体性なく行われる大量殺戮が普遍的にみられるならば、戦争状態において「どちらが正義なのか」と問うことに本質的な意味はなく、即時停戦を説くことのほうに理があるはずだ。しかし、「悪の愚かさ」へのコミットメントが人びとが主体性を欠いた特殊な集団に限られるのならば、非戦や即時停戦を説く前に、理性や正義は紛争当事者のどちらにあるかを見極める議論が不可欠になる。なぜならより理性的で普遍性を備えた軍隊の下では「悪の愚かさ」は生じない可能性が高いからだ。
本書の中で「ぼくたちは中動態の論理のなかでいともたやすく巨大な悪に加担してしまう」(292頁)と記す東は、「悪の愚かさ」をむしろ普遍的なものとして捉えようとしているように見える。しかし、「悪の愚かさ」と「平和」がもし等しく普遍的なものなのであれば、悪を否定することそのものが困難になってしまうのではないか。本当にそれでよいのか。ここでは、「考えないことについて考えるという、ほとんど自己矛盾のような作業」をより広い文脈で論じている、本書の第8章「哲学とはなにか、あるいは客的-裏方的二重体について」にその回答のヒントを探ってみよう。
ここでいう客的-裏方二重体における「客」とは、イメージとしてはリゾート地やテーマパークに来ている観光客に近く、本書で繰り返し論じられる「平和ボケ」の状況と対応している。しかし、言うまでもないが現実の社会は「客」だけでは回らない。それを支える「裏方」、すなわちリゾート施設の管理者やスタッフの存在を不可欠とする。しかしその「裏方」も、休日には「何も考えない」客として別のリゾート施設などを訪れる。多くの人は、その二つの立場を往復しながら生活している。東は、このような現代社会の成り立ちをひとまず肯定したうえで、そこに真や善や美のような超越論的な理念が凋落した現代における自然科学と人文学との関係を読み込もうとする。
すなわち、自然科学は様々な事象やその成り立ちを解明し、それらを操作可能なものとする。その延長線上にひとびとが「何も考えない」客として生きていけるような具体的な仕組みを設計する、工学的な知が存在する。一方で、人文学は、そのように直接の役には立たないが、それが失われると人間の存在基盤が失われるような「幻想」を分析対象とする。東はこれらの学問をともに社会の「裏方」に見立て、それぞれ担当する業務が異なるのだと述べる。進化論の発展は、真や善といった超越論的な理念が、人間が進化の過程で獲得した幻想にすぎないことを明らかにした。しかし、そのことが科学的に解明されても、幻想にとらえられてしまう人間の厄介な本質は変わっていない。だからこそ人文学的な知には、人間の幻想の厄介さに向き合いそれを訂正していく、一種の啓蒙活動を担うという役割がある。そう東は主張する。
新たな平和論の構築に向けて
ここで話を先ほどの「平和ボケ」と「悪の愚かさ」における普遍性の問題に戻そう。評者は先ほど「悪の愚かさ」は、悪を成す社会の特殊さと結びつけられがちだ、と述べた。人間は平和のようなありふれた状態をなかなか記憶できないが、大量殺戮のような特殊な現象のことは何代にもわたって記憶し続けるという性質を持つ。言い換えれば「悪」が記憶され続けるためには、その存在は常に特殊さと結びつけられる必要がある。そしてその作業は、歴史学や丸山眞男が展開した政治哲学など、もっぱら人文学的な知が担ってきた。問題は、特に日本におけるそれらの議論が、悪の「特殊さ」を強調するために、しばしば欧米を物差しとした普遍的価値が想定されていた、という点だ。ここでの普遍的価値は、そのまま超越論的な理念、と読み替えてよいだろう。例えば、丸山の日本=超国家主義論は、西洋的社会で共有される超越論的な理念が日本には(萌芽はあったにせよ)不在である、という認識がなければ成り立たないものだ。
では上述のように、科学の進歩によってかつて信じられていた超越論的な理念が幻想であることが明らかになった以上、戦前の日本は天皇制を抱いた特殊な超国家体制だったから愚かな「悪」を成したのだ、という認識もつまるところは幻想であり、私たちはこれを捨てさるしかないのだろうか。
恐らく、東が言いたいことはそんな単純なものではないだろう。裏方=工学的な知が作り出す平和ボケの状態は、常に「それはまやかしだ」という異議申し立てによって訂正される可能性に開かれていなければならない。第1部での、平和の記憶という「幻想」に固執したクストリッツァへの批判を思い出してほしい。しかし、平和ボケにひたる客から見れば、「それはまやかしだ」という異議申し立ては端的に不快なものだ。だからこそ東は、人文学の役割を「まずは客の期待=幻想に耳を傾けたうえで、その幻想のほうを『訂正』しようと試みる」(472頁)ことに見出す。
そのうえで評者は、異議申し立てそのものを支えることもやはり、人文学的な知の重要な役割にほかならない、と付け加えたい。そのような異議申し立ては、大量殺戮に代表される「悪」を特殊なものと結び付け、その記憶を長く保持し続けようという信念――それを幻想と呼んでもよい――によって支えられている。そうである以上、丸山眞男に連なる「悪の愚かさ」を特殊なものとして認識する姿勢自体は、決して否定されるべきものではないはずだ。
同時に、ある社会を特殊/普遍と認識するその判断の軸は、常に問い直され、訂正され続けなければならないだろう。言い換えれば、人文学的な知は、「悪の愚かさ」を記憶し続ける際のよすがとなる理念自体を、常に訂正し続けることによってはじめて、平和ボケを支えるもう一つの裏方としての普遍性を獲得できるのではないだろうか。本書におさめられた各章の議論は、このように考えることで、一貫した骨太の思想として立ち現われてくるように思われる。
もちろん、以上の議論はあくまで評者による一つの解釈であって、本書の主張とは微妙にずれているかもしれない。そもそも、本書をはじめとした東の言論活動は、読み手による多様な解釈を許すものであり、だからこそ一部の反発や誤解にさらされてもいる。しかし少なくとも、厳しい世界情勢の下で人びとの心に響く平和論を展開するためには、国際社会で前提とされる「正義」のあり方とは別の次元で、戦時下における「愚かさ」とその意味を考えていく必要があるように思われる。本書が広い読者層を獲得し、こうした本質的な議論が高まるきっかけとなることを期待したい。
■書誌情報
『平和と愚かさ』
著者:東浩紀
価格:3,300円(税込)
発売日:2025年12月18日
出版社:ゲンロン























