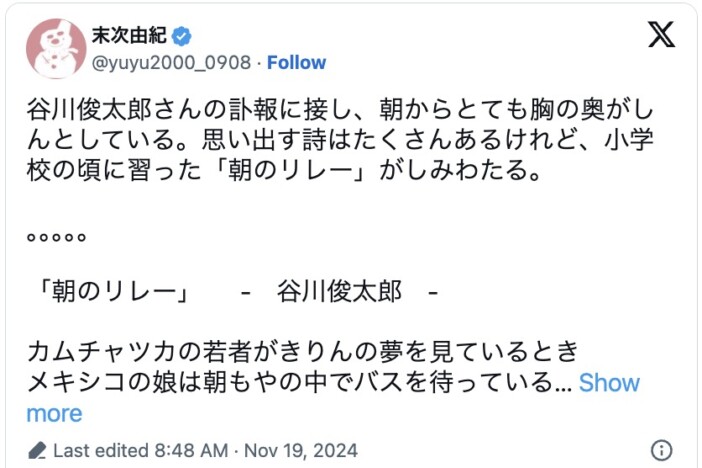谷川俊太郎は、なぜ詩を書き続けたのかーー最新詩集『ひとりでこの世に』で問いかけたこと

2024年11月13日、92歳で逝去した詩人・谷川俊太郎。遺作を含む最新詩集『ひとりでこの世に』には、主に65歳以降に発表した単行本未収録詩篇が収録されている。
対詩「いつかなじんだ靴を履いて」
遺作となった対詩「いつかなじんだ靴を履いて」は覚和歌子との共作で、谷川の逝去後「新潮」2025年1月号に掲載された。
覚和歌子は詩人・作詞家で、映画「千と千尋の神隠し」主題歌「いつも何度でも」の作詞で2001年レコード大賞金賞を受賞。谷川とは共著『対詩 2馬力』(ナナロク社、2017年)を刊行するなど、以前から親交がある。今回の企画は「覚さんが谷川さんと電話で話す中で、『谷川さんは筆を執るのが何となく億劫になっている』と感じ、持ちかけた」(読売新聞、2024年12月4日)という。
「対詩(たいし)」とは10行以内の短い詩を交互に送り合いながら紡がれるもので、1983年に刊行された『対詩』(谷川俊太郎・正津勉、書肆山田)がその始まりだ。谷川によれば「編集者が『何か新しいことやりませんか』と言ってきたときに、じゃあ二人で連詩をやったらどうなるだろう、みたいなことになって、対詩というのがはじまったんですよ」(谷川俊太郎・山田馨『ぼくはこうやって詩を書いてきた』ナナロク社、2010年)という。近年では歌人・木下龍也とともに、短歌×詩の対詩を同人誌として『これより先には入れません』(ナナロク社より2023年販売)にまとめている。
本書に収載された対詩では、2024年5月20日から、谷川が亡くなる約3週間前の10月20日まで、それぞれ12編ずつ送り合った。
この窓に五月を切り取って
お送りします
いちめんの薄荷畑を見下ろして
青空をうつっていく雲
名残りの鶯に 名を知らぬ鳥の初稽古
―― 覚和歌子
今過ぎ去ったものと
今もたらされたものの区別が
もうついていない
時は今 常に今 動き続ける不動の今
―― 谷川俊太郎
これは冒頭のやりとりだが、まず覚が五月の風景を描写し、それに対して谷川が「今」に焦点を当てた詩を返している。「今過ぎ去ったもの」は過去、「今もたらされたもの」は未来、つまり過去と未来の区別がもうついていない。しかし過去と未来が曖昧になる中でも、谷川は「時は今 常に今 動き続ける不動の今」と力強く言い切る。
この一連の対詩を掲載した「新潮」編集長の杉山達哉氏が「生死のあわいが曖昧になってつながっていく感覚を、平易な言葉でうたっている。死についての詩だが、どこか明るさがある」(読売新聞、2024年12月4日)と話すように、過去と未来が曖昧になる感覚は「生死のあわいが曖昧になってつながっていく感覚」ととらえることができるだろう。そして、死についての詩だが、「今」をうたう谷川の言葉にはどこか明るさがある。
どこまでもここしかなく
いつまでも今しかない
夢幻の生きる事実の
初夏の今日のきらめき
(「過去へ」より、『どこからか言葉が』朝日新聞出版、2021年)
筆者は、谷川のこの詩を思い出した。晩年、死の気配を徐々に感じながらも、しかしだからこそ「今、ここ」の生のきらめきが眩しい。そんな明るさを、谷川は常に見つめていたのかもしれない。
「ひとりでこの世に」
ひとりでこの世に来た
いつだったか覚えていない
びっくりした
訳がわからなかった
腹が立った
大声で泣き喚いてやった
疲れたので黙った
世界は何も言わない
口に来たものをなめた
指に触れたものを掴んだ九〇年がたった
また朝だ
結論はない
本書の表題作となった詩「ひとりでこの世に」は、「詩人会議」2023年1月号に掲載された。
なぜ「ひとりでこの世に来た」のか、「訳がわからなかった」。「九〇年がたった」が「結論はない」。つまり、なぜひとりでこの世に来たのか、90年間毎日を過ごしながらずっと問い続けているが結論はない、というのである。
このような、「この世」ではない別の場所からやってきたという表現は、谷川の過去の詩にもよく見られる。
そして私はいつか
どこかから来て
不意にこの芝生の上に立っていた
(「芝生」より、『夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった』青土社、1975年)
この詩について、詩人・茨木のり子は『詩のこころを読む』(岩波書店、1979年)の中で「『なんだか宇宙人が書いたような詩だ』と批評されたりします」と述べながら、
あの青い空の波の音が聞えるあたりに
何かとんでもないおとし物を
僕はしてきてしまつたらしい
(「かなしみ」より、『二十億光年の孤独』創元社、1952年)
を引いて、「『私はどうして今、ここにいるのだろう』『いったい何をやっているのだろう』『なんのために生まれてきたのだろう』 思い出せそうで、うまく思い出せない世界。両親がいたから生まれてきたのに間違いはないけれど、もう一つ別の、抽象的なルートへ思いを馳せる」「そんな問いの一つかもしれません」と述べている。
「ひとりでこの世に」も、そのような問いの一つと言えるだろう。谷川は「大声で泣き喚いて」「口に来たものをなめ」「指に触れたものを掴んだ」りしてもなお何も言わない世界で、90年間ずっと問いを繰り返して生きてきた。谷川にとって生きること、そして詩を書くことは、問い続けることに他ならなかったのである。
「ひとりで」というのも重要なポイントだ。人間は本質的に「ひとり」であるということ、つまり唯一無二の存在であるという意味での「孤独」であることを考えるとき、谷川の代表作「二十億光年の孤独」を考えずにはいられない。
二十億光年の孤独に
僕は思わずくしゃみをした
(「二十億光年の孤独」より、『二十億光年の孤独』創元社、1952年)
これは詩の最後の部分だが、批評家で詩人の若松英輔は「100分de名著 谷川俊太郎」(NHK出版、2025年)の中で次のように述べる。
「くしゃみ」は永遠とは違う「この世的」なものの象徴でもある。人は誰も二十億光年の孤独、つまり永遠の孤独――本源的に固有者である自覚――を内に抱えながら、日々、雑事にまみれつつ、「この世的」に生きている。それが人間なのではないか、と谷川は問いかけます。二十億光年の孤独だけを生きるのでも、くしゃみをしながら生きるだけでもない、私たちのなかで永遠と日常は並行しているのです。
「ひとりでこの世に」の中で書かれる、「大声で泣き喚いて」「口に来たものをなめ」「指に触れたものを掴んだ」なども赤ん坊にとって生理的な反応で、「くしゃみをする」ことと同義と言えるだろう。つまり「この世的」なものの象徴である。そして、そこから一行置いて「九〇年がたった」という。その空白の一行には、前文を受けた延長としての90年があったことを示唆している。「ひとり」の孤独を内に抱え、「問い」を繰り返しながら、「この世的」に生きてきた。どれかひとつを生きるのではなく、それらを並行しながら生きている、それこそが人間なのではないか。谷川はそう問いかけているのである。