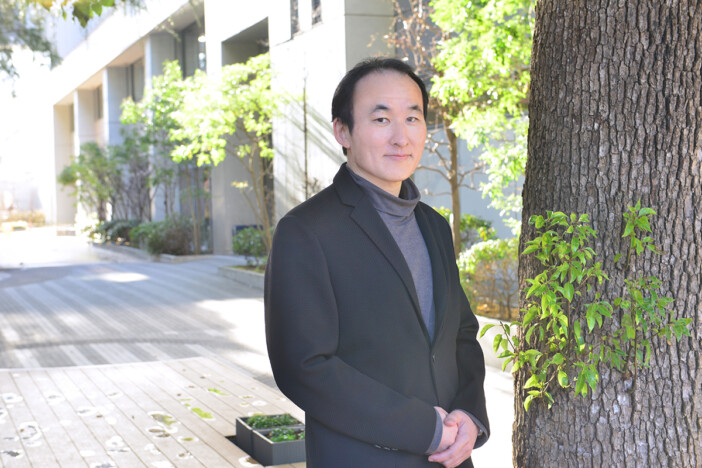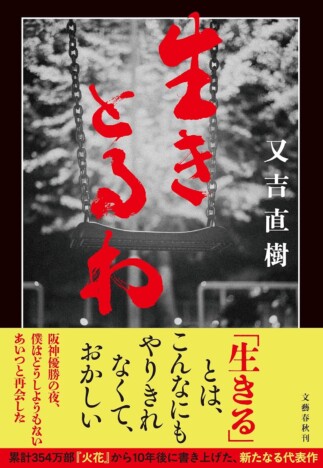夏川草介『エピクロスの処方箋』オリコン文芸書ランキング第1位に 〈神様のカルテ〉シリーズに続く代表作となるか?

以前このコーナーで取り上げた『白魔の檻』(東京創元社)の著者、山口未桜は現役の医師である。『白魔の檻』はクローズドサークルと化した病院内を舞台にした本格謎解きミステリだが、物語の諸所には地域医療の光景が織り込まれていた。最近では伊豆半島にある病院に勤務するようになった主人公を描く藤ノ木優の〈あしたの名医〉シリーズ(新潮文庫)が注目を集めるなど、地域医療という題材は医療小説の分野に深く根付いているものだと言えるだろう。
そうした地域医療の現実を描く医療小説のヒット作として真っ先に思い浮かぶのが、夏川草介の〈神様のカルテ〉シリーズ(小学館文庫)だ。同シリーズは地域医療の過酷な姿を捉えつつ、栗原一止というキャラクターの魅力で牽引するという稀有な医療小説だった。2025年9月第5週のオリコン文芸書ランキング第1位にランクインした『エピクロスの処方箋』(水鈴社)は、その夏川による京都の町中にある病院を舞台にした小説である。2023年に刊行された『スピノザの診察室』の続編で、主人公の“マチ先生”こと雄町哲郎はかつて大学病院で数々の難手術を経験し、将来を嘱望された医師だった。しかしシングルマザーだった妹が病没し、その一人息子である龍之介を引き取ることにした雄町は大学病院を辞め、原田病院という地域病院で内科医として勤務するようになる。
原田病院が抱える患者の多くは高齢者であり、なかには年単位で脳神経が委縮していくような難病を患っている者もいる。手術などによる治療が困難で、ひたすら患者に寄り添うことが求められる場面に雄町哲郎は幾度となく出くわす。
ただし著者は医療のシビアな現実を突きつけることを小説の主眼にはしていない。『スピノザの診察室』および『エピクロスの処方箋』で書かれるのは、医師がどのような哲学を自分の中に持って患者と向き合っていくのか、ということだ。雄町哲郎は常に「人にとって幸福とは何か」という問いを考え続ける人物である。タイトルにスピノザ、エピクロスという哲学者の名前が入っている通り、雄町はときに哲学の古典をひも解きながら人間にとって幸せと呼べる状態が何なのかを徹底的に考え、語ってみせる。医師の劇的な活躍によって困難な手術や治療法が施されるようなカタルシスとは違う、知性によって人間の心に深く分け入っていく姿に感銘を覚えるはずだ。
『スピノザの診察室』は2024年本屋大賞において第4位になり、同じく2024年には第12回京都本大賞を受賞している。(京都本大賞とは「過去1年間に発刊された京都府を舞台にした小説の中から、もっとも地元の人々に読んで欲しいと思う小説を決める賞」で、京都の書店や出版社などで構成される京都本大賞実行委員会が運営している)さらに映画化も決定しているとのことで、シリーズ作品として〈神様のカルテ〉と並ぶ著者の新たな代表作になりそうな予感がしている。