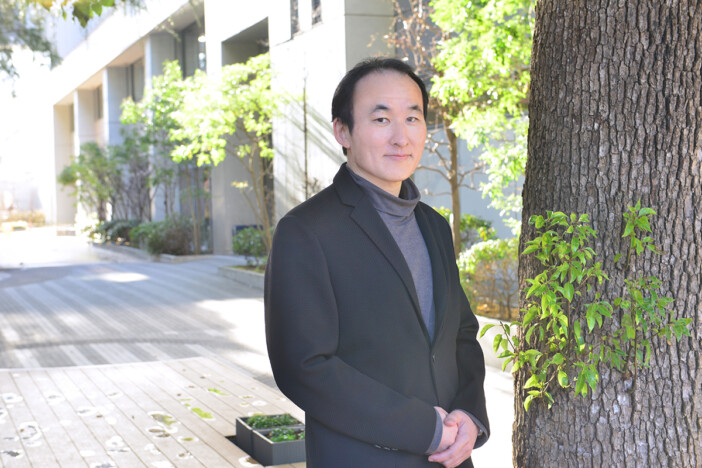整理しきれない感情を抱きながら前へーーカズオ・イシグロ『遠い山なみの光』が描こうとした人間のあり方
石川慶監督、広瀬すず主演の映画『遠い山なみの光 A Pale View of Hills』が9月5日に日本公開を迎える。同映画でエグゼクティブ・プロデューサーも務めたカズオ・イシグロによる同題の原作小説は、1982年に発表されたデビュー長編だ。現在と過去を行き来する小説であり、どちらの時期も決定的な出来事が起こってしまった後の日常をあつかっている。消すことのできない状況や条件の下におかれた登場人物が、それでも懸命に生きようとする。『日の名残り』(1989年)、『わたしを離さないで』(2005年)、『クララとお日さま』(2021年)など、後の作品にもみられるそのようなテーマに、イシグロは最初期からとり組んでいた。
1980年代はじめ、イギリスに暮らす悦子は、長女・景子を自殺で亡くしていた。姉の葬式に出なかった次女・ニキが悦子のいる実家を訪れ、滞在するところから物語は始まる。景子のことをニキと話すうちに悦子は、故郷の長崎にいた頃を思い出す。1950年代の長崎は、原爆投下による甚大な被害と日本の敗戦を経て復興に向かっていたものの、戦争の傷跡が多く残っていた。この小説は、過去の回想が大部分を占め、外枠と合間で現在を語る構成だ。そして、過去では原爆と敗戦、現在では長女の自殺という決定的な出来事が起きた後の登場人物の日常を見つめている。
過去パートの悦子には二郎という夫があり、子どもを身ごもっている状態である。一方、現在パートの悦子は、再婚したイギリス人の夫を亡くしており、ニキは彼との子だ。読んでいくと、過去パートで悦子のお腹のなかにいたのは、後に成長して自殺する景子だと察せられる。悦子の連れ子としてイギリスにきた景子は家族や環境になじめず、親元から離れた場所で首を吊ったのだった。
この経緯を理解すると、過去パート前半のある言葉が、悲しい未来を暗示していたように感じられる。うどん屋の女将の藤原が、悦子に話したことである。自分が墓参りにいくと、妊娠中の若い女性が夫ときているのに毎週会う。妊娠している人が死んだ人のことを考えるのはよくない。「もっと将来のことを考えなくちゃ」(ハヤカワepi文庫、小野寺健訳。以下の引用も同じ)と藤原は、妊娠中の悦子にいう。この時代だから、長崎の原爆か、徴兵されて戦地で死んだ身内が眠る墓に妊婦は通っているのかもしれない。それに対し、墓より将来を考えるべきだと主張するのだ。
藤原は、亡くなった身近な人間を供養する墓を将来と対立するものととらえている。つまり彼女は墓について、遺された人がそれまでの過去に区切りをつけるためのものとみなしているのではないか。ただ、うどん屋を切り盛りし、将来に心が向いているようにみえる藤原も墓参りを続けているわけで(だから妊婦と“毎週会う”)、過去を割り切れているのでもないらしい。そして、頻繁に墓参りをしたのでもない悦子が当時身ごもっていた景子が、後に自殺して将来を絶つのを読者は知っている。ゆえに悦子が藤原から聞かされた墓参りのエピソードには、なにか不吉なものを感じてしまう。この種の不吉さが。過去パートには複数ちりばめられている。例えば、土手の草むらを歩く悦子の足に落ちていた縄がからまるが、それは自殺した景子が首を吊った際の縄を連想させるのだ。
過去パートで悦子は、佐知子と万里子という母子と会う。シングルマザーの佐知子は、アメリカ人のフランクと交際しており、彼とアメリカへ渡ることに希望を抱いている。だが、悦子にはフランクが疑わしく感じられ、まだ幼い万里子が夜にどこかへ出かけていても捜そうとしないような佐知子への批判的な感情がある。悦子と佐知子は、表面的には友人関係であるものの、互いのあり方を本心から認めあっているわけではない。
また、義父の緒方がしばらく悦子と二郎の家に滞在する。緒方は戦前の思想を持ち続ける人物であり、共産主義だけでなく民主主義や男女平等といった戦後の価値観に否定的だ。自分が仕事の世話をしてやった息子と同世代の松田重夫から、緒方が職を失ったのは当然で終戦と同時に追放されるべきだったと雑誌で批判されたことに怒りをためこんでいる。そんな父をうとましく感じている二郎に比べ、悦子は緒方に好感を持っている。義父の方も息子より嫁に気やすく接しているようだ。だが、緒方がうどん屋の藤原に「洗濯機だのアメリカの洋服の話ばかりしている」近頃の若い女性への非難をいうなかで、悦子も同じだと口走る。新技術や外国文化をもてはやす新世代の感覚を嫌悪しているのだ。
駐留米兵が、日本人母子と本気で家族になるつもりがあるのかわからない。そんな相手に頼ろうとする佐知子の姿勢を否定的に受けとる悦子は、既婚者であり、もうじき子どもが生まれる立場だ。二人のなかでは、悦子の方が保守的にみえる。一方、戦前の価値観を引きずる緒方からすれば、義父にものわかりのよい態度をとっていたとしても、嫁は新世代だ。佐知子と悦子、緒方と悦子の対比は、そのようになる。
ところが『遠い山なみの光』は、1980年代の現在のイギリスから、1950年代の長崎を思い出す物語なのだ。幼い娘のいる佐知子とアメリカ人の交際を喜ばしく思っていなかった悦子は、二郎と離別し、景子を連れてイギリス人と再婚した。景子より先に死んだその夫は、日本に関する論説をいくつも書いていたが、日本文化の性格などわかっていなかったと悦子は考えている。また、景子が自殺した時に新聞をはじめイギリス人は、日本人には本能的な自殺願望があるという見方に固執したと彼女は思い返す。松田重夫が戦前的価値観の緒方を非難したように、イギリス人が自分たちより遅れていると思う日本人を批判したのである。また、悦子は、イギリス人の夫との間に生まれたニキと結婚観などでたびたび意見がくい違い、「昔の日本の習慣というのも、けっして悪くはなかったのよ」などともらす。緒方に対して新世代だった悦子は、ニキの前では旧世代であるしかない。
過去と現在で対比的なモチーフが複数共通しているのに、悦子の立場はかつてと逆になっている。悦子と景子のその後は、佐知子と万里子のありえたかもしれない将来だとも感じられる。そうした過去と現在のねじれを含んだつながりと断絶が、時代や国の違い、歳を重ねた人間の変化を感じさせて興味深い。現在の悦子は過去の悦子とは違っているのだし、肯定したい過去も否定したい過去もあるだろう。このため、過去に関する彼女の言葉、回想には、意図的な噓だけでなく、無意識のうちに生じる捏造や脱落が含まれる。こうした記憶の歪みや、語り手の信頼できなさを描いて人間のあり方の真実を深掘りする手法は、デビュー作以後のカズオ・イシグロ作品でも引き継がれていった。
『遠い山なみの光』には、悦子と緒方が長崎の平和公園を訪れ、平和祈念像を見る場面がある。座った巨像が両腕を上げており、「右手で原爆が落ちてきた空を指し、もう一方の手を左にのばしているその像は、悪の力をおさえている」というポーズにこめられた意味を悦子は知っている。だが、彼女には像の格好がぶざまに感じられ、原爆とその後の日々にどうも結びつかない。「遠くから見ると、まるで交通整理をしている警官の姿のようで、こっけいにさえ思えた」というのだ。祈念像は、原爆が落とされた過去と平和であるべき未来をポーズで示し、過去と未来をいわば整理しているのだが、現実を生きる人々には整理できないものがある。うどん屋の藤原が、墓に対してみせた矛盾する感情と似たものを、祈念像は想い起こさせる。『遠い山なみの光』は、二つの時代と場所を行き来することで、決定的なことが起きた後の人々の整理しきれない感情と、それでも前へ歩もうとする姿を描いている。
作者のカズオ・イシグロは、1954年に長崎で生まれたが、5歳半で両親とともにイギリスに移住した。イギリスで育ちアイデンティティを形成した彼は、出生地を舞台にした『遠い山なみの光』をはじめ一連の小説を英語で書いている。現在のイギリスと過去の日本というデビュー作の構成には、作者の実人生が反映されているのだろう。彼は当初、同作をイギリスを舞台に書き始めたが、間もなく戦後の日本に変更したのだという。ただ、イシグロの日本での記憶は、幼少期のわずかなものしかない。このため実際には、小津安二郎や成瀬巳喜男など1950年代の日本映画のイメージと記憶をまぜあわせ、『遠い山なみの光』における日本を作っていったそうだ。実体験や記憶に基づく日本ではなく仮構の日本であり、それゆえに特定の地域に縛られない普遍性を有しているといえる。過去の記憶を抱えて現在を生きる人々に広く響く小説である。