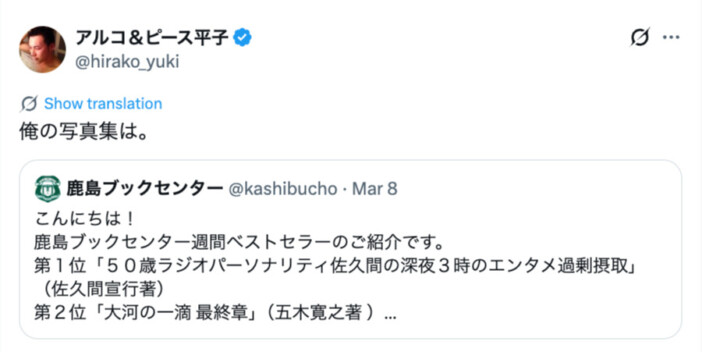『国宝』吉沢亮と横浜流星、最後の「演目」が小説とは異なる理由ーー映画がより面白くなる「原作」の読み方

喜久雄(吉沢亮)が”国宝"たる所以
喜久雄の背負うものは芸の業だけではない。父としての罪、そしてそれを背負いながら舞台に立ち続ける姿が、彼の“国宝”たる所以の一つでもあるのだ。
さらに、妻となる彰子(森七菜)も、原作を読むことでその存在感の大きさが際立ってくる。映画のラストでは姿が確認できなかった彰子だが、それは芸以外のすべてを捨てるという「悪魔の取り引き」で、喜久雄が空っぽになっていることを表現していたとの解釈もできる。しかし原作では、彼女は最後まで喜久雄を見守り続けており、そんな彰子は、恋人や妻というよりも、“芸の証人”という役割を担っているのだ。
また、原作にはもう一人重要人物が存在する。喜久雄の幼なじみであり、暴力団の世界に足を踏み入れていた徳次(下川恭平)である。映画では序盤に登場していたのみだったが、2歳上の兄貴分である徳次は喜久雄を支える付き人であり、最も信頼できる存在。無償の献身が物語に感動を与え、人間ドラマに厚みを持たせているのも原作小説の大きなポイントだ。
映画のクライマックスで俊介と喜久雄が共演する演目は「曽根崎心中」だが、原作で描かれる最後の舞台は「隅田川」である。この演目は、死んだ子どもを探してさまよう母を描いているが、原作の俊介も子どもを亡くし、両足も失った状態で登場する。その苦悩と芸に生きることへの執念が重ね合わされる演出だ。一方、映画では喜久雄と俊介の2人にフォーカスが当たっていることでアレンジが加えられていた。演目の選択一つとっても、そこに込められた意味の違いが、映画と小説の表現の奥行きを際立たせているのである。
映画『国宝』を観たあと、原作を手に取る。それは、スクリーンの外に広がるもう一つの舞台に足を踏み入れることでもある。吉田修一が見つめた“人間国宝”の裏側には、名前も光も持たない者たちの人生があった。そのすべてが一つの“芸”に収斂していくさまを、小説という静かな舞台でも味わってほしい。観ることで心を震わせ、読むことで魂を深くえぐる――この映画と原作の関係性こそが、まさに“国宝級”の芸術体験なのである。