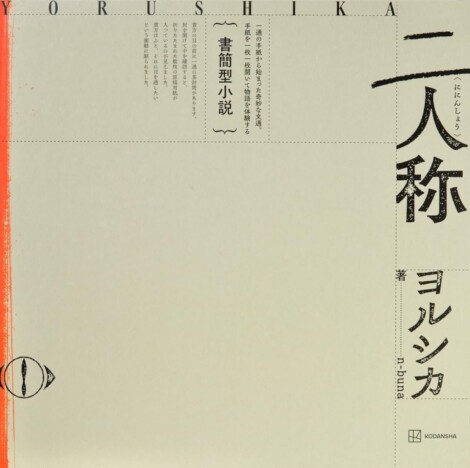【連載】福嶋亮大「メディアが人間である」 第10回:マルクスとAI

3、資本に吸収される機械=知能
ここで重要なのは、この労働を代替する機械が、一種の「知能」として現れたことである。労働のオートメーション化は、知能の意味そのものを刷新した。繰り返せば、知能とは社会的・歴史的な構築物である。19世紀の産業社会はまさに労働の分業=分解によって、知能を労働の生産性向上に適した形で再編成したと言えるだろう。私は先ほど「われわれの「知能」のあり方が、ITやAIに適合するようにあらかじめ調律されている」と述べたが、その調律は産業時代においてすでに始まっていたのだ。
この点についても、マルクスに示唆に富んだ記述がある。『資本論』に先立つノート(いわゆる『経済学批判要綱』)のなかで、マルクスは機関車、鉄道、電信、紡績機のような機械をあげて、それらが「人間の手で創造された、人間の頭脳の器官であり、対象化された知力」だと指摘した(※6)。つまり、機械はたんなる労働する装置ではなく思考する装置、つまり頭脳の代替物だというのだ。これは驚くべき指摘である――マルクスは鉄道や電信、紡績機をいわば原始的なAIと見なしたのだから。しかも、これはさほど突飛な考えでもない。現に、バベッジは解析機関を制御するのにパンチカードを用いたが、このアイディアは当時の自動織機(ジャガード織機)で使われていたテクノロジーの応用であった。バベッジによって、自動織機は計算機のプロトタイプとして再創造されたわけだ。
さらに、マルクスにとって、この≪知能を備えた機械≫は孤立したものではなく、社会的な諸関係のなかに組み込まれていた。マルクスは機械が「社会的頭脳」を形成すると見なし、その知やスキルの集積が資本のなかに「吸収」されると考えた(※7)。それは21世紀になって、いっそうはっきりした問題だと言えるだろう。実際、今日のプラットフォーム企業は、まさに「社会的頭脳」の結晶と呼ぶべきビッグデータをユーザーに生産させてはそれを貪欲に吸収し、莫大な富に成長させているのだから。これはショシャナ・ズボフの言った監視資本主義の問題だが(第8回参照)、マルクスはすでにそのことを直観的につかんでいた。
バベッジとマルクスの時代以降、知能は機械といっそう深く同化することによって、社会的な力や経済的な富を生み出してきた。そのプロセスにおいて、機械‐知能‐資本は相互浸透し、グーグルをはじめとするテックジャイアンツを触媒として、自らをどんどん膨れ上がらせていった。今日のAIの隆盛は、このような知の社会史の帰結である。パスクィネッリが言うように、AIによって知識はより一般化され、新しいデータセットやアルゴリズムへと疎外(外化)された。AIの普及は、集合的知識をシステマティックに機械化・資本化することに等しい(※8)。
※6 『マルクス資本論草稿集』(第二巻、資本論草稿集翻訳委員会訳、大月書店、1993年)492頁。
※7 同上、477頁。
※8 Pasquinelli, op.cit, pp.94, 100.なお、ここでは触れなかったが、パスクィネッリはAIの重要な源流としてニューラルネットワークに基づくコネクショニズムをあげて、ノーバート・ウィーナーやハイエクの思想を例にその社会思想史的分析を試みている。
4、労働を高密度化するAI=一般知性
オートメーション化が必ずしも労働者の自由につながらない理由も、以上の知の社会史から理解できるだろう。バベッジの分業論はあくまで労働の生産性の最適化をめざすものであり、働き方の改善を目的とするものではなかった。機械は確かに労働をオートメーション化し効率化するが、その一方で、現場の労働者はしばしば、多大な労力や注意力をたえず要求されることにもなる。
例えば、日々の連絡はインターネットによって確かに効率化された。手紙や電話しかなかった時代に比べると、コミュニケーションのコストは格段に下がった。それは一面では便利だし、歓迎すべきことである。しかし、その反面、休日だろうと夜中だろうとお構いなしにメールが届き、仕事時間と日常時間の境界があいまいになるという事態は、恐らく現代の労働者ならば誰しも経験があるはずだ。要するに、仕事の労力が減ることは、全体の労働量が減ることとイコールではない。
これは決して最近出てきた問題ではなく、むしろ19世紀の産業社会からずっと続く難題である。現に、マルクスは『資本論』で、法律によって労働日の短縮が求められるようになると、資本家は機械によって「同一時間により多くの労働を搾り取る」ようになると指摘している(※9)。つまり、一つ一つの作業は機械によってオートメーション化され、負担が軽減されるとしても、まさにそれによって、一人の労働者に要求される時間あたりの仕事の総量は増えてしまうのだ。労働時間が圧縮され、そこからより多くの労働が搾り出されること――マルクスはそのことを「労働の高密度化」と呼び、その例として、当時のイギリス人工場経営者の次の言葉を引用している。
機械装置の速度が目に見えて高まったために、労働者により大きな注意力と活動とが要求されるようになり、その結果、工場でおこなわれる労働は以前に比べてはるかに増えた。(※10)
このオートメーション化のもたらした弊害は、21世紀のデジタル化した労働環境でも引き継がれている。例えば、生成AIを使って文書を制作すれば、労苦やコストは確かに軽減されるだろう。しかし、そのぶん職場の人員は減らされ、残った少数の労働者がAIをパートナーとして、より過密化した仕事に駆り出されることになる。これはまさに「労働の高密度化」の典型である。知能が機械化・オートメーション化されるほど「労働者により大きな注意力と活動とが要求されるように」なる。なぜなら、オートメーション化はもともと労働者にとってではなく資本家にとっての恩恵だからである。
興味深いことに、マルクスは『経済学批判要綱』において、社会化・機械化された新しいタイプの知能に、英語でgeneral intellect(一般知性)という名を与え、それが社会生活をコントロールするようになると予想した(※11)。このルソーの「一般意志」を思わせなくもない概念は、具体的に展開されることもなく、後の『資本論』では消えてしまうのだが、イタリアのオペライズモの系譜をつぐ論者――パオロ・ヴィルノからパスクィネッリまで――が注目してきたように、この一般知性という即興的なアイディアに、現代の労働問題を考える鍵があるのは確かだろう。
実際、生成AIはまさに「一般知性」の名にふさわしい――それはまさに一般性を備えた知識を広く利用可能にして、労働や学習やビジネスを効率化するのだから。ビッグデータとアルゴリズムに根拠づけられたデジタル世界の生成(generation)は、レイ・カーツワイルの期待に反して、単独性(singularity)ではなく、むしろ一般性(generality)の領野を拡大している。問題なのは、この一般知性が、労働者をしばしば、余白のない緊密な仕事のゲットーに閉じ込めてしまうことである。この構造が解消されない限り、AIが人間を解放することはない。結局のところ、AIは古典的な労働問題を再び呼び戻したのだ。
※9 『資本論 第一巻(下)』89頁。
※10 同上、90頁。なお、マルクスが「これまでなされたあらゆる機械の発明によって、日々の労苦が軽減された人間が一人でもいたかどうかは疑問だ」というジョン・スチュアート・ミルの『経済学原理』の言葉を引用しつつ「ミルは「他人の労働によって生きているわけにはいかない人間のなかに一人でもいたかどうか……」と書くべきだった。機械が高等遊民の数を大幅に増やしたことは疑いえないからだ」とコメントしているのも興味深い(17頁)。
※11 Pasquinelli, op.cit, p.96.