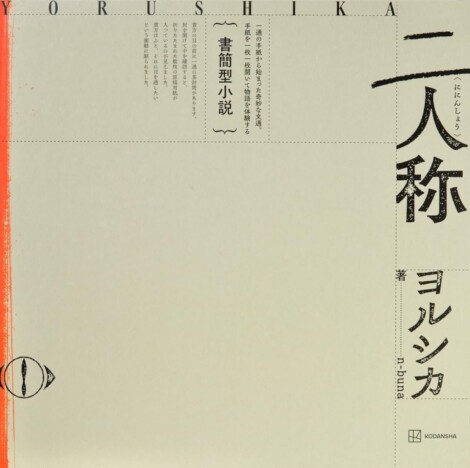【連載】福嶋亮大「メディアが人間である」 第6回:鏡の世紀――テクノ・ユートピアニズム再考

3、カウンターカルチャーとサイバーカルチャーの融合
現に、2010年代の後半以降は「鏡の世紀」をそのまま反射したような楽観的な情報社会のヴィジョンが、しきりに宣伝されるようになった。それが「ミラーワールド」である。ミラーワールドとはデジタル世界に構築された物理世界のツイン(双子)であり、ARやVRの技術がその世界への入口となる。そこでは、もはやスクリーンという媒介物も不要であり、人間はこの「鏡の国」にダイレクトに没入するとされる。ここ数年は、仮想性をいっそう強めたメタバースのほうがよく話題になるが、それもミラーワールドと同根である。
ケヴィン・ケリーは「インターネットの次に来るもの」の筆頭にミラーワールドを挙げて、近い将来、すべてのものがミラーワールドにデジタルツインをもつと断言している(※4)。ケリーによれば、惑星全体はいずれカメラで埋め尽くされ、物理空間のすべてがリアルタイムで逐一データ化され、相互に接続された上に検索可能になる。このミラーワールドが完成した暁には、歴史は「動詞」になり、時間をスクロールして世界を前のヴァージョンに戻すことも可能になるだろう……。
むろん、万物の流れをそのまま動詞的にデータ化するといっても、その莫大なデータがどこに保存され、誰に管理されるのか、天文学的なコストを誰が負担するのかは判然としない。百歩譲って完璧なデジタルツインが作成可能だとしても、このカメラだらけのハイパー監視社会がなぜ必要で望ましいのかも説明されない。ケリーはこの変化をほとんど自明の理のように語るが、それ自体が典型的なイデオロギーである。彼の語るデジタルツインは、世界の忠実なコピーではなく、そこから都合の良い面だけを取り出しているにすぎない――現に、戦争や疫病や飢餓はミラーワールドには存在しないことになっているし、プライバシーの問題も無視されているのだ。
それでも、21世紀のミラーワールドないしメタバースの構想が、デジタル社会の中核的な欲望に連なっていることは確かである。思想史をさかのぼれば、それが、半世紀前のカウンターカルチャーとサイバーカルチャーの融合にルーツをもつことが分かる。このテーマで優れた研究書を書いたフレッド・ターナーが指摘するように、1960年代後半にサンフランシスコのフラワーチルドレン(ヒッピー)が、シリコンバレーのテクノロジストと出会ったことが、ケヴィン・ケリー流の「デジタル・ユートピアニズム」の起源にある。
ケリーはもともと、スチュアート・ブランドの『ホール・アース・カタログ』に関与した後、『Wired』の初代編集長となった著述家である。ブランドはベトナム反戦やヒッピー、LSD等を含む1960年代後半のカウンターカルチャーの流れを汲みながら、ウィーナーのサイバネティクスやバックミンスター・フラーのダイマクション(「最小で最大を成す」の意)等を背骨として、物質的な現実を「情報システム」として理解するという新しい世界像を、スティーヴ・ジョブズをはじめとする若いアメリカ人の読者に注入した。カウンターカルチャーが導いた既成の文化への反発は、コンピュータとサイバネティクスという新たな受け皿を得て、巨大なサイバーカルチャーを結晶化させたのである。

ここで重要なのは、世界を情報システムと見なすサイバネティクス的な態度が、全体性にアクセスする道を開いたことである。ブランドの『ホール・アース・カタログ』はその名の通り、地球という全体システムをいわば神の視点から再配置する。『カタログ』の読者ひとりひとりは、既存の個別の文化に囚われることなく、相互に接続された情報システムを、活発なフィードバックを通じて自由に操作する能力を手にするだろう。このサイバネティクス的な世界像は、ケリーの編集する『Wired』にも受け継がれる。ケリーはvivisystem(機械が生物学的なパターンを模倣する段階に到ったシステム)のアイディア等を掲げながら、生物のように動く情報環境を理解し制御するデジタル社会のエリート像を描き出し、それが『Wired』のテクノリバタリアン的な思想の土壌となった(※5)。
そう考えると、ミラーワールドが偶発的に出てきた流行語ではなく、むしろこの半世紀のテクノ・ユートピアニズムの直系であることが分かる。人間を含めて森羅万象がデータ(情報)になり、歴史が「動詞」になり、それらすべてがアクセス可能で操作可能になるというケリーの万物理論は、ノーバート・ウィーナーとスチュアート・ブランド、サイバネティクスとカウンターカルチャー、テクノロジストとヒッピーの結婚の所産なのである。
※4 ケヴィン・ケリー「ARが生み出す次の巨大プラットフォーム」(松島倫明訳)『WIRED』(第33号、2019年)。
※5 Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism, The University of Chicago Press, 2006, pp.5, 92, 200, 236. 日本でも、ケリーの影響を受けた落合陽一が、自然そのものを計算機と見なす立場から「デジタルネイチャー」という標語を展開しているが、これもウィーナー以降のテクノ・ユートピアニズムの直系である。日本語で読めるスチュアート・ブランドの紹介としては、池田純一『ウェブ×ソーシャル×アメリカ』(講談社現代新書、2011年)が好著である。
4、カウンターカルチャーの反転
世界の鏡ないしツイン(双子)としてのもう一つの世界――それはカウンターカルチャーの想像力を吸収した情報社会論が、長く夢見てきたユートピアである。この「鏡の国」は現実と同じくらい豊かであり、かつ人間の自由を最大化する動的なデジタル世界として描かれる。このテクノ・ユートピアニズムは、われわれの生きる「鏡の世紀」に流布する物語やイメージに、すでに深く浸透している。
例えば、メタバースの業者は「なりたい自分になれる」ことをしきりに宣伝する。自己が一種の情報システムなのだとしたら、確かにその情報を操作し制御することによって、自己のイメージを任意に変更できるだろう。人間は物理的存在から情報的存在に変わることによって、あらゆる束縛から解放され、その自由を最大化することができる――この自己の「最適化」の物語は、まさにウィーナーの言う「人間の人間的な利用」の完成であるとともに、個人の解放をめざすカウンターカルチャーの理想の結実でもある。
加えて、日本ではカウンターカルチャーがオタクカルチャーと交差したことも重要である。情報テクノロジーの力で「なりたい自分になれる」というとき、日本ではその宣伝が往々にして、アニメや漫画やゲームのイメージでラッピングされるのだ。メタバースの論客がしばしばオタク系の美少女キャラになりすましたりするのも、その一例である(そこには当然、シリコンバレーの経営者や著述家にも共通するジェンダー的な偏向もある)。裏返せば、日本のオタク系のキャラ文化は、ITの宣伝に場を貸すことによって、いっそう栄えたとも言えるだろう。人間を操作可能な情報システムと見なすサイバネティクスの世界像は、日本ではオタク系の文化と共進化を遂げてきた。
ただ、2020年代から情報社会の歴史を振り返ったとき、これらの楽観的なストーリーに対しては大きな疑義が生じざるを得ない――それは、カウンターカルチャーに由来するテクノ・ユートピアニズムが、果たして人間の解放に寄与したのか、カウンターカルチャーの望んだ解放の理想はすでに反転してしまったのではないかという疑問である。現代のフィードバック・システムは「なりたい自分になれる」というメタバースの宣伝文句とは裏腹に、むしろ「人間の人間的な利用」には逆行しているのではないか。
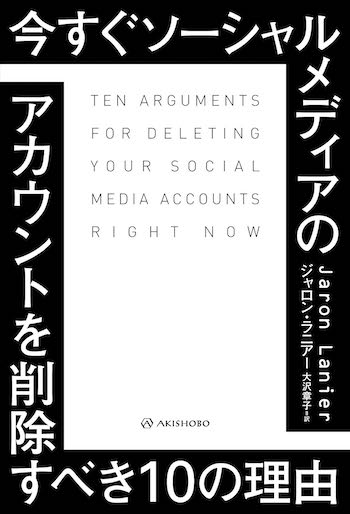
現に、VRという概念の創始者ジャロン・ラニアーが辛辣に述べるように、ソーシャルメディアの発生させるフィードバックは、人間を右にするのでも左にするのでもなく「下」にする。ソーシャルメディアは脳の報酬系に作用し、ユーザーをそれに依存させるが、その場合の報酬は本物の富ではなく「他者からの注目を集めること」に集中しているため、人間はたやすく下劣な行為に導かれる。そこは「ドーパミン主導の短期的なフィードバックループ」(フェイスブックの元幹部の言葉)が支配しているが、そのフィードバックを加速させるのはもっぱら負の感情である。ラニアーが言うように、それは「恐れや怒りなどの否定的感情は、肯定的感情よりずっと簡単に人の心に沸き上がり、より長く留まり続ける」からだ(※6)。
このような負の感情の上昇は、情報社会のダークサイドを拡大する。例えば「ソーシャルメディアには、オールドメディアでは報じられない真実がある」という類の主張は、カウンターカルチャーの反逆的な気分を引き継いでいる。このような反抗的なメッセージが広まりやすいのは、そこでまさに「恐れ」や「怒り」を核とするフィードバックループが組織されるからだ。しかし、ソーシャルメディアは今や少数のカウンターどころか、それ自体が巨大な権力の源泉となった。しかも、それは確かに人間の心の動きを鏡のように反射してはいるものの、そのデジタルの心は本来の心を極度に制限したものにすぎない。
ゆえに、ラニアーはまともなソーシャルメディアが出てくるまで、今のソーシャルメディアのアカウントを削除しようと呼びかけている。つまり、真に「キャンセル」されるべきなのは、不祥事をしでかした個々の悪人よりも、情報社会のダークサイドを拡大したソーシャルメディアそのものなのだ。しかし「アカウントを削除する」という誰にでもできる単純なボイコットこそが難しい――それはアルコールやニコチンへの依存症が解消しがたいのと同じである。要するに、情報社会はサイバネティクスとカウンターカルチャーの理想を「半ば」実現したことによって、かえってそれらから遠く離れてしまった。この苦境から抜け出る道については、本連載の後半で改めて問題にしたい。
※6 ジャロン・ラニアー『今すぐソーシャルメディアのアカウントを削除すべき10の理由』(大沢章子訳、亜紀書房、2019年)19、33、50頁。