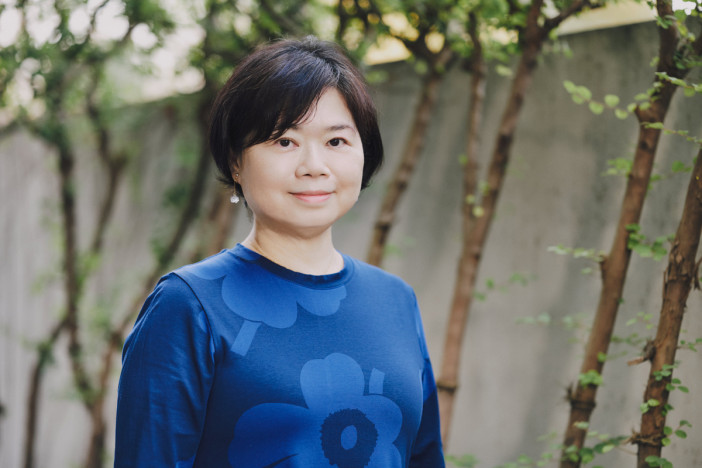初の単著で即重版! 『その謎を解いてはいけない』の新鋭作家・大滝瓶太にミステリ評論家、千街晶之が迫る

大滝瓶太による『その謎を解いてはいけない』(実業之日本社)が話題となっている。大滝瓶太は『青は藍より藍より青』で第1回阿波しらさぎ文学賞を受賞し小説家デビュー。これまでにさまざまな文芸媒体に作品を発表し、今回が初の単著である。
『その謎を解いてはいけない』は、探偵である暗黒院真実(あんこくいんまこと)と助手である女子高生の小鳥遊唯(たかなしゆい)によるバディもので、5話による短編の連作。「ミステリ」の形式をとっているが、ミステリの常識を覆すような内容で、書評家をはじめとした読書好きを中心に反響を巻き起こし、即重版の人気だ。
今回はそんな注目作家である大滝瓶太氏にインタビュー。『その謎を解いてはいけない』の創作についての話を中心に、作家としてのルーツや影響を受けた作品など、大滝氏の作家性にミステリ評論家であり書評家の千街晶之が迫る。
学者になろうと考えていた学生時代
――大滝さんが小説家になろうと思ったきっかけをお聞かせください。
大滝:もともと小説なんてまったく読まない人間でしたが、ふと気まぐれでいろいろと読み始めたのが大学院の修士課程2回生のときです。僕は熱力学とか統計力学とかそのあたりを専門にしていて、その方面で学者になろうと考えていたのですが、ちょうど迷いが出てきた時期でもありました。
このときに読んだ川上未映子さんの『先端で、さすわさされるわそらええわ』が衝撃で、「言葉」を絵の具のように色彩やアートみたいな感じの使い方をしてもいいっていうことを初めて知りました。でも読んだ当時、僕はこれを「小説」と思い込んでいたのですが、詩集だと知ったのはずっとあとのことでした。
ともあれ、川上未映子さんの作品がきっかけで、そんな言葉の使い方があるんだったら何か自分もやってみたいと小説を書き始めました。ただ、書けば書くほど片手間でできるものではないな……という認識が強くなり、「自分が納得できる次元で小説をやるためには小説で金がもらえないと時間があまりにも足らなさすぎる」と思うようになり、職業作家になろうとおもいました。それが大学院の博士課程2回生とか、そのあたりだったと思います。
トマス・ピンチョンやリチャード・パワーズなどの理系作家からの影響
ーー川上未映子さんの本からの影響で創作されるようになったということですが、その後の読書歴をお聞かせください。
大滝:主に現代文学でも文体や作品構造への批評性が高い作家を好んでいました。日本だと金井美恵子さんや保坂和志さんで、海外だとヌーヴォーロマンあたりに興味を持っていました。そのなかで特にピンとくるものがあったのがアメリカのポスト・モダン文学のトマス・ピンチョンとリチャード・パワーズなどの理系作家でした。
ピンチョンやパワーズは自然科学への理解が深い作家で、ともに膨大な知識・情報を縦横無尽に使った作風で知られています。脱線につぐ脱線、多岐にわたる話題が闇鍋みたいにごったがえし、小説が作家によって制御された構造でなく、雑多なものたちが勝手に構造をつくる──自然科学でいうところの「自己組織化」の結果生まれたものに感じます。そこにぼくは小説の自然現象的な側面を感じ、自身の創作でもっとも大きな影響を受けました。
ミステリ長編を書けないと小説家としてやっていけない
ーーこれまでの理系の知識がピンチョンらの小説と結びついたのですね。大滝さんは小説家のキャリアで見ると純文学からSF、そして今回初めてミステリへという風に、扱っているジャンルが変化していますが、どのようなきっかけがあったのでしょうか。
大滝:けっこう成り行きにまかせて、という感じでした。アマチュアで新人賞に応募していた時期、主に純文学五大文芸誌の賞に応募していて、そのとき作中で数学とか物理の話をよくしていました。でも箸にも棒にも……という感じで、そのころちょうど西崎憲さんの電子書籍レーベル「惑星と口笛ブックス」にお誘いいただき『コロニアルタイム』という短編集を出してもらいました。このときSFと言い張ってSFと縁ができた感じです。
ただ、本を作ってくれるあてもなく、短編でもなかなか文芸誌に掲載してもらえないことが続いていて、「大滝は小難しい小説だけでなく読者をおもしろがらせるエンタメも書ける」と対外的に示さないとこの仕事を続けていけないという危機感を持っていました。
そこで自分が心から楽しんで書けて、なおかつ読者数の多い場所で勝負できるものを……と考え、ミステリ長編を書けるようになろうと3年くらい前に勉強をはじめました。