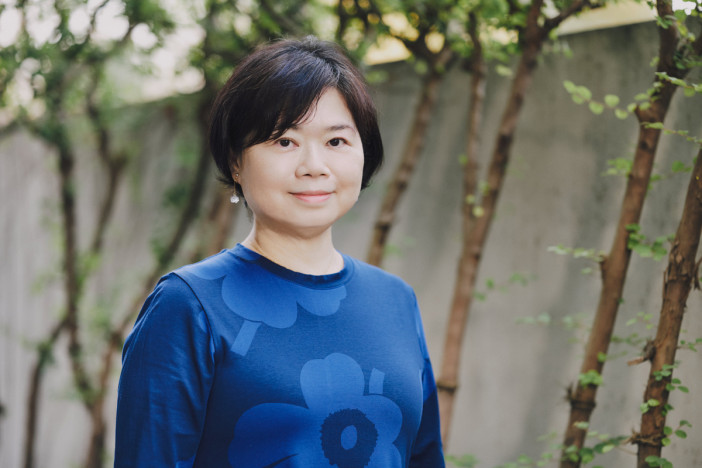初の単著で即重版! 『その謎を解いてはいけない』の新鋭作家・大滝瓶太にミステリ評論家、千街晶之が迫る

存在自体が不条理な「名探偵」の着想
ーーその両輪で満を持して書かれたのが『その謎を解いてはいけない』です。中二病の探偵・暗黒院真実(あんこくいんまこと)と助手でありツッコミ役であるオッドアイの女子高生・小鳥遊唯(たかなしゆい)によるバディものの作品です。この物語や主人公はどのように創られたのでしょうか。着想を教えてください。
大滝:僕はよくTwitterで大喜利をしているのですが、黒歴史探偵は「こんな探偵は嫌だ」の回答でした。ひらめいてから、「探偵の推理が推理じゃなくて〝惨劇〟だったらおもしろいのでは?」というアイデアにピンとくるものがありました。
それでちょっと先行作品を調べてみると、エラリー・クイーンが同じようなことをデビュー作『ローマ帽子の謎』でやっていたんです。それをエピグラフに完璧なパロディ小説を書いたら……と構想が固まっていった感じです。
黒歴史探偵は、漫画家・うすた京介の影響
ーー確かに本格ミステリでは、犯人を特定する際にさまざまな証拠を突きつける中で事件とは関係ないような秘密をみんなの前で暴いちゃうことがありますよね。
大滝:黒歴史探偵の着想はうすた京介さんの影響なんじゃないかと思っています。十代の頃にうすた京介さんの『すごいよ!マサルさん』『ピューっと吹く!ジャガー』の影響をとてつもなく受けていたので、「存在自体が不条理」な主人公や、誰にもわからないようなマニアックなネタの濫用、なんかイヤな視点をネチネチやるみたいなものが、自分の人格の根っこにまで影響している感じがします。暗黒院はいわば、存在自体が不条理なジャガーとなにをやってもダメすぎてハードなイジりを受けまくるハマーが悪魔合体したようなイメージで造詣しています。
自分の中二性を曝け出さないとフェアじゃない
ーー『その謎を解いてはいけない』を読んでいるとパロディをどれだけ入れられるかに力が入っている印象があります。執筆の際に意識されたことはありますか。
大滝:パロディやギャグが満載のミステリ小説をやるとなった時にどうしても他人をいじって笑いを取るっていう加害性が生じるので、これを令和の時代にやることに第一話書いた時点では自分自身でも懐疑的でした。イジり笑いをやるならそれを相対化する視点を入れる事が必須だと思いましたし、「黒歴史」と呼びたくなるような思い出したくもないあれこれと肯定的に付き合う物語にならなければ、書く価値がなかったと僕自身は考えています。
それゆえに「著者自身の中二性」を全ベットしないとフェアじゃないという気持ちは強くありました。そしてぼくにとってのいちばんの黒歴史は「小説を書いてしまったこと」です。僕は中高生のとき「小説を書いている奴は気持ち悪い」と思っていましたが、その「気持ち悪い」人間が他ならぬ今の僕です。10代の頃の僕が気持ち悪いと思っていた人間の思考、そして「文体」と呼ぶしかないその身体をきっちり書ききるのを念頭に置きました。
ーー小鳥遊唯をいわゆるワトソン役兼ツッコミ役、なおかつ実際に謎を解く役割にするというのは最初から考えていたのでしょうか。
大滝:はい、これには明確な着想がありました。大山誠一郎さんの『ワトソン力』というミステリを参考にしています。あれは「その場にいるだけで周りの人間の推理力が爆上がりする」という設定なのですが、それとは逆に「探偵がダメすぎて助手が探偵化する」としたら書けそうな気がしてきました。いわば「逆ワトソン力」です。その設定だと、普段から小鳥遊は暗黒院に対して細かいところまで過剰に突っ込むぐらいにしておくと物語が作りやりやすいと思ったんですね。
このキャラクター配置だとコメディになるのは必至ですので、どうやって笑いをとるかは書きながら調整しました。1話では「クセが強い黒歴史」で火力を出す方針にしましたが、これは一発芸的なところがあり、つまり「おもしろいボケを思いつかないと小説が死ぬ」という長く書くことを想定するとクオリティの安定に課題がありました。「笑い」の質と量を安定させるためには「ツッコミ」で小説の手綱をとっていく必要があり、当初暗黒院のボケ主導から小鳥遊のツッコミ主導の笑いに変えていきました。
これに応じて、ミステリ的な難易度のイメージも立てました。とりあえず最初は「あってないようなしょうもないレベル」にして、「事件と関係ないことばっかりに探偵の〝推理〟が無駄遣いされる」面を強調しようとしました。これはドラマ「33分探偵」を参考にしたのですが、事前に試し読みしてもらった同業者の意見を聞き、徐々に本格ミステリらしくしていく方針をとることにしました。そのほうが真面目な話も入れやすくなりますし。
「脱線」こそ小説の醍醐味
ーー本作の特色として話が脇道に逸れる面白さがありますが、これはある程度最初から意識しているのでしょうか、それとも書いているうちに自然とそうなったのでしょうか。
大滝:脱線こそ小説の醍醐味というか、脱線してナンボといいますか、特定の作品イメージに収束しない小説こそ傑作というイメージがぼくにはあります。「○○な小説を読んでいたはずなのに、気づいたらまったくちがう何かを読まされていた!」という小説にぼくは感動してしまいます。
今回の場合、ガッチガチの本格ミステリみたいな面構えをしていて、アクの強いキャラの意味不明なコントを嫌がらせみたいに延々と見させられたりするのにまずキレて欲しかった。漫画『すごいよ!マサルさん』や『ピューと吹く!ジャガー』、『あそびあそばせ』やアニメ『人造昆虫カブトボーグV×V』のイメージがベースにかなりあって、遠田志帆さんにどうしても装画をお願いしたかったのはそのためです。最初の打ち合わせの段階で希望の装幀・装画をチラッと聞かれたときからその意向を伝えていました。
ただ、それに終わることなくいきなりガチめのフィクション論がはじまったり、やたらネチョネチョした文学青年風の文体でエモい話をしたり、言葉による加害についての内省がはじまったりしますが、この小説によらず脱線に次ぐ脱線により要素還元的な読み方では太刀打ちできないようなものにしたいというのは常に念頭にあります。
自分の読書経験から、本筋をかき消すほどの脱線はそれまでの小説観をいったん捨てないと太刀打ちできないという認識があって、自作についてもそうであって欲しいと思っています。いわゆる「小説っぽさ」の外に出ていき、小説では使われてこなかった言葉や概念を持ち込み、作者すら手に負えない大きさを獲得するには「脱線」が不可欠だと思います。
ーー本作をミステリの視点から見ますと、第一話の「蛇怨館の殺人」ではいかにもな因習村の館ミステリの設定になっています。これは冒頭からミステリ読者を惹きつけるためのフックという意図があったのでしょうか。
大滝:それもあります。それと同時に、本格ミステリの装いにしておいて、いざ推理が始まったら全く関係のないことを言い出す探偵がいるという、読者をある意味で裏切るようなことも考えていたんですね。「この先ふつうのミステリの感覚とはちがうものがくるよ」という警告を与えたかったという意図もあります。ただ、お金を払って買ってくれたひとに対してその態度はどうなのか問題はありますが……。
点ではなく線で読んでもらえるように
ーーなるほど、それにこれはちょっと結末に関わることですが、最後の決着バトルでは本格的な推理というより物理でやっつけるという結末になっています。
大滝:最後は僕も迷ったところではありました。真面目にミステリらしく推理で終わらせるか、ここ一番の大きな笑いをしかけていくか。最後の最後まで悩みましたが、真面目にやって得られるものよりもミステリの枠の中で攻めて終わりたいかなと思いました。
ーー読者の反応はいかがですか?
大滝:予想通りといいますか、いざ蓋を開けるとすごいですよね……賛否の差が……じゃっかん「否」が多めなのが気になりますが、まぁそもそも悪意をもって嫌がらせみたいに謎のコントを延々と続けているので当然ですよね。ただ、今回は盛大にスベることを覚悟してのこのネタでしたので、ウケるひとにはウケてて本当によかったなと。他ジャンルの作家が無難でキレイなミステリをやっても「まぁがんばったよね」くらいの評価にしかならないと思うので、むしろこれくらいやってちょうどよかったかもな、と思います。
仕事として考えると、現時点の評価はこれはこれとして、今後どういう作家性を示していくか、これまでやってきたこともふくめて「点ではなく線で読んでもらえる」ように、一作一作軸をしっかり持ちながら取り組んでいくのが大事だと考えています。
ーーこれまで執筆した作品と『その謎を解いてはいけない』に共通するものとはなんでしょうか。
大滝:小説を書くって、物語をつくる以上に「この作品でしかなしえない文体をつくる」ということだと思っています。でも「文体」って非常にあいまいでいい加減な概念なんですけど、あえて言えば「最終にできあがったテクストの特性」であり、小説を書く前から存在していたものじゃなく、できあがった文章にたいして事後的に与えられるものだと考えています。
それはよく言われる「物語が文体を選ぶ」みたいな綺麗で耳障りのいい話なんかじゃなくて、ある問題を考えるなかでしかこの世に存在できなかった謎の塊であり、読者にどう読んでもらいたいとかどう演出したいとか、そういう上っ面の話じゃない。文章がこのかたちでしか存在できなかったという唯一性にこだわることが小説を書くいちばんの楽しみなので、それはこれまでのものと一貫しているという感触があります。「小説っぽさ」の外に出るような作品を書き続けられればと思います。