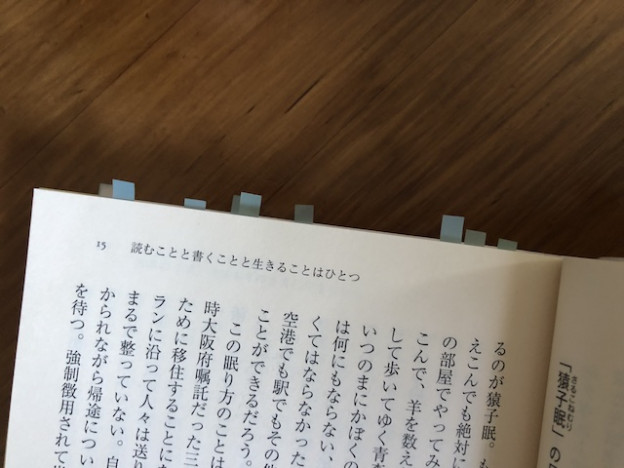管啓次郎「旅と読書は同じ形をしている」エッセイ『本は読めないものだから心配するな』への思い

本は決して読み終えることがない
――『本は読めないものだから心配するな』は、ページの左上にその見開きの中の一節が書かれていますね。
管:これはシームレスにつながっていく本にしたいと思って考えた工夫です。章ごとにタイトルのあるいくつかの文章が並んでいるという(一般的な)形式をやめて、全部で一冊なんだけど入り口はいたるところにあるような本にしたかった。
それなら、見開きからセンテンスを抜き出して並べておくのがわかりやすい。こうすると、ぱらぱら見た時に「こういうことが書いてあるのか」とそのページから入れるでしょう。撒き餌みたいなものですね(笑)。
紙の本というのは、どのページから開いてどこから読んでもいいという究極のランダムアクセスを体現しています。紙の本を模倣する電子の本ではできない。特に検索をしてヒットしたページだけを読むなんて、それでは何も新しい発見はないでしょう。ぱっと開いた時に思いがけない何かがあって、それがまたぱっと開いた別のところとつながる。それは脳のシナプスのつながり方そのもので、そうやって知識は構築され、経験が定着していくわけだから。
――管さんが学生に向けて書いたエッセイ「本のエクトプラズム」(管研究室発行のジン『本につれられて』収録)でも、具体的な読み方の一例を紹介していました。
“これらの本は、通読はしない。あっちを二行、こっちを三行と、拾い読みをして、何か新しい知識を得たら、それで満足。かける時間は一冊あたり十分でもいい。気が向けば三十分。それで得た情報のかけらは心のどこかに転がしておけば、やがて勝手につながってくるものだ。それでいい。(管啓次郎「本のエクトプラズム」)”
管:ある文脈を作って読まなきゃいけないし、その文脈は自分が生きることと直接重なっていないとどうしても身につかない。
『本は読めないものだから心配するな』の帯には、「読書の実用論」と書かれています。これは僕がエッセイで使った言葉ですが、実用論とはどういうことかを考えてほしい。いわゆるハウツー的なものとはまったく違って、読書そのものが生きることの根本にあって、われわれを実際に動かしているんだということですね。
本は冊という単位で考えてはいけない。それと同時に伝えたいのが、一冊の本は決して読み終えることがないということです。どの本を読んでも、「読み尽くした」と言えるほどは読んでいない。著者自身ですらわからないまま書いていることがいっぱいあって、著者も読み尽くしてはいないわけです。だとしたら、この一冊の本とは一体なんなのか。誰も読み尽くしていない、だけどこういうものとしてある。人間は本をページ数のあるかたちを持ったものとして考えるけど、実はそれはわれわれが考えているよりはるかに大きな存在で、一冊すら絶対に読み終えることはない。一度読みはじめたらずっと続くんです。
旅は常にそこにある
――管さんはさまざまな土地を旅していて、本にもその描写がたくさん出てきます。あらためて旅の魅力とは?
管:旅は意義や魅力を語る以前に、常にそこにあるものです。人間は一人ではなにも知らないし、なにも考えていないし、なにも新しいものを生み出す力はない。それが真実です。常にまわりのものを求めていないといけない。
本に対する狩猟採集の態度とも通じますが、旅はとにかく一瞬ごとが発見に満ちています。地形や気象みたいな自然の世界も、樹木も動物も、人間も全部違っていて、全面的に発見の連続。自分をそれにさらすことで何かが残るんだけど、何が残るかは終わってみなければわからない。それが面白いから旅をするんでしょうね。
そして本が「冊」という単位で語れないように、旅も一回ごとのものではないんですよ。「今度ちょっと台湾に4泊で行ってくるんですよ」と仮に言ってみることはできるけど、それ自体に意味はありません。ヘミングウェイに「何を見ても何かを思いだす」という短編がありますが、これはある意味、究極の真実なんですよ。何かを見ると、どこかへ行くと、必ず別の何かを思い出す。要するに人間って、本当は多分、今ここにいることはできないんです。今ここにいるつもりでも、そこには他の時間が流れているし、別の場所がつながっているし、よそのことを考えているわけだから。
そのつながりは言葉によって構成されます。人間の心が言葉と、見たものの映像的なイメージの記憶でできているとしたら、旅行記は書く書かないに関係なく、誰でも実践しているわけです。そしてその人が生まれてから死ぬまでが一つのユニットであり、区分けして細かく見ていっても便宜的な意味しかない。ある人にとっての本が広がりのある一冊であるのと同様に、生きることはずっと旅であるという考えに行き着くのではないでしょうか。
――読書と旅は近い存在だと言えますね。
管:7月に閉館した岩波ホールの最終上映作品だった『歩いて見た世界 ブルース・チャトウィンの足跡』という映画があります。ブルース・チャトウィンは『パタゴニア』などを書いた作家であり旅人。本作はそのチャトウィンが亡くなって30年が経ってから、彼の親友だった映画監督のヴェルナー・ヘルツォークがその足跡をたどりながら作ったドキュメンタリーです。パンフレットなどにも書いたのですが、これは僕にとってものすごく重要な作品です。チャトウィンとヘルツォークにとっての「旅」とはどういうものだったかがはっきりと語られているし、彼らのやってきたことは20世紀の旅人の極限の部分を示していると思います。
彼らは旅人であると同時にものすごい読書家なんですよね。それから世界中の写真を撮影している石川直樹くんもすごい読書家です。かれらの例を考えるだけで、旅行と読書には本質的な関係があると言わざるを得ないでしょう。というか、二つは同じ形をしている。同じモードで構成されているとしか言いようがないのではないでしょうか。