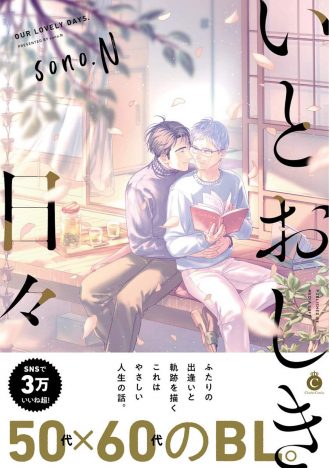大ヒットBL作品『ポルノグラファー』はなぜ三部作となったか? 過去と未来を描く必然性

2018年、FOD史上最速で100万回再生を突破したBL実写ドラマがある。官能小説家と口述筆記を依頼された大学生の恋愛を描いた『ポルノグラファー』だ。その人気から過去編『ポルノグラファー ~インディゴの気分~』も製作され、2021年2月には続編であり完結編となる『劇場版ポルノグラファー~プレイバック~』の上映が全国の映画館で始まった。
原作は丸木戸マキの『ポルノグラファー』『インディゴの気分』『續・ポルノグラファー プレイバック』のシリーズ三部作。
BL漫画は人気作になるとしばしば、スピンオフや続編が描かれる。ただ1作目の終わり方に“作者の美学”が感じられるのなら、人気だからという理由で続けることに疑問を抱く読者もいるだろう。ただ同作に関しては過去も未来も描く必要があったと、シリーズを読んで実感できるのだ。
(以下、ネタバレあり)
物語は自転車と歩行者の追突事故から始まる。自転車に乗っていたのは金欠大学生・久住春彦(くずみ はるひこ)。そして自転車との衝突で右手を負傷し、1カ月半の療養が必要となった人物が木島理生 (きじま りお)だ。とても損害賠償ができるとは思えない久住に木島は、「治療費の代わりに自分の小説の口述筆記をしないか」と提案するところから始まる。
ハッピーエンドを“遠回し”に描く美学
『ポルノグラファー』のラストは、“遠回し”なハッピーエンドだと思う。木島は作中でスランプに陥っていたのだが、そんな彼の“書く理由”になったのが久住だ。書けない小説家にとってはこれ以上ないハッピーエンドだが、ふたりはその瞬間その幸せを離れた場所で噛みしめている。
恋愛作品でハッピーエンドと言えば、「想いが通じ合う」「未来でも共にいることを選ぶ」といった目に見えてわかりやすいものが定石だろう。また世間的にはあまりよろしくない結末ではあるものの、物語の当事者であるふたりは幸せそうに見える“メリーバッドエンド”をハッピーエンドとして捉える人もいるかもしれない。
同作の場合、ふたりの想いは通じ合っている。もちろん世の中も不幸にはなっていない。ただふたりは一緒にいないのだ。木島が書いた本と久住が送った手紙を別々の場所で読んでいる様子からは、ふたりがその後どういう選択をとったのかがはっきりとは見えてこない。この“先の展開が読者の想像に委ねられてる”部分に、原作者丸木戸マキ氏の“ハッピーエンドは読み手の心の中で完成させる”という美学が感じられた。この“ハッピーエンドの型にはまっていない”ラストが、1作目『ポルノグラファー』の大きな魅力だったと思う。
木島理生を知るための過去編

読者にラストを委ねるという大胆な美学を感じさせてくれた『ポルノグラファー』。ただ木島の過去を描く『インディゴの気分』を読むと、『ポルノグラファー』はシリーズでなければなかったと感じざるをえなかった。
『インディゴの気分』は、1作目で「このふたり、絶対何かあったな」と思わせてきた悪友・城戸(きど)の目線で、木島の過去が語られる。かつて大学の同期で同じゼミに所属していた木島と城戸は、同作で同居人兼編集と作家という関係になる。城戸はアングラな作品を扱う出版社の編集者で、純文学で停滞し金に困っていた木島を官能小説作家の道へと引きこんだ張本人だ。
1作目で木島は息を吐くように嘘をつき、感情も簡単には読めない“食えない人間”として描かれている。その片鱗は過去編の同作でも見え、久住と同じく城戸も木島にそれはもう振り回されていた。この木島の突飛な言動は創作者、小説家ならではの才能、もしくはそれと表裏一体の変態性からくるものだと捉えられていたように思う。実際に城戸は、木島の才能に猛烈な憧れと嫉妬を抱いていた。
ただ木島は1作目で、久住との関係に変化が起こる中で誰もが共感する部分を持つ“凡人”なのではないかいう部分を垣間見せていた。そんな凡人がなぜ嘘にまみれ、感情を表に出さない人間になったのかが、『インディゴの気分』で明らかになる。
まず木島は、実家との折り合いが悪い。父に作家になることを反対され、名声を得ても認められることのないまま死別している。純文学で停滞した理由も、担当編集との文学性の違いだった。おそらくこれらの描写だけでは、単にプライドの高い作家にしか見えないだろう。
ただ彼は自分の作品に、なにより自分が書き続けることを信じてくれる人がいることに生きる意味を見い出す人間だと感じた。その証拠に城戸の「書き続けてほしい」という言葉をきっかけに、最初は断った官能小説執筆の提案にのるのだ。また大御所官能小説家の遺作を取るために弟子になってほしいという城戸の嘆願の際も、「お前だけが頼りだ」という言葉が決め手となっている。振り返ってみれば1作目でも、久住が官能小説とともに純文学作品を借りたりほぼ全作品を読破したと言ったりした時に、木島はハッとした表情を見せていた。
木島もきっと、誰もが心に抱いている「自分を見てほしい、必要としてほしい」という気持ちを持っている、自分に自信のない人物だ。ただ「この感情は心の奥底にしまっておかなければ」というプライドがあるため、表向きは飄々とした天才というアンバランスな状態になっているのだと思う。