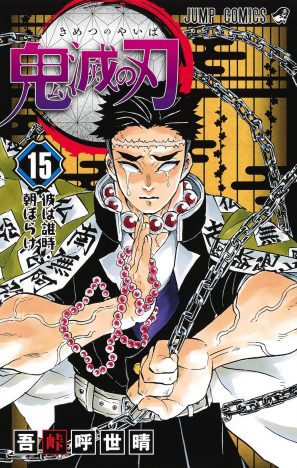『鬼滅の刃』は「マスクの時代」を先取りしていた? 評論家3名が語り合う、コロナ禍における作品の評価

予想外だった大ヒット

成馬:僕はアニメから入って、単行本を読んで、最後にリアルタイムの連載を追うようになったのですが、連載当初はどのような印象でしたか?
島田:漫画編集者としては、ちょっと戸惑っていた部分もあります。ご存じのように本作は、すごくスロースタートな作品で、ほぼ1巻まるごと炭治郎が剣士として独り立ちするまでの描写に費やしていますよね。普通の週刊連載の漫画なら、2話目で鬼殺隊に入隊するぐらいのスピード感が求められていると思うのですが、『鬼滅の刃』はそこに至るまでをすごく丁寧に描いていた。一方で、いざ炭治郎が鬼殺隊に入ってからは怒涛の勢いで、物語の展開がすごく早くなる。最後の無限城の戦いなんて、いきなり始まりましたし、しかも同時進行でいろんな戦いが描かれていくから、ついていくのも大変で(笑)。無限城での戦いは、その後の無惨との死闘も含めて、たった一晩の話なんですよね。本来、『週刊少年ジャンプ』は人気がなかったら10週で打ち切られる世界だと思うのですが、そういう背景を考えても、この物語全体を貫く時間感覚は、なかなか興味深いものがありました。特に、あまりアンケートの結果を意識していない序盤の丁寧な作りは、『ジャンプ』の漫画の新しいかたちを提示したとさえ言えるかもしれません。
倉本:『ワンピース』の場合は〇〇編というのがたくさんある一方で、構造的にいえばすでに完成されたプロットの繰り返しになっているため、途中から入ってもなんとなくあの世界を共有できる。でも、『鬼滅の刃』はキャラクターの関係性とかもストーリーの進行上どんどん変わっていくから、なかなかそうもいかないんですよね。
成馬:初期から読んでいた読者として、ヒットしたときはどう思いましたか? 近年稀に見るような異常なヒットだったと思いますが。
倉本:単純にびっくりしました。もちろん、アニメのクオリティが高かったとか、サブスクでアニメを観る環境が一般化しつつあるとか、ヒットの理由は複合的だと思うので一概には言えません。ただ、その中で、私がすごく現代的だなと思ったのは、今の視聴者や読者はあまりネタバレを気にしないというか、レビューで高評価だったのをしっかり確認してから鑑賞する人が多いんだなということ。アニメが高評価で、そのレビューを見た人が単行本を買ったりしている。ネタバレよりも失敗したくないということのほうが先にきているのが、今の時代の嗜好性なのかもしれません。
島田:実際、なんであそこまで売れたのか、おそらく集英社もすべてを把握できているわけではないと思います。19巻を買おうとしたとき、どこの書店でも売り切れていてかなり探しましたけど、それはつまり、版元も初刷りの部数が読めていなかったということですよね。さすがに20巻以降は、初版部数がニュースになるくらい刷っていますので、普通に買えますが。余談ですが、単行本がどこの書店にもなくて探しまくったのって、個人的には『デトロイト・メタル・シティ』の1巻以来でしたよ。あの頃、書店をさまよう「DMC難民」なる言葉まで生まれました(笑)。
倉本:私自身が連載当初から読んでいて感じたのは、けっこう読む人を選ぶ絵柄だろうな、ということ。当時の『ジャンプ』って、例えば『食戟のソーマ』が人気だったみたいに、デジタル作画の魅力が浸透しつつある時期だったと思うんですが、ああいう端正でつるんとした印象と違って、吾峠先生の場合は描線のクセがあきらかに強いというか、全体的にどことなくザラついたタッチで、ノイズが多い印象だったんです。登場人物も人の話を聞かないタイプばかりだし(笑)。一方で、だからこそ代替不可能な漫画だとも思いました。
成馬:おそらく編集部も、『ワンピース』や『NARUTO』や『僕のヒーローアカデミア』に続くような王道のヒット作にしようとは思っていなかったですよね。どちらかというと、『ジョジョの奇妙な冒険』や『魔人探偵脳噛ネウロ』の立ち位置というか、『ジャンプ』におけるカルト作品枠を狙っていたと思うんですよね。個人的には完成度の高い『約束のネバーランド』の方が、『ジャンプ』の新しい王道になるんじゃないかと思っていたので、『鬼滅の刃』の人気がどんどん盛り上がっていったときは、戸惑いがありました。
島田:作品として完璧じゃないからこその危うさが、ヒットすることによってむしろ魅力に転じていった部分はあるかもしれませんね。
「マスクの時代」を先取りしていた?

倉本:禰豆子のキャラクターデザインも、幅広い層のファンを虜にしたポイントなのかなと思います。子どもたちもみんな禰豆子のコスプレをしたがります。これまでに眼帯ヒロインはたくさんいたけれど、竹筒の口輪をかまされている和装の少女の姿は圧倒的に新しかった。
成馬:奇しくもコロナ禍による「マスクの時代」を先取りしていたかのようですよね。無惨と戦う場面はコロナ禍に向かっていく時期だったため、鬼殺隊の姿と医療従事者の方々の姿が重なって見えて、コロナ禍の比喩のように読んでいました。作者はこんな状況になる前から、あの展開を考えていたと思うのですが、結果的に時代とシンクロしてしまったと思うんですよ。第1巻に作者の「感謝の言葉」が掲載されているのですが、「漫画は水や食べ物と違って生きていくために必ず必要なものではなありません。それを買ってもらうということは、とても難しく大変なことです」と、今風に言うと「不要不急のものではない」と書かれていたのが、すごく印象的でした。宮藤官九郎も同じようなことを朝ドラの『あまちゃん』(NHK)で書いていたのですが、この距離感はやはり、震災以降の感覚だと思うんですよね。震災を経て、その時に感じたことをエンタテインメントに昇華したら、後からコロナ禍が来て、多くの人が実感を持って読める作品になったということかもしれませんね。
島田:最後の無惨戦が総力戦の人海戦術だったのも、現代的だったと思います。
成馬:無惨一人に対して全員で挑んでましたからね。昔の漫画ならタイマンじゃないと卑怯だ、みたいな感覚があったと思いますが、『鬼滅の刃』はむしろ組織で戦うことを肯定していて、絶対的な個の永遠性みたいなものは否定している。
倉本:組織の描き方自体にも現代的な感性が感じられましたよね。最終決戦のラストでは無惨がでかい赤ん坊の姿になってゴリ押しで逃げるのを、末端の隊士や隠たちが捨て身で堰き止めようとする。そのときに、新しい当主になった産屋敷輝利哉が「死ぬな一旦下がれ!」「次の手は僕が考えるから!!」って言うんですよ。例えば初期の『機動戦士ガンダム』とかだったら、ああいう場面なら「すまん、組織のために死んでくれ」的なセリフが似合ってしまうんだと思うんですけれど、『鬼滅の刃』の場合はリーダーにちゃんと末端の隊員の命を優先させたところに、令和の価値観を感じました。