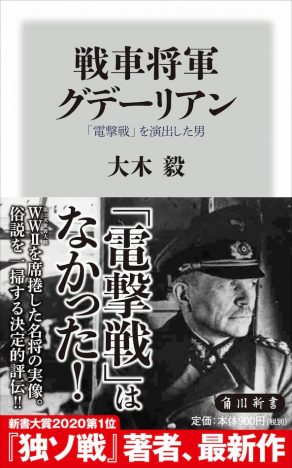ドイツ軍の“伝説”は歪曲して語り継がれているーー軍事史研究者・大木毅が語る、巨大な空白を埋める意義
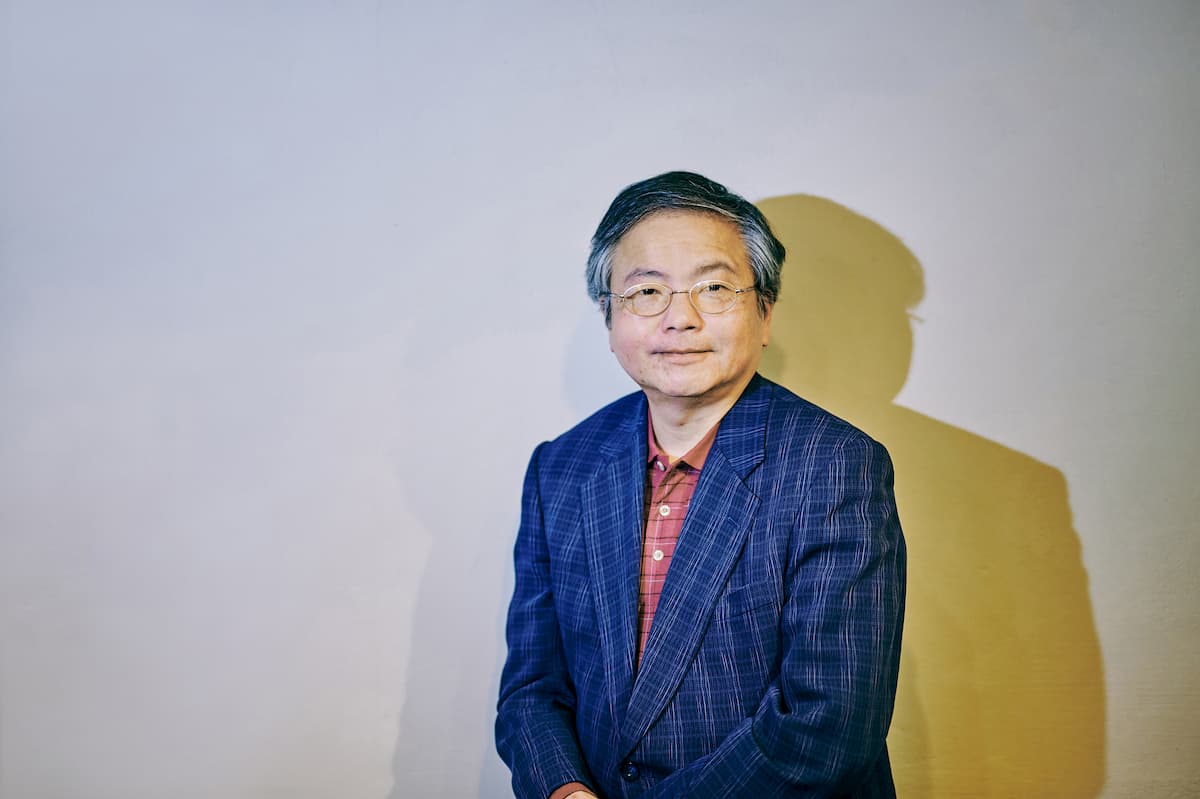
ドイツ国防軍で最も有名な将軍と呼ばれたエルヴィン・ロンメル。その英雄像から生まれた数々の俗説を打破し、読者に新鮮な驚きを与えた『「砂漠の狐」ロンメル』(角川新書)。また、歴史に埋もれた戦場、いや地獄を我々の前によみがえらせ、「新書大賞2020」の大賞を受賞した『独ソ戦 絶滅戦争の惨禍』(岩波新書)。新書市場の話題を席捲している大木毅氏が、新刊『戦車将軍グデーリアン 「電撃戦」を演出した男』(角川新書)を上梓した。
第二次世界大戦下、ドイツ装甲集団を率いた将軍にして、「電撃戦」の生みの親とされ、連合軍からも名将とされたグデーリアン。本書は、“伝説”となった戦車将軍の作られた仮面をはぎ、虚実を明らかにした一冊となっている。ロンメルと同様に、グデーリアンの研究もまた日本では遅れ、とうに否定されている“伝説”が未だに独り歩きしているというのだ。なぜ、日本ではかくも歴史が歪曲して語り継がれるのか? そして、その歪曲の果てに起こり得ることとは何か? 大木毅氏に話を聞いた。(編集部)
日本のドイツ軍イメージは1970年代で止まっている

大木:ドイツ語を学ぶ人が減りましたからね。それは自衛隊でも同様です。旧陸軍はドイツを重視していましたから、旧陸軍から自衛隊に入った人がいた時代には、ドイツ語を叩き込まれて、原書で研究できる人がたくさんいたんです。しかし、戦後は、同盟国であるアメリカ、また紛争の対象となり得るロシア、中国、北朝鮮が研究対象としてより重要になったことから、ドイツ語要員は減る一方ですね。自衛隊でも、防衛駐在官としてドイツに行く人はいますが、やはり少数派といわざるを得ない現状です。
――とはいっても、ドイツ軍関係の専門書は日本でも多数出版されています。
大木:たしかに、ミリタリー・ファン向けの本はたくさん出版されています。ただ、それを書いている人の多くは、ドイツ語の研究書を読めるわけではないため、英語経由、場合によっては日本語の資料だけで、新しい研究成果を反映せずにドイツ軍のことを書いてしまっています。このような状態が、日本ではかれこれ3〜40年続いているんですね。
――やはり大戦中のドイツ軍の研究が進んでいる国というと、ドイツ本国ということになるんでしょうか?
大木:もちろん、ドイツ本国では進んでいますし、英米、とくにアメリカでは研究が盛んですね。なぜアメリカでドイツ軍研究が進んだかというと、米陸軍や海兵隊がドイツ軍の伝統的な戦法である「委任戦術」に注目したからです。これは、権限を下方に委任し、下級指揮官に任務と手段だけを明示して、あとは自分の創意工夫で現場の指揮をとらせるという方法です。今の米陸軍や海兵隊は、これを「ミッション・コマンド」と称して取り入れたので、その過程で自然とドイツ軍のことが研究されたわけです。
――そういった国と比べると、日本におけるドイツ軍理解は止まったままなんですね。
大木:日本では、1970年代にグデーリアンやマンシュタインの回想録に、ロンメルの遺稿集などが翻訳・刊行され、一般に広まりました。しかし、それは、本人たちが後世にそう伝えたいと思っていたセルフイメージにすぎなかったのですね。ところが、日本の理解は、そこで止まってしまったのです。欧米では、その後、「本人たちはそう言っているけれども、当時の一次史料と付き合わせてみると、これは都合の悪い事実を糊塗している、本当はこういうことをしていた」という具合に、グデーリアンらの主張と事実の違いが究明されました。また、彼らが、戦争犯罪も見て見ぬふりをしていたことや、軍人としてはこのような欠点があると指摘するような議論もあります。これらが伝えられてこなかった日本では、ドイツ軍事史の理解や解釈が、欧米の1970年代ぐらいの水準に留まっている。最近まで、その状態だったということです。
信じていたドイツ軍像が崩壊した日

大木:1970年代だと僕はまさに10代だから、もちろんプラモデルを作って「ドイツ軍かっこいいな!」と思っていましたよ(笑)。10代のころはそういうものや、あるいは今では元ナチエリートだったことが暴露されてしまったパウル・カレルの著作も、何度も読み返して、「ドイツ軍はうまくやっていれば勝てたんじゃないか」「ヒトラーさえ余計な口出ししなければなあ!」と嘆いていました(笑)。
――もろに影響を受けていたわけですね。
大木:高校2~3年のころに外国の古書店に洋書を注文することを覚え、まずは英語でドイツ軍に関する本を読むようになったんですね。そうするといろいろなことがわかってきまして、「これは僕らが知っていることとは違うじゃないか」と。パウル・カレルにしても、勉強して、英語、さらにはドイツ語で、ヨーロッパの第二次世界大戦についての文献を読めるようになってくると、どうも怪しげではないかという気がしてくる。そもそも海外では、彼はまともな歴史家という扱いをされていなかったのです。
――それはびっくりしますよね……。
大木:そんな経験を重ねているうちに、僕の信じていたドイツ軍像は、1970年代に流布されていた、ドイツ国防軍弁護論にもとづくものでしかなかったことがわかってきました。それならば、本当のことはどうなんだろうということで、大学生のころから、いろいろ調べだしたのです。拙著『「砂漠の狐」ロンメル』も、原型は、実は20代前半のときに発表しているのですよ。僕はアナログのウォーゲームが好きなのですが、その専門誌に掲載されたんです。だから、ごくごく狭いウォーゲーマーの間では「ロンメルというのはこういう人だったのか」と衝撃があったようなんですが、いかんせん読んでいる人が果たして1000人いるかどうかという規模だったので……。今から30年以上前の話ですね。
戦争を嫌うからこそ、戦争を知らなければならない
ーー大木さんはそういった研究をどのように進めてきたのでしょうか?
大木:信頼できる邦語文献はごくわずかしかないため、ドイツ語や英語の資料を探さなければならない。けれども、日本の図書館が海外の文献を網羅しているわけではないし、ましてや軍事や戦争の本は冷遇されていて、購入してもらえるほうが珍しかったですからね。しかたなく、自分で史資料を買い集めるほかありませんでした。
――自腹が基本なんですね……。
大木:たぶん、ここ30年ぐらいは、毎年少なくとも100万円はつぎ込んでいるはずです。さらに、そこから進めば、今度は翻刻・出版されていない生の史料、国防軍最高司令部や陸軍総司令部の文書もみたくなる。僕は二年ちょっと留学させてもらいましたから、それらを調べて回ったわけです。研究書や公刊されている文書、国防軍最高司令部の戦時日誌なども買い集め、未刊行史料はドイツに行って閲覧したり、マイクロフィルムを購入したり……。文献にしても、なかなか日本では手に入らないものもありますが、それもドイツに行けばみられますから。もっともネットの普及以後は、かなりの稀覯本でも入手しやすくなりましたが。
――そこまでやっている方の立場から見て、今の日本の外国軍事史研究の問題点はどのようなところにあるとお考えでしょうか?
大木:『中央公論』最新号(4月10日発売)にも書いたことですが、とにかくやっている人がいない。アカデミシャンにも、自衛隊の本職にも、です。ただ、いわゆる「広義の軍事史」「新しい軍事史」について書く人は21世紀に入って出てきたのです。それは、どんな人が徴兵されたのか、あるいは連隊での生活はどのようなものだったのかというようなことを研究する、社会史・日常史からのアプローチです。しかし、軍隊の目的である「戦うこと」は、なぜかみなさん避けるんですよね。
ーーそれはなぜでしょう?
大木:ひとつには戦争嫌悪というものがあるでしょうし、さらに軍事の根本的な要素である戦略や作戦、戦術、戦闘、軍隊組織というところに踏み込もうとすると、相当踏み込んで勉強しなければならない。ところが、これはなかなか大変なことなんです。教科書や参考書はなきに等しいですから、結局旧陸海軍の作ったもの、あるいは自衛隊が編纂したなかで公表されているもの、あるいは外国の軍事理論書を体系的に読んでいかなければなりません。
――聞くだにハードルが高そうですね……。
大木:去年、新書大賞を受賞された吉田裕先生が「日本の軍事史で手つかずに残っているのは戦史である」という意味のことをおっしゃっていました。逆説的な話ですよね。本屋さんに行けば、戦記本やミリタリーに関連する書籍は山のようにありますが、それでも戦史は手つかずだと。おそらく、吉田先生は、学問的な戦史や軍事史の研究というものが、実は日本では欠如していることを言いたかったのではないか、と思います。もし、そうだとすれば、僕も全く同感ですね。防衛大学の大学院に当たる総合安全保障研究科では、欧米に引けを取らないような学問的アプローチで、戦争や軍事について研究しています。ただ、残念ながら、それは例外で、全体的にみれば、そのような研究は不足しています。日本の戦争に関する本が氾濫しているようにみえるけれども、その大多数は昭和の時代の戦記と同じ手法で書かれている。新しい解釈、新しい分析をしているかといえば、大いに疑問です。これから必要とされるのは、そういう研究ではないでしょうか。