日本人は「人を殺すダニ」とどう闘ってきたのか? ノンフィクション作家・小林照幸に聞く、ツツガムシ病の恐怖

“死の虫”ツツガムシ
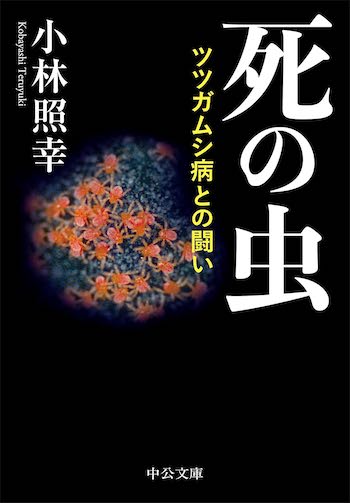
ツツガムシ病は、戦前は秋田県、山形県、新潟県などの日本海側に多く見られる風土病の一種と考えられていた。感染すると、高熱、発疹、倦怠感などの深刻な症状が現れて重症化するケースも多く、時には死に至ることもある深刻な病気である。それゆえ、ツツガムシは“死の虫”として恐れられてきた歴史がある。
人間とツツガムシとの戦いに、ノンフィクション作家の小林照幸氏が迫った一冊が『死の虫-ツツガムシ病との闘い』(中央公論新社/刊)である。それまで風土病とされていたツツガムシ病に医学者が関心をもち、やがて病原体が発見され、治療方法が確立されるまでには知られざるドラマがあった。著書の読みどころを、小林氏にインタビューで聞いた。
ツツガムシはどんな虫?

――私は秋田県出身で、「ツツガムシには注意するように」と子どものころから注意を受けてきましたが、ツツガムシを知らない人は多いと思います。まずはどんな虫なのか、生態を教えていただけますか。
小林:ツツガムシはダニの仲間で、全長0.2~0.3mmの小さな虫です。怖いのは幼虫の時のみで、人体に食らいついて体液を吸うときに、リケッチアという病原体を人の身体に入れます。リケッチアと言っても聞き慣れないかもしれませんが、細菌とウイルスの中間にあたる微生物です。
――ツツガムシはどんな環境に生息するのでしょうか。
小林:アカツツガムシは河川敷などの河川流域にいますが、ほかの種類は野山や草藪などで見られます。キャンプなどのアウトドアや農作業、外で遊んでいるときに感染する恐れがありますから、親御さんは子どもたちに注意喚起してほしいですね。
――ツツガムシ病は現在も患者はいるのでしょうか。
小林:戦後の調査で全国に分布する病気であり、風土病ではないとわかり、毎年、患者が出て死亡者も出ています。もっとも、早めに医療機関で診断を得て、抗生物質の治療薬の投与を受ければ治るのですが、対応が遅れてしまい、命を落としてしまうケースは今もあるので、恐ろしい病気であることには変わりありません。知っていると知らないとでは大違いだと思います。
――ツツガムシ病は夏に多く発生するそうですね。かつて、秋田、山形、山形などの農家はツツガムシ病で亡くなることが多く、実りの秋を迎えることが難しい地域も多かったと小林さんは指摘しています。
小林:稲が収穫を迎えるまでには、冷害やイナゴの蝗害といった苦労もありますが、収穫を迎える前にツツガムシ病になって年を越せない人もいました。冬は雪が積もり、寒さも厳しいですが、ツツガムシ病にならないと考えると、安心して過ごせた季節だったともいえます。昔は数え年の概念があり、年を越せば年齢が1つ上がっていきました。無事に年を越せると、感慨深かったのだと思います。
――身近な病気だったからこそ、ツツガムシ病は地域の伝統行事や祭事とのつながりも深いと聞きます。秋田県湯沢市の“まなぐ凧”もツツガムシ退散を祈念したものですし、虫送りの行事は新潟県内各地で見られますね。
小林:秋田県を訪れた紀行家・菅江真澄の記録にもあるように、ツツガムシ病として医学の概念が立てられるようになる前から、人々は虫が原因であると経験則で知っていました。それゆえ、秋田県、山形県、新潟県にはツツガムシ病にまつわるお地蔵さんや祠などが建立され、寺院や寺社でも疫病退散祈願をしていました。今となっては非科学的かもしれませんが、なにぶん、治療薬である抗生物質がない時代です。人々はツツガムシ病にならないようにと、神仏に祈ったのだと思います。
――当時はどんなにツツガムシ病が恐ろしくても、今のように簡単に引っ越しができたわけでもないですからね。
小林:先祖代々の土地から離れることは難しく、土地を守ることに一生懸命でした。人々はその土地で生きる宿命を受け入れたのだと思います。だからこそ、虫送りや祭事などを受け継いできたのでしょう。我々はコロナ禍という未曽有の感染症を経験しましたが、あの時期を振り返ってみると、先人がどれだけツツガムシ病に苦労したのか、実感できるのではないでしょうか。
明治時代に研究が盛んに
――ツツガムシ病の研究が盛んになったのは、近代医学が導入された明治時代です。
小林:ヨーロッパの医学書に載っていない病気があるということで、研究者は好奇心を刺激されたと思います。何より、未知の病気をどうにかして解明するのが医学者の使命と考えたのでしょう。例えば、新潟県長岡市では梛野直、川上清哉などの医学者が調査を行いました。彼らは東京大学を出ているので、地方にいながら中央とのパイプがあったのです。
――秋田県湯沢市にも、田中敬助が日本沙蝨病研究所という施設を作っています。
小林:田中は湯沢市出身で、東大を出た後に故郷に戻った医学者です。秋田県内で発生していた毛蝨病が、新潟県のツツガムシ病と同じ症状を示していることを明らかにし、梛野と同じく中央とパイプを持っていました。現在だと、東大を出た後に研究者として大学にとどまるケースが多いですが、当時は学問を修めて地元に貢献するという使命をもち、卒業後に故郷に戻った人もたくさんいました。田中は農民がツツガムシ病に苦しんでいる恐怖をリアルにわかっているからこそ、なおさら故郷に戻ろうと考えたのではないでしょうか。
――素晴らしい志ですね。
小林:田中は自分で研究所を建て、ツツガムシ病の研究をライフワークにしました。郷土を苦しめる病気への治療を願っていたことがわかります。地元で研究し、成果を論文にまとめて学会に発表していました。患者を診察しながら執筆しているので、他の研究者も一目置いたのでしょう。研究所の跡地に石碑などがないのは残念ですが、湯沢市が誇る偉人と言っていいと思います。
――明治時代は、感染症に対して社会的な関心が高かったのでしょうか。
小林:当時は感染症ではなく“伝染病”といいましたが、多くの感染症が原因不明で、感染経路もわかっていませんでした。そこで、病原体の発見を多くの研究者が目指したのです。感染症は多くの人が亡くなりますから、克服を目指すのは医学者にとって最優先課題だったといえます。地域の暮らしとも密接につながっているわけですからね。
――新1000円札の肖像にもなった北里柴三郎もツツガムシ病に関心を持ち、ドイツから帰国後に新潟県内で実地調査を行っています。
小林:私は新潟県五泉市の虫送りなどを行っている地区など、北里が実際に訪れた場所を取材しましたが、現在と比べたら交通が不便だった時代に、二年連続で訪れたことに熱意を感じました。鉄道では途中までしか行けないため、阿賀野川を船で上ったようです。その際、医療機器も大量に持参する必要もあったでしょうから、北里にとっても一大事だったはずですよ。
――新潟の人たちは北里を歓迎したようですね。
小林:歓迎は、これで病原体は発見される、という期待と同義だったでしょう。現地では北里の講演会も開催されています。ツツガムシ病についてどれだけ話したかはわかりませんが、感染症全般についての講演だったようです。北里本人はツツガムシ病の病原体を発見できませんでしたが、それで終わりではなく、伝染病研究所の弟子が受け継いで現地調査を続けたことが意義深いと思います。
病原体、リケッチアの発見
――リケッチアという細菌でもない、ウイルスでもない新たな微生物が発見されたのが1916(大正5)年のことでした。その後、東大伝染病研究所の長与又郎が実験を繰り返し、1930(昭和5)年にツツガムシ病の病原体であるリケッチアの発見者となります。
小林:長与は調査のために防虫白衣を着て、山形県の最上川の中州の草むらを徘徊し、原因となるツツガムシの幼虫の採集や実験動物への感染を試みました。まさに命がけでした。自分も感染したら死ぬかもしれないのに、使命感を持っていたからできたことだと思います。ただ、学術的な意味では論文を書いた長与が発見者なのですが、長与より早くツツガムシ病のリケッチアの尾をつかんだのは千葉大学の緒方規雄です。緒方はどうして早く論文を書かなかったのかと思います。もしかすると、自分以外にこんな発見をする人はいないだろうと、甘く考えてしまったのかもしれません。
――リケッチアが発見されたのち、ツツガムシ病の病原体と特定できるまでには、それなりに時間がかかったように思えます。
小林:海外の文献報告で日本の医学者が「ツツガムシ病の病原体もリケッチアかもしれない」と考えられるようになってからも、特定に至るまでにはウイルスや寄生虫など様々な可能性を想定しては研究を繰り返していました。消去法によって解明に至ったのでしょう。
――病原体の特定は、当時に医学界では大きなトピックだったのでしょうか。
小林:そうだと思います。特定できたことで、治療法の開発に取り組めるわけですからね。その後、抗生物質が出てきて、戦後にはアメリカの貢献もありました。アメリカは戦時中に東南アジアや太平洋地域でツツガムシ病に苦しんだ経験を活かし、日本と共同研究の体勢を持ちました。これは、ツツガムシ病患者の治療や疫学を発展させたことでも、大きな貢献があったといえます。
――治療法が確立できたのは戦後なのですね。
小林:戦後になると、早期に治療すれば治る病気になってきました。ただ、そこにたどり着くまでは、多くの人々の努力と犠牲があったことを忘れてはいけません。それに、繰り返すようですが、早期治療しないと命を落としてしまう病気である点は今も変わらないといえます。






















