“出版不況”が叫ばれる今、出版社に必要なことは? マイナビ出版社長・角竹輝紀が語る「読者に会いに行く」姿勢

1973年に設立されたマイナビ(当時は毎日コミュニケーションズ)。その出版事業本部として生まれ、2015年に分社化したのが「マイナビ出版」だ。
『将棋世界』に代表される囲碁・将棋関係や、プログラミングを始めとする専門技術から一般向けまで幅広く扱うIT・コンピュータ関連など、大手出版社とは異なる独自のジャンル展開で立ち位置を確立してきた歴史を持つ。
昨年5月には、文芸の新レーベル「MPエンタテイメント」を立ち上げ。6月にはドイツで開催された日本のポップカルチャーを紹介するイベント「DoKomi」に出展。直接、自社の出版物を販売して、海外市場への展開にも積極的に踏み出し始めた。
出版業界は厳しい状況が続く中で、大胆な挑戦を続ける理由は何か。「舵取り」役ともいえる、角竹輝紀社長に聞いてみた。
「コレは売ってないのか?」とドイツで聞かれる価値。
――昨年スタートした文芸レーベル「MPエンタテイメント」が好調です。そもそも角竹社長の肝いりでスタートしたそうですね。あらためて立ち上げの経緯を教えてもらえますか?
角竹輝紀(以下、角竹):起点のひとつは、危機感ですね。マイナビ出版は、「将棋」や「IT」などの領域で長く出版物を出してきましたので、それらの分野では読者の認知度も高いし、内容面でも信頼いただき、買っていただけることが多い。
それが強みである一方、同じジャンルを長くやっていると読者層もある程度固定化されてしまいます。市場に対して視野が狭まり、新しい読者との出会いが減っている危険がある。安全なところで事業を行うことも重要ですが、新しい市場や読者を探しに行く必要性を感じました。待っていても新しい読者が来てくれるかどうかわからない。それなら、当社の未来のためにも、こちらから読者に会いに行ってみよう、そういう思いでレーベルを開始しました。
――文芸、しかも単行本を選ばれた理由は?
角竹:1つ目の理由は、出版社としてのブランドイメージを上げるためには文芸が有効だろうと考えたこと。2つ目は、文芸ジャンルは専門書や実用書より読者の裾野が広く、読者の趣味趣向や動向を見ることができるのではないかと考えたこと。3つ目は、文芸は「出版社買い」よりも「著者買い」されるケースが圧倒的に多いだろうと考えたこと。
文芸は、好きな著者が新作を出したなら、読者は出版社を問わず買ってくださる可能性が高い。大手出版社ではなく、マイナビ出版から出たとしても、好きな著者の素晴らしい作品なら、読者はきっと手にとってくださるだろうと。
実際に文芸ジャンルを始めて実感したのですが、著者を通して出版社同士も繋がりやすいんですね。「この著者の本を売りたい」という思いは、どの出版社も変わらない。出版社の枠を超えて連携したフェアやイベントなどが多いのも文芸ならではの特徴です。
単行本サイズを選んだ理由は、読者にアイテムとして手元に置いておきたいと思ってもらえそうな、その本の内容にあったデザインにしたいと考えたからです。あと、文庫はライト文芸の「ファン文庫」というレーベルをすでに持っていますので、それと差別化する意図もありました。
――いずれにしても、良い著者との繋がりを持つことが大切になります。新たに築きあげるのは難しかったのでは?
角竹:そこは、担当編集者の熱量が大きいと思います。以前、こちら(URL:https://realsound.jp/book/2025/05/post-2021778.html)でもインタビューしていただきました。
実質、レーベルの専任はその担当編集者ひとりなのですが、とにかく小説や作家に詳しいし、ジャンルの動向もきちんと追っている。「良いものを送り出したい」というエネルギーが強い一方で冷静な市場分析も欠かさない。
こうした熱量あふれる人材が、どんどん力のある著者に声がけして、ネットワークを作っています。すでに藍内友紀さんや十文字青さんといった方々に参加いただいていますが、今後も驚くような著者の方に「MPエンタテイメント」で書いていただく予定です。
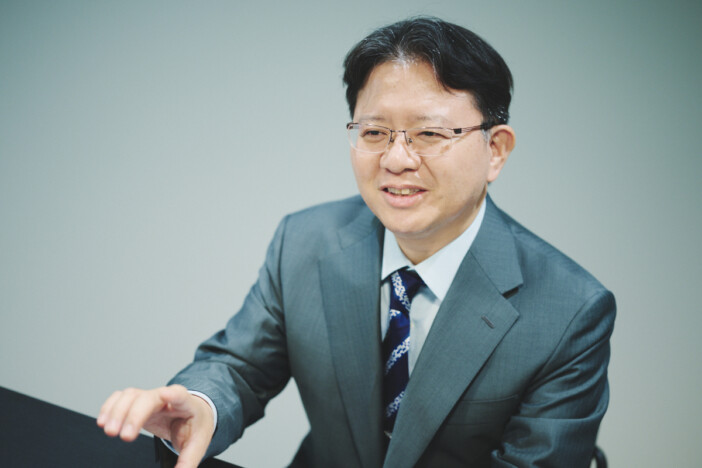
――もうひとつ「海外展開」にも力を入れ始めています。昨年6月にドイツ・デュッセルドルフで開催された「DoKomi(アニメ・マンガ・コスプレなどの日本文化が集うイベント)」に初めて出展されました。
角竹:はい。この挑戦も、危機感をエンジンに「新たな読者に会いに行こう」と考えて実施した施策です。言うまでもなく、以前から、当社の一部の書籍は海外でローカライズして出版されていました。ただ、現地の出版社に版権を販売して、先方に翻訳・販売・PRまですべて任せるのがスタンダードでした。
しかし、そうすると実際にどんな読者にどのように手にとってもらえているのか、見えにくかったんですね。そこで、直接足を運ぼうと文字通り「会いに行った」わけです。
――ブースを出されて、イラスト関連書が完売になるなど盛況だった、と伺っています。
角竹:そうなんです。ビジネス的には、「何がどれだけ売れたか」といった数字は日本にいてもわかります。ただ展示会を訪れた方々が、どの本を手にして、どんな基準で選び、買っているのか。そもそもどういう人たちがイベントに来て、私たちのブースに足を止めてくれるのか。そういうことは、現地に行って、実際に売ってみないとわからない。現地にいる読者の温度感を知ることこそが、直接会いに行く意義だと考えています。
イベントで販売を担当した社員の話で象徴的だったのは、本を買うだけでなく、多くの方が宣伝用に飾っていたパネルをキラキラした目で眺め「これは売ってないのか?」「売り物ではないの?」と聞いてきたというエピソードです。
私たちが思っている以上に、ドイツの人たちがイラストをアートとして捉えていただいていることがわかりました。そこで「次回は本だけでなく、こうしたパネルを受注生産で販売したらどうだろう」というアイデアがすぐに出てきました。
さらにドイツでのこうした取り組みをニュースリリースで伝えたところ、同業他社から「ヒアリングしたい」「相談にのってほしい」といった声ももらえました。
――現地で読者とふれあって知るニーズは、臨場感が違いますね。それこそ熱を感じる。
角竹:少し話がズレますが、2025年秋に開催された「文学フリマ東京41」に、私も友人のブースの販売員として、個人的に参加してみました。あの場の盛り上がりや熱気を一販売員として体験したことで、出版不況といわれてはいますが、本が求められていることはひしひしと感じられるし、なにか”次の打ち手”のヒントが生まれる気がする。
いずれにしても、受け身では何も起きない。けれど、アクションすると必ず意義のあるリアクションがかえってくる。その価値がとても大きいと感じているから、挑戦を続けているんです。このご時世だからこそ。
勝手に「全集作り」をする少年だった
――そもそも角竹さんは、どのような経緯でマイナビ出版に入られたのでしょう?
角竹:小学生の頃から、本は好きでした。人生のいろんな局面で読んだ小説やその中の一節に助けられたような経験もあった。だから、小説を自分で書いて公募に出した、なんてことも。一方で、編集というか「本作り」そのものへの興味も昔から強かったのです。
たとえば、中学時代は「好きな作家の全集を作るなら、どんな作品をどの順番で入れるかな……。発表順じゃなくて自分ならこうするな」といった具合に、ひとりであれこれ勝手に考えていましたね。
――当時、好きだった作家というと?
角竹:中学の頃は、小松左京や星新一、福永武彦、辻邦生、海外だとトルストイやトーマス・マン、ディケンズなどとにかくさまざまな作家の本が好きで読んでいました。しかし、「本作り」に興味を持つきっかけになったのは、意外に思われるかもしれませんが、ミステリー作家の赤川次郎なんですよね。
例えば『三毛猫ホームズの狂死曲(ラプソディ)』。目次を見て驚いたのが、通常の小説に多い「第1章」、「第2章」ではなく、「第1楽章」「第2楽章」という章立てになっていた。プロローグは「チューニング」、エピローグは「アンコール」と、タイトルが「狂詩曲」をもじったものですから、それに合わせて変えてあったのです。
――おしゃれですね。
角竹:他の作品にもそういう「遊び」や「仕掛け」があったりして、内容を楽しむだけでなく、そういう仕掛けを読み解く楽しさがあることに気付きました。
それまでは、本=書かれている中身、小説=ストーリーだと思っていた。けれど、本は「コンテンツ」だけでなく、「仕掛け」も含めたもの、と気づいた。そのときから、少しずつ「将来は本作りに関わりたい」と考えるようになり、結果として、編集者というキャリアを選ぶことになりました。

――では、文学部などに進まれたのですか?
角竹:それが違ったんですよ。というのも、中高生の頃に読書に明け暮れすぎていて、「このまま文学を極めていくと、社会性に欠けた人間になってしまうではないか」という不安がありまして(笑)。
考えた結果、社会と繋がる実学を、と法学部に進みました。でも結果的に一番私にとって良い選択をしたのではないかと思います。編集者は、本が好きなだけではダメで、著者と会社、デザイナーなど複数の立場の人たちと付き合っていかなければならない。当然立場が違うと考えも違うわけで、その調整をしていかなければなりません。そういった場合に、今起きているものごとを公平に捉えて、意見や利益が相反する中でどのように最適解を見つけるか、落としどころを見つけるか、といった考え方や視点が必要です。私の場合は法学を学ぶことで、それを身につけられたように感じます。また、管理職になったら、リーガルマインドというんでしょうか、会社の規程や法律に則り、物事を論理的かつ公正に判断する能力も役立っているように思いますね。
――そして卒業後、1991年に新卒でマイナビ出版、当時は毎日コミュニケーションズの出版事業本部に入社されます。なぜ数ある出版社の中でマイナビを選ばれたのでしょう?
角竹:一般企業や大手出版社も受けましたが、もっとも自由さを感じたのがマイナビだったんです。
形式張っていない、何でもやれそうな雰囲気があった。実際、当時としては早い段階でコンピュータ関連の書籍などを手掛けたりしていて。そうした自由度の高い中で本作りをしてみたい、と思いました。
――配属されたのは、実際コンピュータの書籍部門だったそうですね。
角竹:はい。とはいえ、完全な文系人間で、コンピュータすら触ったことがありませんでした。とにかく、情報を収集すること、勉強することに必死でしたね。上司もいきなりコンピュータの専門書を担当させるのは厳しいと判断したのでしょうか、最初に手掛けた本は『普通の人100人のパソコン』という、ユーザーを取材して紹介する一冊でした。自分もちょうど普通の入門者でしたから、入門者(私)が他の入門者の使い方を聞いていく、という視点で作った本でした。まだWindowsでもない、MS-DOSの時代ですね。
ライバルからかかってきた1本の電話
――また社内では角竹さんといえば、ともいえるロングセラー『ノンデザイナーズ・デザインブック』の担当もされていたとか。
角竹:もともとは1998年に、私の当時の上司が担当した翻訳書です。デザイナーではない普通の人でも、デザインのイロハを理解することで、レイアウトやデザインを美しく、読みやすくすることができる。あるいはデザイナーへの指示も的確におこなえる、という趣旨でアメリカのロビン・ウイリアムズという方が書かれました。
当初は冊子や社内報、ポスターといったグラフィックデザイン向けの本として売れ、第2版まではスムーズでした。
ただ、第2版の売れ行きがあまりよくなく、アメリカで出版された第3版の日本語版をどうするか……というタイミングでその上司が異動することになり、私が引き継いだのです。
――そこからどのように四半世紀以上続くロングセラーになったのでしょう?
角竹:最初の転機は、Webデザイナーの方々が本書を買ってくださるようになったときですね。2000年頃からWebサイトが一般的になり、多くの方がどんどんホームページを作ったり、発注したりするようになったのです。
このときに「この本に書かれているデザイン基本原則は、Webのデザインでも参考になる」と買ってくださるようになった。つまり、これまでのグラフィックデザイナーとは違う、新しい読者層が増えたのです。
2010年代に、また同じような新しい読者層の増加がありました。今度はUIの設計やアプリケーションを作るエンジニアの人たちでした。「エンジニアはデザインそのものには関わらないかも知れないが、アプリの設計とデザインとは似ている面も多いから、基礎を知っておいたほうがいい」と発言してくださる方がいらっしゃったりして、また違う読者が手にしてくれるようになったのです。
――本質的なデザインの基本をわかりやすく教える本だからこそ、時代が変わっても、いろいろな場所で同じく重宝されたわけですね。
角竹:コンピュータ書はITの最先端をテーマにすることが多いのですが、オーソドックスでベーシックなものも、時代時代のトレンドが変わっても変わらぬ価値があるということかもしれません。
といっても、やはりただ販売していれば売れていくというものでもない。そこで発売20周年となる2018年に、『ノンデザイナーズ・デザインブック』をかつて読んだプロのデザイナーさんたちに、それぞれの現場でどのように本書のノウハウを活かしているかを伝える記事を執筆してもらいました。これをPDF冊子にしてSNS上で無料配布をするキャンペーンを仕掛けました。これはそれまで愛読してくれた読者の方々への感謝を込めて実施したものでした。
それが思った以上の反響がありまして、Twitter(現X)のトレンドに一時期入るほどでした。最終的には1万以上もツイートされるとともに、ダウンロードされました。「デザイナーなりたての頃に読んだ。懐かしい」「自分が読んだのは第1版。もう20年になるのか」といったコメントを嬉しく読みました。
――その1件を聞いても、「読者に会いに行く」というか、読者に近い場所でニーズをひろうことをとても意識されている気がします。
角竹:それは、私にとって未知のジャンルだったIT、コンピュータ書籍の編集を担当してきたことが関係しているかもしれません。
先に述べたように私自身は文学青年で、コンピュータについての知識に乏しかった。だから、企画を考えるときに自分だけでは良いものが出てくる気がしない。誰か詳しい人に会いに行き、話を聞きながら詰めていったほうが絶対良いものになる。初期はパソコン通信、そして、インターネットの時代になったら早い段階でTwitter(現X)やFacebookなどのSNSを始めました。また、IT関連のエンジニアの方やそのコミュニティに飛び込んで、足繁く会合などにも通い、「いまどんなものが注目されているか」「どこにおもしろい方がいるか」「もしよろしければ、うちで本を書きませんか?」と尋ね回っていました。
そうした繋がりから、多くの企画、本が生まれました。結局、読者というか「人」にフォーカスして、何が求められているか探し出す。それを形にすることが、自分たちの仕事だと思っています。
求められているものを一緒に形にするのが一番で、「本」にこだわらなくてもいいとさえ思っています。先ほど海外事業でお話したパネルなどのグッズにしろ、現在当社で頻繁に実施している棋士やエンジニアといった方々を迎えてのセミナーやトークイベントなどもそう。
ただ情報を一方的に提供するのではなく、そうした読者、人に寄り添って、共になにかを作りあげる。そうした姿勢こそが、いま出版社や編集者に求められているのではないでしょうか。
――昨年には『知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く』と企業理念を変えられました。体験という言葉が入っているのは示唆的ですね。ところで角竹さんが、これまで出版の仕事を通して忘れられない“体験”をあげるとしたら、何になります?
角竹: “体験”としては、先ほどお話しした、IT関連のコミュニティに飛び込んだことでの様々な出会いや出来事が本当に大きいですね。そのジャンルの知見を持った人たちとの会話自体が刺激的でしたし、大阪までセミナーを見に行ってみたり、イベントに登壇してくれとお願いされたり、今でも忘れられない出来事がいろいろあります。
それとは別の方向で、記憶に残っている“体験”は、1995年に作った『Macの工作室』という本に関するエピソードですね。
Macintoshだけでなく、紙とハサミとのりといった道具も使って、ステッカーなどを工作する、という内容でした。Macというデジタルな道具を主軸に、アナログなものを作る楽しさを紹介する、という、なかなかにチャレンジングな企画でした。
すると、発売後、ライバルのコンピュータ関連の出版社の方から名指しで電話がかかってきたんです。「うわ、クレームかな。嫌だな」と思いながらおそるおそる電話をとると「悔しい!」と言われたんですよ。
――悔しい?
角竹:「同じような工作の企画を考えていたが、うちの会社では通せなかった」と。
今ならメールやSNSなどで気軽につぶやけるのでしょうが、わざわざ電話をかけて、悔しさを伝えてくれたのは、こそばゆいような、誇らしいような、なんともいえない体験で、今も強く残っていますね。自分の仕事が、読者だけでなく、同業の仲間にも伝わっていると実感できた瞬間でした。
――これまでの角竹さんのお話を聞いていると、マイナビ出版が大胆な挑戦を続ける理由がわかる気がします。
角竹:これまでの私自身の経験から、この仕事において一番大事なことは、読者との繋がり方だと考えています。新しい読者に会いに行く、出会った読者の反応を見ながらより良い繋がりを考えていく。新ジャンルやイベントへの挑戦、キャンペーンといった施策を行うことで、私たちも経験値が溜まっていきますし、読者のニーズもより見えてくる。それを繰り返すことで、読者との繋がりもより深く、より良いものになっていくんじゃないかと思っています。
冒頭に現状への危機感がある、と申し上げましたが、市場が変化している以上、こちらの行動も変化しなければならないし、それであれば、より積極的に変わっていく姿勢のほうが良い。これからも、出版という枠をあまり意識せず、新しい読者、新しい分野に会いに行きたいですし、そこで得られる出会いと経験が、会社をもっと良くしていくんじゃないかと。そういう挑戦者の姿勢を持った人と、これからも出会い、一緒に新しい読者との繋がり作りに挑んでいきたいと思います。


























