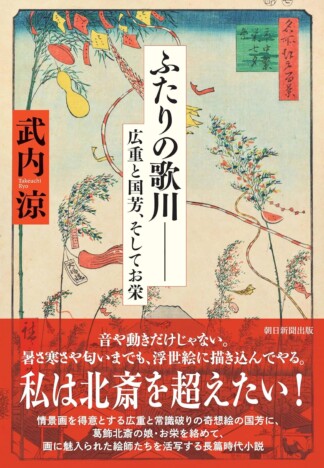『のぼうの城』『村上海賊の娘』の和田竜、12年ぶり長編小説『最後の一色』の仕上がりは? 心震える力作を読む

野村萬斎主演の映画も大ヒットした『のぼうの城』や『忍びの国』、歴史小説として初めて「本屋大賞」に輝いたベストセラー『村上海賊の娘』によって、一躍「ニューウェーブ歴史・時代小説」の旗手となった和田竜が、長きにわたる沈黙を破って、実に12年ぶり(!)の長編小説『最後の一色』(小学館)を上梓した。
主人公は、表題の通り、室町時代より丹後国の守護を代々務めてきた一色家、最後の当主である「一色五郎」だ。必ずしも多くの人にとって馴染みのある人物とは言えないこの人物だが、それもそのはず。彼の「名乗り」は史料によって「義有」「義俊」「満信」「義定」など、さまざまであるというのだ。細川家の家記である『綿考輯録(めんこうしゅうろく)』をはじめ、『一色軍記』など膨大な史料を丹念に読み解きながら(実際、その作業に6年ほど費やしたという)、数々の「謎」と「魅力」に満ちたこの人物の「実像」を、彼と同年代の武将・細川忠興との因果を絡めながら、今の世の中に活き活きと描き出そうとすること。それが本作『最後の一色』なのだ。
物語の主な舞台となるのは、現在の京都府北部にあたる丹後国、日本三景のひとつである天橋立で知られる地域だ。戦国時代の終盤、織田信長がいよいよ天下をその手中に収めようとしている頃から、この物語は幕を開ける。信長に反旗を翻した一色家を倒すべく、丹後国に派遣されたのは、長岡(細川)藤孝・忠興父子が率いる長岡軍(室町幕府最後の将軍・足利義昭を見限り、信長の配下となってからは、「細川」ではなく「長岡」を名乗っていた)だった。彼らの侵攻と裏切りによって、窮地に立たされた一色家の当主・義員(よしかず)は自刃。それに伴い、義員の嫡男・五郎が一色家の当主となるのだが……この若者が破格だった! 少ない軍勢ながらも自ら先頭に立ち、獅子奮迅の活躍を見せるのだ。その姿は阿修羅のごとく、残酷極まりない。にわかに恐慌に陥る長岡軍だが、こちらも血気盛んな若き猛将・忠興が、一色勢を追撃する。しかし……そこで完膚なきまで打ちのめされながら、なぜかその命を奪われなかったことに、負けず嫌いでプライドの高い忠興は、激しく憤慨する。奇しくも五郎と同い年である彼は、いつの日が五郎を打ち破り、丹後国を自らの手に収めることを、自らの心に誓うのだった。
豪放磊落なのか、はたまた繊細なのか。残酷なのか慈愛に溢れた人物なのか。策士なのか愚鈍なのか。その「真意」を自ら語ることがないので、たとえその家臣であっても、なかなか判別のつかない――しかし、戦場では「怪物」と呼ばれるような、恐るべき活躍をみせる若き当主・一色五郎。かくして始まった五郎と忠興の因果は、めまぐるしく変化する情勢の中で、五郎と同じくその「真意」がどこにあるのかわからない織田信長、彼と長岡家を繋ぐ信長の右腕・明智光秀(大河ドラマ『麒麟がくる』でも描かれていたように、光秀と藤孝は義昭配下の頃からの盟友であり、のちにキリスト教徒となり、洗礼名・ガラシャで後世に知られることになる光秀の娘・玉は、忠興の妻でもある)の思惑によって、数奇なめぐり合わせを辿ってゆくのだった。
あるときは刃を交える「敵」として、あるときは忠興の妹・伊也を嫁がせた「義兄弟」として、またあるときは共に馬を並べて戦う「味方」として、さらには互いの生死を左右する「恩人」として。その途中には、誰もが予想しなかった驚天動地の出来事――「本能寺の変」もあった。双方の複雑な思いが入り混じる2人の関係性は、紆余曲折の挙句、やがて史実的にも多くの「謎」を含んでいる、ある「謀殺事件」に至るのだった……。
それにしても圧巻なのは、そのクライマックスの描写と、そこに至るまでの予測不可能なめくるめく展開だ。必ずしも定説とは言えない……否、定説さえ存在しない領域に、筆者は膨大な史料を読み解きながら、作家ならではの想像力と人物描写を駆使して、果敢に踏み込んでゆくのだった(思えば『村上海賊の娘』も、そういう小説だった)。先に挙げた『綿考輯録』を主軸としつつ、『丹州三家物語』『細川忠興軍功記』、果ては吉田兼見の『兼見卿記』など、膨大な史料を丹念読み解きながら、そこに矛盾があれば理路整然と反駁し、誰がいつどこにいたのかを明らかにしつつ描き出される怒濤のクライマックス。その手際と筆致は、さながら「現場検証」のように、手に汗握るスリリングな臨場感に溢れているのだった。
「怪物」と恐れられながらも、慈愛の心をもった誰よりも魅力的な人物として描き出される最後の一色――一色五郎の「真意」と、その「運命」やいかに。彼の心の内にあった「一色家の業報」とは何なのか。そして、そんな「怪物」との若かりし頃の邂逅が、信長亡きあと、秀吉、家康と次々主君を変えながら、数々の戦場を渡り歩いた猛将として名を残し、最終的には80過ぎまで生きることになる細川忠興にもたらせたものとは、果たして何だったのか。ぜひ、その身で体感してもらいたい、心震えるような力作だ。