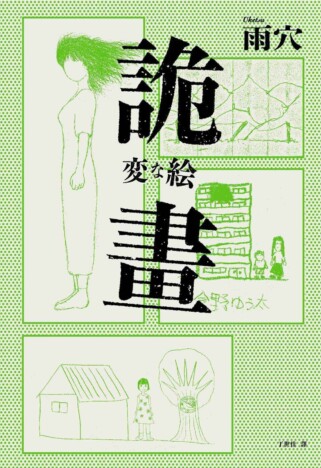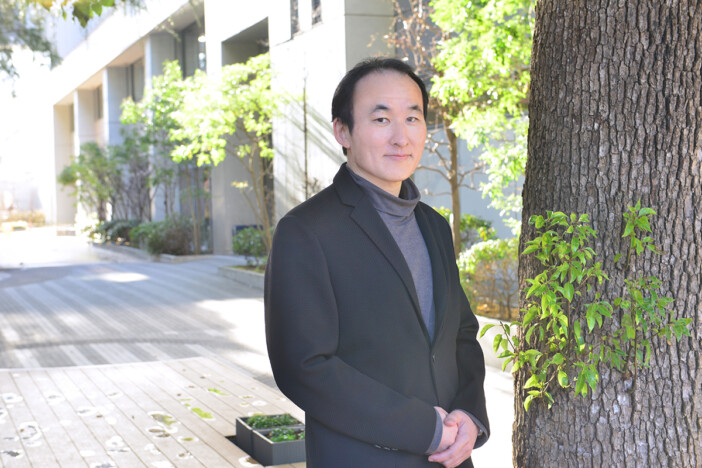連載:道玄坂上ミステリ監視塔 書評家たちが選ぶ、2025年10月のベスト国内ミステリ小説

今のミステリー界は幹線道路沿いのメガ・ドンキ並みになんでもあり。そこで最先端の情報を提供するためのレビューを毎月ご用意しました。
事前打ち合わせなし、前月に出た新刊(奥付準拠)を一人一冊ずつ挙げて書評するという方式はあの「七福神の今月の一冊」(翻訳ミステリー大賞シンジケート)と一緒。原稿の掲載が到着順というのも同じです。今回は十月刊の作品から。
千街晶之の一冊:犬塚理人『サンクチュアリ』(講談社)
犬塚理人の新刊『サンクチュアリ』は、東京地検刑事部に着任して間もない一色瑞穂が、被害者たちに頼まれたから殺したと被疑者が主張している事件、アイドルの遺体の強奪から発展した殺人事件、目撃者の証言を信用していいか判断が難しい殺人事件などの背景を掘り下げてゆく連作スタイルだ。どの事件も意外な企みが裏に存在しており、ホワイダニットの面白さをメインとする優れた本格ミステリに仕上がっている。ところがこの連作、最終話でいきなり話のスケールが巨大化する。果たしてその狙いが何かは、実際に読んで確認していただきたい。
若林踏の一冊:伊坂幸太郎『さよならジャバウォック』(双葉社)
ものの弾みで夫を殺害してしまった女性が狼狽えている場面から小説は始まる。スリラーの本道を行くような幕開けだな、と思っていたら早々に変てこな展開が待ち受けており、頭の中が疑問符でいっぱいになる。その後、物語の開始当初から予想も出来ないような要素が入り込んできて、話がどの方向に転ぶのか分からず頭がますます混乱してきたところで途方もない大仕掛けが炸裂、浮かんでいた疑問符が綺麗に解消されるのだ。著者のデビュー25周年を飾るに相応しい、これまでの作品で培われた騙しの技法が詰め込まれた渾身の一作である。
藤田香織の一冊:葉真中顕『家族』(文藝春秋)
夜戸瑠璃子。通称、ピンクババア。いつもピンク色の服を着用した肥った女は、地元の警察官にも知られるトラブルメーカーだった。血縁関係のない人間を疑似家族として周囲に置き、「躾け」だと暴力をふるう。瑠璃子は前科もあり要注意人物であったが、厄介な存在で、警察は民事不介入を盾に向き合うことを避けていた——。2011年に公になった『尼崎連続殺人事件』をモチーフに、東京・八王子に舞台を移し壮絶な関係性を物語として読ませる。何故言いなりになるのか。何故逃げ出さないのか。理不尽極まりないのにあり得ないとは言い切れぬ恐ろしさが!
橋本輝幸の一冊:梓崎優『狼少年ABC』(東京創元社)
15年ぶり2冊目の短編集。収録作は、ハワイでのロマンスの予感と戦争の影「美しい雪の物語」、級友の墜落死と彼が残した奇妙な写真「重力と飛翔」、カナダの原生林で思い出す幼少期の不思議な体験「狼少年ABC」、同窓会で卒業式CDすり替え事件の犯人探しに挑む「スプリング・ハズ・カム」の4編だ。どれも青春時代をめぐるミステリだが、過去を解釈する話ばかりなので雰囲気は落ちついている。真相にたどりつくまでの多重解決パートは悩み惑う心にシンクロしているようで、謎の解明は登場人物たちの肩を押し、過去から一歩前進させる。
梅原いずみの一冊:市川憂人『もつれ星は最果ての夢を見る』(PHP研究所)
デビュー25周年を迎える伊坂幸太郎の『さよならジャバウォック』と最後まで迷い、今月はハードなSF好きにも本格ミステリファンにもオススメのこちらを。銃殺遺体が見つかった。現場はなんと地球から十光年離れた未開の星。いったい誰が、どうやって? 宇宙規模の不可解な謎は、宇宙開発コンペに参加した主人公と相棒のAIを巻き込み、連続殺人へと発展していく。量子力学が物語の鍵を握っており、中でも「量子もつれ」を犯人当てに絡ませる趣向は圧巻。物理化学が万年赤点の私が一気読みできたので、理系が苦手な方も安心してどうぞ!
酒井貞道の一冊:門前典之『ネズミとキリンの金字塔』(論創ノベルス)
奥付が9月末日ながら10月頭でも店頭で見かけなかった本作を挙げます。舞台は、地域を代表する一族が経営する大病院である。この病院の本館は8階建てのピラミッド形状をしており、中央部は吹き抜けで、最上階は四角錐の頂点から吊り下がっている。この最上階が1階まで落下し、中から死体が発見されるのがメインの事件となる。トンデモとしか言いようのない真相に吹っ飛べ。だがそこに、精神疾患治療の暗い歴史と、痛切な情念が絡み、シリアスな風情も絶妙に薫り立つ。この作家だけが書き得る、建築と大トリックと詩情のキメラ的融合。
杉江松恋の一冊:伊坂幸太郎『さよならジャバウォック』(双葉社)
書評でも触れたのだけど構成から連想したのは旧作『SOSの猿』で、墜ちてきた隕石に当たってしまうような驚きが後半にある。物語の始まり方は東野圭吾『容疑者Xの献身』を連想させるもので、そこからいわゆる倒叙推理小説の展開になるのかと思いきや、すぐに違う要素が入ってきて後はどっちに進む小説なのかまったく見当がつかなくなる。この、ぐるぐると引き回される感覚が伊坂作品の真骨頂で、小説を読む楽しみを存分に味わうことができる。読者ととにかく勝負して、参ったと言わせたい人なんだなあと改めて感じた。参りました。
思いのほか作品がばらけた十月でした。この多様さは、日本の現代ミステリーが抱いている豊穣を示しているものと言えるでしょう。来月はどのような作品が上がってくるのか。楽しみにお待ちください。