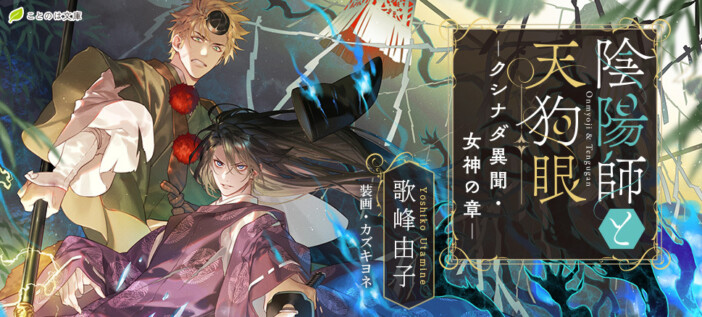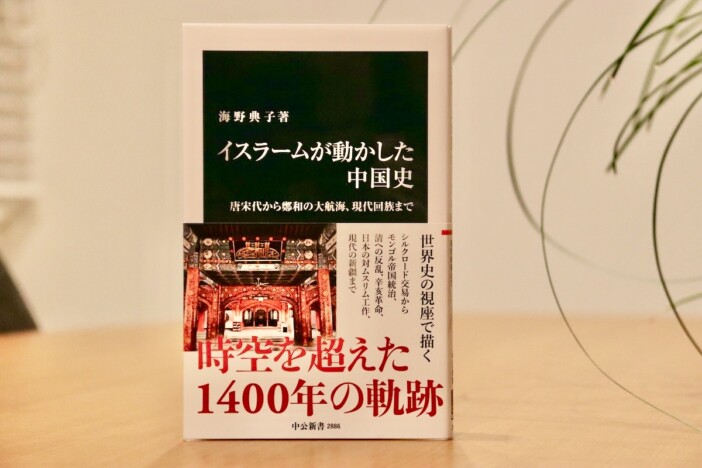『極彩色の食卓』みお ×『わが家は幽世の貸本屋さん』忍丸 × 編集長・佐藤理 ことのは文庫創刊6周年スペシャル鼎談

「ことのは文庫」(マイクロマガジン社)が6周年を迎えた。2019年6月22日の創刊より、読者にそっと寄り添う心あたたまる物語を多く届けてきた。
リアルサウンドブックでは、編集長の佐藤理と、創刊タイトルである『極彩色の食卓』のみお、『わが家は幽世の貸本屋さん』の忍丸3名での鼎談を実施。創刊に至るまでからそれぞれの作品についてまで語ってもらった。
「ことのは文庫」創刊時を振り返って
――さまざまに小説の文庫レーベルがあるなか、ことのは文庫はどんなコンセプトで創刊されたのでしょう。
ことのは文庫編集長・佐藤理(以下、佐藤) レーベルのモットーは「心に響く物語に、きっと出逢える。」。読む人の心を豊かにしてくれるような作品を刊行していきたいと思いました。そのなかで、コミックとはまた違う、文章ならではの表現力をお持ちの作家に書いていただきたいと思い、お声がけしたのがみお先生と忍丸先生。6年経って、刊行される作品の幅も広がり、女性向けのキャラ文芸が増えてきた印象はありますが、しっかりとした文学の読み味があるレーベルとしての礎をつくってくださったのは、まぎれもなく最初に刊行したお二人の作品。ありがたいなあと思っています。
――お二人のことはどのように知ったのですか?
佐藤 みお先生の『極彩色の食卓』は「小説家になろう」、忍丸先生の『わが家は幽世の貸本屋さん』は「エブリスタ」で作品を連載されていて、それが非常におもしろく、僕がめざしたいレーベルのイメージにも合うな、と。
みお 突然、メールをいただいたんですよね。仕事中だったのですが、件名に「書籍化」の文字が見えて、あわてて会社のトイレに駆け込んで、こっそりメールを読んだことを覚えています(笑)。書籍としての刊行(ことのは文庫の創刊)は2019年ですが、実際に書いたのは2014~15年だったので、私自身、記憶があやふやな部分が多いなかで、時がたってもこんなふうに細やかに読んでくださる方がいるんだと胸を打たれました。キャラクター造形を褒めてくださったのも嬉しくて、何度も何度も、メールを読み返したのを覚えています。
忍丸 佐藤さんは作家に対して誠実で、フットワークも軽いですよね。なかなか編集さんで、ここまで丁寧なメールをくださる方はいないし、この方にだったら作品をお任せしてもいいかもしれない、と思って私もお話をお受けしました。
佐藤 なにぶん創刊する前なので、ことのは文庫といってもなんのことだか、お二人にはわからない。ともすると、弊社の名前もご存じないかもしれないと思いましたので、真剣であることをお伝えするにはまず、想いをお伝えしなければ、と。どこの誰かもわからないような状況で、お二人がお受けくださったことが、僕もとても嬉しかったです。
――書籍化にあたっては、どのようなやりとりをしたのでしょう。
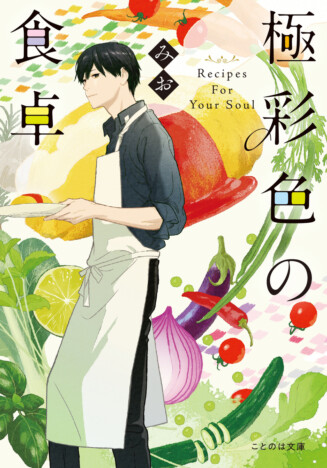
みお わりと全面改稿に近いというか、物語の大筋は変わっていないんですけど、あまり大きな事件が起きない小説だったので、読者の心をつかむような何かを加えていきましょうとご指摘をいただきました。『極彩色の食卓』は、美大生の燕という青年が、天才画家の律子さんと一緒に暮らし始める物語なんですけれど、律子さんの背景もWEB連載時にはあまり書き込まれていなかったんですよね。律子さんの具合が悪くなってしまうシーンも、さらりと書き流していたので、もっと燕の心情を深堀りして、二人の関係がまた一歩深くなる姿を書いた方がいいのではないかとアドバイスをいただいて。
佐藤 僕が記憶しているのは、柏木というちょっと嫌な感じのキャラクターが登場するんですけど、WEBで読んだときは本当に「いやだな」って印象しか受けなかったんですよ。でも、なぜこの人はこんなことを言ってしまうのか、人となりをもっと知りたいなあと思ったら、みお先生のなかにはちゃんと「この人はこういう経緯でこうなっているんです」というしっかりとした造形があった。僕が修正をお願いしたというよりも、みお先生のなかにある世界観をもっと知りたくて、惜しみなく書いていただくようにした、というのが正しいですね。
みお 佐藤さんとお話しするうちに湧き上がってくるものがあって、キャラクターに厚みを持たせていただいたなあ、と思います。私が文字数のカウントを間違えていて、ゲラにするとき文章があふれ出てしまったのですが、それも削るのではなくおさめる方向でご尽力いただき、本当に、しっかりと寄り添ってもらえたという印象です。
佐藤 極彩色フォーマットというのを、臨時で、急いでつくったんですよね(笑)。忍丸先生とも基本的には、そんなふうに原稿の感想を言いあいながら進めていったと思うのですが。
忍丸 そうですね。WEBで読みやすいように描写をだいぶ削ぎ落としていたので、その部分を改めて肉づけしていきましょう、と言っていただきました。『貸本屋さん』は幻想的な世界が特徴だから、その情景が読む人の目の前に広がるような感じにしてほしい、と言われて、そこはとくに意識して改稿した記憶があります。
佐藤 なにより、僕が読みたかったんですよ(笑)。せっかく幽世という舞台にある貸本屋さんなのだから、建物の構造自体も変わったものにしませんか、とご提案しましたよね。外から見たらただの古い二階建てなんだけど、一歩足を踏み入れると、天井がどこまでも伸びていくような場所がいい。 装画を担当した六七質先生は、そういう独特な和風建築を描くのもお好きそうだし、と。
「情景がやすやすと浮かぶ」みおが読む『わが家は幽世の貸本屋さん』
忍丸 主人公の夏織は、幼いころに幽世に迷い込み、貸本屋を営むあやかし・東雲に拾われ育てられるんですけど、義理の父である東雲のキャラクターがいい、刺さりすぎると絶賛していただいたのも覚えています(笑)。シリーズを続けていくうちに、祓い屋の少年・水明との恋愛描写も増えていきましたが、もともと私が書きたかったのは家族の話なので、嬉しかったですね。
佐藤 恋愛要素も、ずっともだもだしているじれったい感じがとても好きですが、ふだんはぼんやりしていて、どちらかといえばポンコツの東雲が、娘のためにあやかし本来の力を発揮していく。そんな親子愛が、ドンピシャで刺さったんですよね。
忍丸 佐藤さんは、ご提案はしてくださるけど「こうしなければだめ」ということではなく、ちゃんと私の書きたいものを書かせてくださるので、それもありがたかったですね。佐藤さんとのやりとりがアイディアを膨らませるきっかけになりました。
みお 私はわりと閉じこもっているようなお話が好きで、燕が無気力な青年なのも、家のなかに閉じ込めてどこにも行かせないようにしたいから、という理由もあります。だから登場するキャラクターの数もそう多くはないのですが、『貸本屋さん』はたくさんのあやかしが登場して、複雑に関係性が描かれるうえ、世界観の奥行きもどんどん広がっていくのに、その情景がやすやすと思い浮かび、物語もテンポよく進んで飽きさせない。私にはできないことなので、初めて読んだときは圧倒されました。あと、資料をしっかり読み込んで書かれているんだろうなと伝わってくるところも。