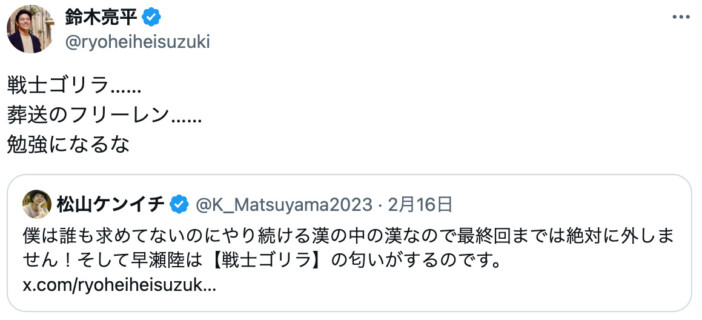『岸辺露伴は動かない 懺悔室』が問いかける「幸せ」と「絶望」――稀代のトリックスター、岸辺露伴が物語を動かすワケ

現在、大ヒット上映中の映画『岸辺露伴は動かない 懺悔室』(主演・高橋一生/監督・渡辺一貴)は、“「幸せ」が「呪い」となって襲いかかってくる”という、なんとも奇怪な物語である。
原作は、荒木飛呂彦の代表作『ジョジョの奇妙な冒険』から派生したスピンオフ・シリーズ『岸辺露伴は動かない』の第1作――「エピソード#16 懺悔室」。初出は、1997年の「週刊少年ジャンプ」30号、「ジャンプ・リーダーズ・カップ」(当時のジャンプ作家10名による読切の競作企画)の1編として描かれた同作は、「原作・岸辺露伴/絵・荒木飛呂彦」という「設定」で発表された。
事前に「スピンオフ・外伝は絶対禁止」と編集部からいわれていたにもかかわらず、あえて「ジョジョ」第4部に出てくる漫画家「岸辺露伴」を語り部として登場させた荒木は、同作が収録された単行本の自作解説ページにて、こんなことを書いている。「最初、露伴が出てこないバージョンをもちろん描いたのですけれど。露伴先生が解説してくれた方が、断然良いと思うでしょ? 露伴先生登場部分をカットして読んでみてください。香りのない食事みたいに感じてしまうでしょう」
ちなみに、この作品における岸辺露伴は、のちのシリーズで描かれているような行動的な人間ではなく、完全な傍観者である。つまり、『岸辺露伴は動かない』というタイトルはここから来ているのだ。
人間を「本」にする異能(スタンド)――「ヘブンズ・ドアー」
また、「体験はリアリティを作品に生む」という信条のもとに漫画を描いている露伴は、「取材」と称して何かと危険な場所へ出かけていき、そこで怪異と遭遇することになるのだが、そうした物語の基本パターンは、この第1作目からすでに完成していたといえよう。
露伴は、理不尽に襲いかかってくる怪異の数々に、(2作目以降は)「スタンド」(具現化されたエネルギー)の「ヘブンズ・ドアー」で立ち向かう。「ヘブンズ・ドアー」とは、人間を本にして、記憶を読み取ったり、指示を書き込んで行動を操ったりすることができる異能だ。
面白いのは、「敵」が同じ「スタンド使い」である「ジョジョ」本編とは異なり、『岸辺露伴は動かない』シリーズで露伴が戦うことになるのは、ほとんどが土着の神や妖怪といった、「スタンド」が思うように使えない(あるいは全く利かない)相手だという点である。それを露伴は、持ち前の知力と機転で毎回なんとか切り抜けていく(「ヘブンズ・ドアー」も、可能な限り併用する)。
なお、前述のように「スタンド」とは、具現化されたエネルギーのことであり、「ヘブンズ・ドアー」の場合は、少年のヴィジョンが露伴の傍に現れて異能を発動させることが多いのだが、今回の映画『懺悔室』をはじめ、前作『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』や、一連のテレビドラマシリーズでも、そうしたエネルギーの具現化(人型ヴィジョンの発現)の描写は一切ない。
また、実写版では、「ヘブンズ・ドアー」のような異能のことを「スタンド」ではなく、「ギフト」(あるいは、単に「能力」)と呼び、作品世界そのものも、『ジョジョの奇妙な冒険』本編とは切り離された、独自のものになっている。
※以下、『岸辺露伴は動かない 懺悔室』の映画および原作の内容に触れています。両作を未見・未読の方はご注意ください。(筆者)
ヴェネツィアで岸辺露伴が聞いた、世にも恐ろしい告白とは
映画『岸辺露伴は動かない 懺悔室』の舞台はイタリア。とある文化交流イベントに招待されていた露伴は、担当編集者の泉京香よりもひと足先に、ヴェネツィアの地を訪れていた。「水の都」の美しい光よりも、戦争、拷問、処刑、そして、幾度も流行したペストの爪痕といった、西洋の闇の部分に強く惹かれる露伴。
そんな彼は、取材のために足を踏み入れた教会の懺悔室(告解室)にて、偶然、水尾という日本人男性の、世にも恐ろしい告白を聞かされることになる(水尾は、露伴のことを神父だと勘違いして、自らの過去を滔々と語り始めるのだ)。

©2025「岸辺露伴は動かない 懺悔室」製作委員会 © LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社
それは、かつて水尾がある浮浪者を理不尽な死に追いやってしまったがゆえに受けた、おぞましい「呪い」にまつわる話だった。「おまえが幸せの絶頂の時、必ず、お前に俺以上の絶望を味わわせてやるッ!」――そんな言葉を遺して死んだ浮浪者が再び彼の前に姿を現した時、水尾は、周到に準備しておいたある“奇策”でその窮地を切り抜ける。しかし、そのために、水尾は浮浪者のゴーストだけでなく、さらにもう1人、別の人間からの呪いをも受けることになるのだった……。
と、ここまでは、原作とほぼ同じストーリー展開であり(ただし、原作では、水尾に相当するキャラクターはイタリア人)、かつ、原作はこのあたりで終わるのだが、映画ではさらに“その先”の物語が描かれていく。