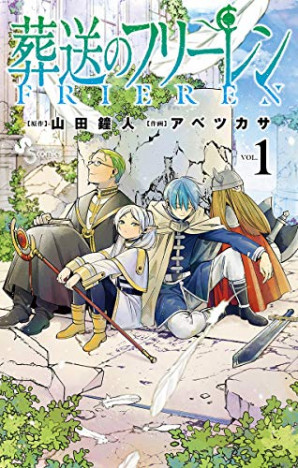漫画業界が注目する『本なら売るほど』舞台はなぜ古書店に? 過去と現在が交差して生み出す「新しい物語」

紙の繊維の間にこもった異なる時間軸の空気が、新たな物語を生み出す
ところで、なぜ「古書」か、という話を最後にしたい。
「ユリイカ」1997年6月号(特集・古書の博物誌/青土社)に掲載されている荒俣宏との対談(「古書はタイムマシンである」)の中で、評論家の紀田順一郎がこんなことをいっている。「つまり古書の魅力というのは、人と本が出会うことによって、時間軸の違ったものが交差し合うことにあると思う。(中略)私は今の時間軸にいる。古書はそれが書かれた過去の時間軸に属している。私がたまたまぼんやりと、その世界のことを知りたいと思っていると、それがある瞬間にパッとクロスする。これは何か人を感動させるものがあると思うんです。人と本がお互いに異なった時間軸に存在しているということは、新刊書ではありえない」
また、次のような言葉も興味深い。「古い雑誌があるとしますね、それが仮に、明治二〇年の三月一日に出た雑誌だとすると、明治二〇年三月一日現在の空気が、この紙の繊維のあいだにこもっているんです。開けるとその空気がぱっと立ちのぼる」
まさに魔法という他ないが、古い時代の雑誌や書籍を開いたとき、「紙の繊維のあいだ」にこもっていた過去の「空気」が立ちのぼるというのは事実である。そしてその立ちのぼった過去の空気――すなわち、異なる時間軸の幻影が、時を越えて現在と交差し、「新しい物語」を生み出すのだ。だからこそ、児島青は『本なら売るほど』の舞台を、新刊書店ではなく、古書店にしたのではないだろうか。
いずれにせよ、過去と現在、虚構と現実が入り混じる十月堂の棚には、店主が選りすぐったさまざまな物語が収められている。そのうちの1冊はもしかしたら、『本なら売るほど』という作品に魅せられた、あなた自身の物語であるかも知れないのだ。