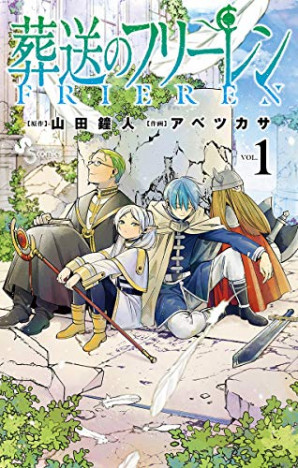漫画業界が注目する『本なら売るほど』舞台はなぜ古書店に? 過去と現在が交差して生み出す「新しい物語」

おそらく、いま最も漫画界で注目されている作品の1つといっていいだろう、児島青の『本なら売るほど』(KADOKAWA)の第2巻が4月15日に発売された。
主人公は、町の小さな古本屋「十月堂」を営んでいる青年。ロン毛を後ろで束ねた、一見けだるい感じを漂わせている若者だが、寺田寅彦の随筆から岡本綺堂の『半七捕物帳』、果ては、近藤ようこ版の『高丘親王航海記』(原作・澁澤龍彥)にまで目を通しているなかなかの読書家であり、こと「本」に関しては何かと熱くなってしまうあたりが憎めない。
物語は基本的に1話完結形式で進行し、毎回、十月堂を訪れた愛書家たちの夢や苦悩が描かれていく。つまり、物語の表面上の主人公は十月堂店主で間違いはないのだが、ある意味では、毎回出てくる少々風変わりな客たちもまた、“それぞれの物語”の主人公として描かれているのだ。
そう、あらためていうまでもなく、人は誰しも「人生」という名の「物語」を日々生きているわけであり、その物語の中では、それぞれが脇役ではなく、主人公だ。そして、この『本なら売るほど』という物語では、そんな別々の物語(=別々の人生)を生きているはずの主人公たちが、「古書」を通じてつながっていく。
古書探しとは、手軽なトレジャー・ハンティングである
さて、第2巻に収録されている物語の中では、とりわけ第7話「鷹の目を持つ男」が素晴らしい。
※以下、『本なら売るほど』第7話の内容に触れています。未読の方はご注意ください。(筆者)
物語の冒頭――ひょんなことから、サラリーマン風の壮年男性が十月堂を訪れる。実はこの壮年男性、若い頃に漫画家を志していたこともあり(そのことは第11話でわかる)、棚で鴨沢祐仁の作品集『クシー君の夜の散歩』を見つけ、購入しようとする。
と、その時、十月堂店主は本を手に取ったまま、微妙な表情を浮かべ、こういうのだ。「この本、今日入荷したばっかです。もうちょっとうちの棚にいてほしかったな」
まず、この場面が素晴らしい。なぜなら、基本的に返品可能な本を並べている(一部例外を除く)新刊書店とは異なり、古書店の本はすべて店主が買い取った、いわば店主の「蔵書」であり、そんな自分にとって大切な“宝物”が売れていくことの寂しさと嬉しさが入り混じった複雑な感情が、よく表れているからだ。
そして、もう1つ。後日、大型古書チェーン店で鉢合わせになった壮年男性と十月堂店主が、店を出て一緒にラーメンを食べに行く場面があるのだが、そこでのふたりの会話も、(本好きとしては)なかなか考えさせられるものがある。
店主は、大型店の存在価値を認めたうえで、こんなことをいう。「俺の店は、大型店の手のひらから零(こぼ)れた本やお客さんのための店にしたいんで……」
一方、そんな「大型店の手のひらから零れた本」を愛する「お客さん」の1人――壮年男性はこういう。「宝探しはすぐ終わってはつまらないですからね。お目当てに辿り着かずとも、思わぬ収穫を得ることもある。あなたの店を見つけたときもまるで、光る鉱脈を発見したような興奮がありましたよ」
いまや、新刊書はいうまでもなく、レアな古書も、ネットで簡単に入手できる時代になってしまったが、このふたりの会話に共感できる人なら――つまり、本を探す手間を楽しめる人なら、間違いなく『本なら売るほど』という作品を好きになるはずだ。