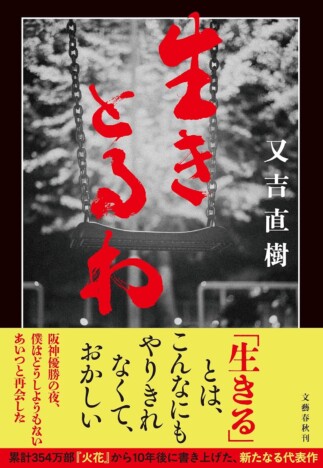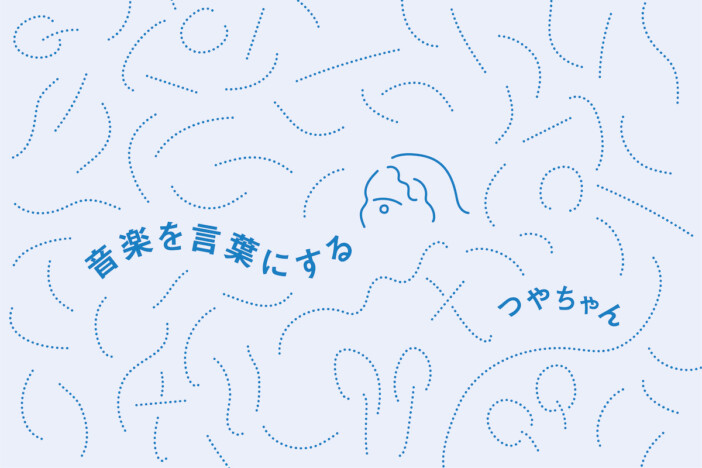【連載】福嶋亮大「メディアが人間である」 第9回:パラ知能としての生成AI――あるいは言語ゲームの多様性

3、唯名論の勝利
このいささか奇妙なパラ知性のもたらす認知上の混乱を鎮静化するのに、哲学の考えが役立つだろう。ここでは言語のテーマに絞ってみたい。
もとより、コンピュータの実行する記号的な操作にはどこか皮相なイメージがつきまとう。それは、電子的な記号演算が、その背後にある実在物との対応を志向していないからである。哲学史の文脈に置き換えれば、それは実在論(リアリズム)ではなく唯名論(ノミナリズム)がコンピュータの思想において優勢であることを意味する。J・D・ボルターがかつて指摘したように「コンピュータの思想は唯名論の勝利である。コンピュータが取り扱う記号はそれだけでは無意味である。なぜならば記号の「背後」にあってそれを支えるべき実体がないからである」(※4)。
インターネット上の人間の言語使用にも、この「記号の背後」をもたずに動作する唯名論が根をはっている。現に、Aという情報を与えられれば自動的にBと反応する、ほとんどボットのように訓練されたアカウントは、ソーシャルメディア上では珍しくない。ユーザーは実在(背後)の有無を気にせず、記号に対する記号の反応だけで、いつまでも書き込みを続けることができる。そのとき、ユーザーが人間なのか機械なのかは判別が難しくなるだろう。
このような唯名論的な記号操作は、大規模言語モデル(LLM)を用いた生成AIにおいて、いっそう顕著になる。この数理モデルは大量の文書データの用例を学習したうえで、ユーザーの入力した文に続く確率の高い語を出力する。語と語の関係を大量に学習することによって、現実をまったく体験したこともないAIが、驚くほど巧みに自然言語を使いこなしているように見えるのだ。
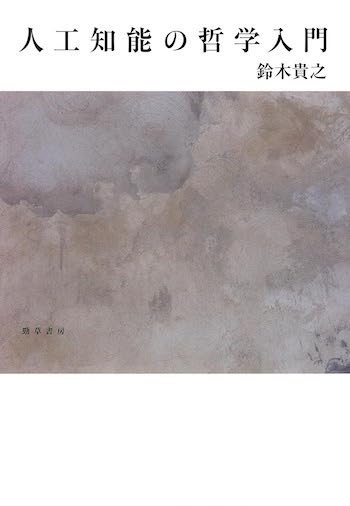
それは、いわゆる記号接地問題(記号と現実の結びつきを問う問題)にも新しい展望を与える。常識的には、現実世界への接地を欠く記号の連なりは意味を欠く(=AIは意味を理解せずに演算結果を出力している)ように思えるが、哲学研究者の鈴木貴之が指摘するように、大規模言語モデルはその常識への反証となっている。なぜなら「大規模言語モデルは、記号接地を欠いているにもかかわらず、さまざまな自然言語処理課題をかなりの程度に実行できるからである。言語上のやりとりを見るかぎり、人間と大規模言語モデルのあいだには、決定的な違いはないように思われるのである」(※5)。
もとより、意味の定義を――つまり「意味の意味」を――考えるのは、それ自体が難問である。「意味」そのものが多義的なので、一つの「意味」には収束しない(哲学者のジャン゠リュック・ナンシーに言わせれば「意味の意味」に統一性を与えるのは不可能である(※6))。記号と現実の対応を「意味」の根拠と見なすならば、大規模言語モデルに基づくAIは意味を理解していないことになる。しかし、鈴木が言うように、語の意味を「高次元空間におけるベクトル」と見なすならば(※7)、語と語の共起確率を表現する大規模言語モデルも、意味=方向をもつことになるかもしれない(ちなみに、フランス語のsensには「意味」だけではなく「方向」の意味がある)。
いずれにせよ、現状の生成AIは(それが望ましいかは別にして)言語のノミナリズム的な操作だけでも――つまり実在物にまったく接触しなくても――外見上は有意味な自然言語を用いることができる。このような知性的な機械の出現は、「意味の意味」にも何らかの修正を生じさせるのではないか。
※4 ジェイ・デイヴィッド・ボルター『チューリング・マン』(土屋俊他訳、みすず書房、1995年)117頁。
※5 鈴木貴之『人工知能の哲学入門』(勁草書房、2024年)170頁。
※6 渡名喜庸哲「ナンシーとレヴィナス――sensについて」『レヴィナス 顔の向こうに』(青土社、2024年)121頁。
※7 鈴木前掲書、146頁。
4、多様な言語ゲームの交差
ここまで来れば、人間の言語とAIの言語を峻別する根拠は次第に弱くなってくるように思える。この両者の言語には、表向きは決定的な違いはない。しかし、それでも両者では何かが違うという印象も依然として残る。だとしたら、何が違うのか。
この問題を考えるのに、ウィトゲンシュタインが提示した「言語ゲーム」と「生活形式」という概念は今なお有効だと思われる。というより、生成AIの登場によって、ウィトゲンシュタインの考えがより具体的かつ鮮明に捉えられるようになったと言うべきだろう。
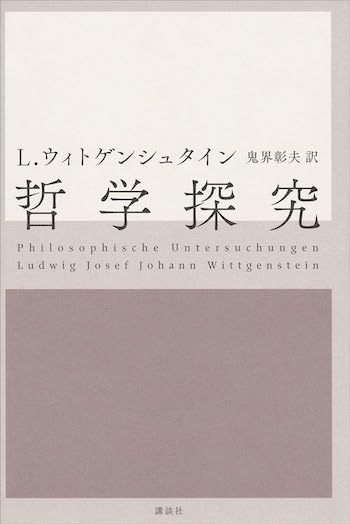
よく知られるように、ウィトゲンシュタインは『哲学探究』で、言語を話すことを「一つの活動ないし生活形式の一部」と見なし、その探究のために「言語ゲーム」という概念を導入した。彼にとって、言語ゲームは本源的に「多様」である。その多様性は「言語という道具とその使い方の多様性、語や文章の多様性」と切り離せない(23節/『哲学探究』の引用は大修館書店刊[藤本隆志訳]を参照したが、訳語を一部変更した)。言い換えれば、言語そのものは存在しない。ただ、そのさまざまな使い方(ゲーム)があるだけだ。
そして、この「使い方」を規定するのが「生活形式」(Lebensform)である。生活形式とはあらかじめ言語に与えられた環境であり、いかなる言語もその外に出ることはできない。つまり「活動」から独立した言語は存在しない。ウィトゲンシュタインは生活形式(活動)を具体的に定義するわけではないが、それはおおむね次の「自然史」という概念と対応するだろう。
命令し、問い、話し、しゃべることは、歩いたり、食べたり、飲んだり、遊んだりすることと同様、われわれの自然史の一環なのである。(25節)
ここでAIの問題に戻ろう。大規模言語モデルに基づく生成AIも人間も、一見すると同じ言語を同じように使っている。しかし、それぞれの言語の根ざす「生活形式」は根本的に違っている。それは、両者が異なる「自然史」を歩んできたことと関わる。
人間は協働の道具として言語を利用するという長い「自然史」を歩み、そのプロセスで言語を用いて「命令」したり「おしゃべり」したり「質問」したりするという用法を発明してきた。それに対して、生成AIはコンピュータの進化という「自然史」のなかで――さらには唯名論的な情報環境という「生活形式」のなかで――記号の「接地」を考慮することなく言語を使用する。より正確に言えば、AIそのものは生(生活)をもたないので、その言語使用はいわば「生活なき生活形式」に先行されている。
繰り返せば、現状のAIは語と語の共起確率をもとにして、文を出力する。そのような演算的な言語使用は、われわれの「生活形式」にも部分的に含まれるが、AIはそれを純化させたのだ。その反面、AIはその「生活なき生活形式」ゆえに「命令し、問い、話し、しゃべること」をしない。それはAIが「歩いたり、食べたり、飲んだり、遊んだり」しないのと同じである。さらに、AIはある対象を新たに「名指し」(命名)することもしない。ウィトゲンシュタインは名指しを「神秘的な出来事」と呼んで、それを「対象に洗礼を施すようなもの」と形容した(38節)。AIの言語ゲームはこのような「神秘」や「洗礼」とは今のところ無縁である。
この場合、機械と人間の言語ゲームが異なるからと言って、お互いを理解できなくなるわけではない。AIからの情報の取得をチャットの形式に落とし込めば、機械の言語ゲームは人間の言語ゲームにひとまず翻訳されるだろう。それでも、生活形式の差異やギャップは消えない。言語という道具を、人間とはあくまで異なる使い方をする≪パラ知能≫が現れたこと――それが言語の歴史における画期的な事件なのである。

ウィトゲンシュタインをフランスで初めて紹介した古典学者のピエール・アドは、かつて「われわれよりも古代人のほうが、複数の言語ゲームのあいだの差異に対する鋭敏な感覚を有していた」と指摘した(※8)。今日、われわれに求められているのは、まさにこの言語ゲームの多様性に対する敏感さである。AIを蔑視したり(子どもでも知っていることを知らない!)、逆にAIを神的な装置(あらゆることを知っている!)としてあがめたりする、そのようなありふれた態度は、AIという隣人の言語ゲームを不当に評価している。そもそも、言語ゲームどうしのあいだに優劣があるわけではない。言語ゲームはたんに多様なのであり、われわれはその事実を尊重するべきなのだ。
むろん、生成AIそのものは今後も進化し、今とは異なる多くの機能を獲得するだろう。それでも、生活形式(自然史)に根ざした差異は決して消えることはない。ただ、両者の言語ゲームが完全に異質ということにもならない。なぜなら、両者の言語ゲームは、ウィトゲンシュタインふうに言えば「家族的」に類似しているからである。複数の言語ゲームは相互に隔絶しているのではなく、むしろ「互いに重なりあい、交差しあう」(67節)。このような言語思想の重要性を際立たせた点で、生成AIは教育的な「隣人」なのである。
※8 ピエール・アド『ウィトゲンシュタインと言語の限界』(合田正人訳、講談社、2022年)136頁。