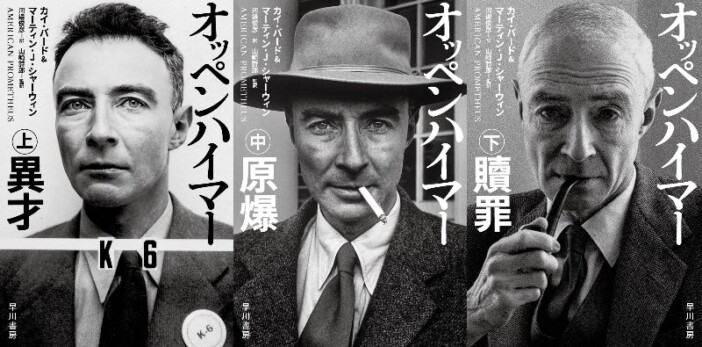ポール・トーマス・アンダーソンが「時代遅れのヒッピー」に託したものーー病んだアメリカと『インヒアレント・ヴァイス』

そもそもインヒアレント・ヴァイスの意味とは?
と、疑問を呈したところで一見関係なさそうな話をしたい。原題と邦題についてだ。映画にせよ小説にせよ、英題を日本語にローカライズするのは骨が折れるもの。音の響きも違えば、意味するところのズレも生まれ得る。例えば駆逐艦と潜水艦の戦いを描いた1957年の映画『The Enemy Below』に対する『眼下の敵』という邦題は見事と言うほかない。『下に潜む敵』ならなんだかH.P.ラブクラフトの小説っぽくなってしまう。ここに「眼下」なる言葉を持ってきたセンスにはいつも震える。口に出しても気持ちいい。シンプルながら名訳だ。
一方で2015年の映画『The Big Short』に対し『マネー・ショート 華麗なる大逆転』と題したような微妙な例も枚挙にいとまがない。ショートって空売り(信用売り)のことなので、その前にマネーなんて置いたら意味不明でしょう。一見しての分かりやすさを重視して動員につなげることが映画配給会社の命題なので仕方ないかと納得もできるが、なんだか資金繰りに苦しむ中小企業の映画みたいなタイトルになってしまった。こういったケースは良例の100倍以上存在するだろう。あるいはそれ以上に。
では「Inherent Vice」が「LAヴァイス」になるにはどのような過程があったのだろう。本書の訳者あとがきにて、その点が詳細に記されており興味深い。原題に忠実な「悪の潜み」といったものから、「重力の虹」に寄せた「時の傷」なるものまで、多くの候補が俎上に乗せられたようだ。だが最終的に物語の持つ軽妙なバイブスに合わせて、現在の邦題を得たとのこと。となると、映画化された際にも同じ邦題が連なるのが通例のはず。しかし、ここで声を上げたのがPTAその人。改題を拒否する鶴の一声により、映画の邦題は『インヒアレント・ヴァイス』となった。この出来事、つまり「インヒアレント・ヴァイス」という言葉にこそPTAが原作からの改変にあたって重視したポイントの答えがある。
そもそもインヒアレント・ヴァイスとは何を意味する言葉であろうか。これは直訳すると「内在する瑕疵(かし)」となる。生モノは腐る、卵は割れる、チョコレートは溶ける、といった起こり得る固有の欠陥を指すものだ。保険業界でも「発生する可能性が極めて高い特性なので、これに関するリスクは負いませんよ」との意味合いで使われる。内在する瑕疵の解釈を広げてゆくと、多くのものを当てはめることができよう。時間は流れる、人は老いる、男女は別れる、地球はいつか崩壊する、宇宙もいずれは終わる。ピンチョンが短編「エントロピー」でモチーフとして取り上げた「エントロピー増大の法則」と「インヒアレント・ヴァイス」はその意味においてつながりを見せる。
エントロピー増大の法則あるいは熱力学第二法則とは、具体例を挙げるとこのようになる。「熱湯は放置しておくと冷めて水になる」「冷めた水はひとりでに熱湯に戻ることは無い」。すなわち、自発的な変化はエネルギーを低級化させるのだ。この考え方は人間組織においても応用される。常に同じメンバーから構成される組織からは活力が失われてゆき、生産性が下がる可能性が高い。なので企業は定期的に組織の変成を変更し、フレッシュさを保とうとする。ではより視座を高くして、主語を国家におけるシステムに置き換えたらどうなるのか。そう、それが回り始めた瞬間よりシステムは崩壊へと向かう。システムの崩壊の要因について考えると、システムそのものが孕む自己崩壊性(エントロピー増大の法則)、言い換えると組織的な腐敗、さらには内部に存在する造反分子がそれにあたるだろう。システムに反する者——それもまた直接的な意味で「内在する瑕疵」である。
『インヒアレント・ヴァイス』は先に述べた通り、アメリカが高度資本主義へと突入する1970年が舞台の物語だ。資本主義においては、金を持たざる者は労働力を提供し、持つものは労働者へ対価を支払うという構造が大原則となる。労働力、つまり人的資本に対を成すのは物的資本——土地に代表されるものだ。ここで、この物語における謎と答えの構造を思い出してほしい。シャスタの今カレである不動産王ウルフマンはなぜ失踪したのか。この謎とその答えを。
ウルフマンは土地を買収しそこに住宅や商業施設を建てるデベロッパー。ウルフマンの次なる野望はLAにおけるカジノの誘致だった。しかし、ここで資本主義に毒された彼の魂を転換させる出会いが生じた。シャスタである。愛と平和の思想に満ちたシャスタはウルフマンにヒッピー思想を与え、彼は回心する。「誰もが平等に、タダで住める住宅を提供しよう!」とウルフマンは思い立つ。しかし、資本主義への背反と言える行為にシステムが黙っているわけがない。土地は単なる土と砂よりなる区画ではない。国家をなす一部……国土なのだ。FBIはウルフマンを拉致してヒッピー洗脳を解くべく精神病院へとブチ込んだ。これが不動産王失踪事件の真実であった。つまり、システムにおけるエラーの消去、バグ取りと言えよう。
そして国家側はこう考えた。ウルフマンにエラーを起こさせたのは誰か、ヒッピーの小娘だ、と。シャスタは「お前はインヒアレント・ヴァイスだ」と宣告され、ウルフマンとの関係を裂くべく遠くの地へと放逐される。すなわちこれはシャスタ個人を指す言葉というより、ヒッピー思想そのものが資本主義によって成り立つ国家における内在する瑕疵であることを意味する。そもそもヒッピー自体が先の見えない冷戦、そして泥沼のベトナム戦争へのカウンターとして発生した、国家が生んだムーブメントだ。まさにシステムを回すうえで避けがたく生じるインヒアレント・ヴァイス。そう、資本主義に依存する国家にとって、愛と平和は回転の恒常性を保てなくする瑕疵なのだ。ヘイト、対立、敵、戦争。これらがあって初めて国家は資本と共に回転できる。歴史の教科書を読んだ人々なら薄らと理解している、微妙に口に出しづらい矛盾を明文化してみよう。人類が目指す恒久的な平和と、国家のシステマティックな運営は全く別のものだ。不動産王でもある現アメリカ大統領がそれを体現してくれているので、この言説についてはネットニュースの国際欄を読む方がよっぽど理解できるかとは思うが……。
ラリー・スポッテッロ、通称「ドック」の役割
でも、これってなんだか病んでない? 病める者に必要なものはなんだ、もちろん医者だ。ここで主人公の役割が明らかになる。ラリー・スポッテッロ、通称「ドック」。なぜ彼がドックと呼ばれるかと言うと、これは「LAヴァイス」に明記されているのだが、探偵業を営む以前に取り立て人として雇われていた時期、自白剤の注射を携帯する姿が「医者みたいに見える」というわけで「ドック=センセー」なる渾名が与えられた。このエピソードで重要なのは、「センセー」が意味するところが博士や教授ではなく医者であることだ。
ドックの視点で紡がれる物語に身をゆだねると、あっちへフラフラ、こっちへフラフラ、たまに行動しては、でもそれが何にどうつながっているのかよく分からない。でも分からないなりに大団円……と観客は煙に巻かれた気分になるだろう。だが、ドックの「役割」に注視すると彼の行動と結果が明確化される。ドックは物語で何を果たしたか。LAにはびこる殺し屋を射殺し、棚ぼた的に国家のスパイとして雇われていた男を解放した。これがドックの功績だ。LAにはびこる殺し屋とは、市警に雇われて汚れ仕事をしていた男たち(具体的にはグレン・チャーロックとエイドリアン・プロシア)である。つまり彼らの役割は法の外で働くシステムの潤滑剤だ。そして、システムと法の間隙を埋める存在として抽象化されたものが、劇中で暗躍する組織「黄金の牙」なのである。効率的な運営を求めるシステムにとって、法律など邪魔でしかない。現アメリカ大統領によるどう見たって違憲な大統領令の連発や、ドキュメンタリー映画『カルテル・ランド』(2015)で映されたメキシコが麻薬組織なくしては国家として成り立たない残酷な現実がその証左と言える。これらによって成り立っているものが健やかなわけがない。病んでいるのだ。だから医者が来た、ドックが現れた。
つまりドックとは、病めるアメリカの創傷治療者なのだ。だからこそ彼はシステムの対極である存在でなければならなかった。ヒッピーである必要が、高度資本主義社会に取り残された「時代遅れのヒッピー」である必要があったのだ。PTAもこの構図に気が付いたに違いない。だからこそ自分の作家性との共振を見出だし、原作の要素を膨らませてドックにより強く時代に取り残された寂寥感を加えたのではないか。
そして原作と大きく違う顛末を迎えるキャラクターが存在する。ドックのアルターエゴその2、ビッグフットだ。原作のビッグフットは暗躍する組織を追い退場する。対して映画のビッグフットは事件がひと段落した後にドックの前に現れ、突然大量のクサをモシャモシャ貪り食う奇行に出る。忌み嫌っていたヒッピーの象徴、大麻を自分の腹に収めてゆく仇敵を前にしたドックはホロリと涙を流す。とても寂しそうに。
自分と同じく時代に取り残されていた男が、60年代を文字通り消化し、そして新たな時代に旅立ってゆくことを決意した。ここに表れているものは、システムの一部を破壊した結果として次の時代が良いものになるかもしれないと考えるドック(ビッグフット)と、そしてそれでも「センセー」としての役割を果たすために過去に留まり続けなければならない圧倒的な諦めを背負ったドックである。システムの創傷治療者としてのドック、システムに内包されながらも虐げられ反旗を翻すビッグフット、システムにエラーをもたらす愛と平和の表象のシャスタ。それぞれがインヒアレント・ヴァイスとしての役割を持ち、だからこそ彼らは三位一体を形成する。しかし、その関係性は恒常性を保たない。なぜならそれがインヒアレント・ヴァイスというものだからだ。
原作と映画のラストシーンは共に霧の中のサンタモニカ・フリーウェイで展開される。外も見えない中、そろりそろりと運転するドック。原作では一人だが、映画では彼の隣にシャスタが座っている。虚ろな様子でシートに身を預けるシャスタの唇から言葉が漏れる。「決してヨリを戻したわけじゃない」。役割を与えられた者たちの、どこへも行けない諦観が何も見えない霧の中とオーバーラップする。しかしドックの様子は少し違う。霧中に差す道路照明の光にソッと目を向けるのだ。その眼差しはスクリーンを観る我々のものと交錯する。ビッグフットは去った、シャスタは戻ってきたが、そこにいるのは美しい思い出ではなく生身の現実だ。生モノは腐る、卵は割れる、チョコレートは溶ける、そして時は逆行しない。ドックは60年代に留まらざるを得ない存在だ。しかしラストシーンの彼はもう過去に思いを馳せてはいない。禊を済ませて自分の役割を明確に理解した、より高次の存在としてそこにいる。それこそ『ファイト・クラブ』(1999)のラストシーンと近しい。タイラー・ダーデンと一体化して変化を果たした主人公は、崩壊するビルを見てこう呟く。「これからすべて大丈夫になる」と。ならば映画を観る人々を見つめるドックは現代に、国家に、システムに、我々に対して何を思い、どのような行動を起こすのだろう。ワッツ・アップ・ドック?